ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
第四章・漂流・その5
何かに群がるカモメに引き寄せられ、明らかに難破船のものと判るイカダを見つけた漁船は、近付きはしたものの、そばへ寄るのには慎重だった。仲間内の話で、軍艦が沈没して漂流した人の中には、精神状態が不安定になっている者がおり、突然拳銃を撃ちかけてきたりする場合があると聞いていたからだ。
まして、一昨日はこのあたりでイギリスとドイツの艦隊同士が戦ったというから、イカダは沈没した軍艦のものである可能性が高い。
「誰も動かないわね」
「昨日は寒かったからな。こんなイカダじゃ死んじまうよ」
放っておくとカモメの餌になってしまう。今は遠巻きにしているけれども、奴らが一度群がれば、追い払うだけだって面倒だ。帆を操った漁師は、回り込んで風上からイカダへ近付いた。動いているものがいれば、カモメは近寄ってこない。
「おーい、誰か生きているかぁ。生きているなら返事をするか、手を振ってくれ」
誰も動かない。皆、死んでしまったのか。
「気味悪いわね。放っておきましょうか」
「そうもいかんさ」
漁師は船を寄せ、体を乗りだして確かめるようにイカダを押してみる。急造りのイカダは、雑多な木材を繋ぎ合わせたもので、ロープが緩み、やっと形を保っているだけだ。
「ドイツ軍?」
「そうだな。あの制服はそうだ」
「ねえ、放っておきましょうよ」
漁師は女房の言葉に応じず、裸足になってイカダへ乗り移る。万一の場合でも、これなら泳げるからだ。
足を乗せた部分の木材が沈む。イカダはやっと浮いているだけに近い。
「こいつらはイカダの組み方も知らんのかな。もっと縦横に重ねなきゃ、すぐに壊れるし、水面からの高さも取れないだろうが」
10人ちょっとが乗るには、イカダは広く作られすぎ、そのために厚みが足らない。この高さじゃ、波が簡単に上がってきて、体を濡らしてしまうじゃないか。体が冷えてしまうぞ。一番近い男の足に触れてみれば、氷のように冷たい。生きちゃいないな。次の足も同じだ。
「みんな、死んでるんじゃないの?」
「確かめてみるさ。戦争があったのはおとといの午後だ。二晩なら、生きている奴もいるかもしれない」
この時期だ、海水に漬かっていても、生きていて不思議ではない。死んではいるが、まだ温もりのある死体がひとつあった。明らかに生きている男が二人。
「二人生きているな。船を繋いでこっちへ来い。手を貸してくれ」
女房はしぶしぶと船をイカダに結びつけ、おっかなびっくりイカダへ乗り移る。
「生きてるって、どれ?」
「この二人だ。そっちのは死んでいるが、まだ暖かい」
全部で十数人。正確に何人か、漁師は数え方を知らない。
「2週間分だわね。日曜、月曜…最後が土曜で、二回りだから」
「チェッ、教会で教わったのか?…どっちから運ぶかな」
「助けるの? ドイツ人よ」
「まだ生きているんだ。放っていくわけにもいかないさ」
「知らん顔して死なせたんじゃ、神様に叱られるかしらね」
「そういうこった」
漁師は息をしている二人の耳に口を寄せ、呼びかけてみる。かなり大きな声を出しても、一人は反応しない。もう一人も、わずかにうめいただけで、それ以上の反応ではなかった。まだ生きているというに過ぎず、回復するかは神様しだいってとこだな。
もう一度確かめても、生きているのは二人だけだ。やけに大柄で、士官の制服を着たのと、ひとまわり小さな水兵の格好をしたのと。どちらもがっちりした体で、けっして痩せてはいない。だからこそ、生きているのだろう。
士官を助ければ、なにかしか恩賞は大きいかもしれないが、夫婦はこれまでに、何度か村を訪れたドイツ軍の横暴に腹を立てていたし、軍艦に威かされたこともある。そのときのドイツ海軍士官の横柄な態度に、嫌な思いをさせられていたから、その嫌悪感が二人の間の暗黙の了解となり、まず水兵のほうを助けださせた。
重い体を持ち上げるには、足場が悪すぎる。二人は引きずるように体を運び、ようやく船に乗せた。まったく動いてくれないから、船べりを越えた後は、落としたも同然だった。
わずかにうめき声をあげ、生きていることを示した水兵だったが、それっきり静かになっている。エンジンも天蓋もない帆装漁船の中で、暖をとる最も確実な方法は、火ではなく、自らの発生する熱を逃がさず、発熱を増進することである。
濡れた衣服をはぎとられ、強い酒を含まされた水兵は、ありったけの毛布にくるまれ、船底に寝かされた。港へ戻るまで生きているかどうか、それは彼の生命力に聞くしかない。
名前も言えない水兵を落ちつかせた夫婦は、もう一人の生存者を運ぶため、イカダへ戻った。そばへ寄っていたカモメが、慌てて文句を言いながら退く。
「あれえ、息が止まってるよ」
鼻の前に手をかざしても、何も感じられない。士官の制服を着た男は、隣にあった熱源を奪われたために、体温が下がってギリギリの淵を越えてしまったらしい。呼びかけても、叩いても反応はない。服を開き、胸に手を入れても、心臓が動いているようには感じられなかった。胸ポケットに何か堅いものがある。
人間は、こういう状態からでも蘇生しないわけではないが、そのためには多大の努力が必要だ。夫婦はすでに、それが必要かもしれない一人を抱えている。顔を見合わせた二人は、死にかけている男のことは諦め、生きている男に全力を傾けることにした。
彼ら二人だけでは、小さな漁船に遺体のすべてを回収するのは難しかったし、硬直した遺体は重なり合い、絡みあって動かしにくかった。
漁師夫婦は、風に逆らってまでイカダを曳いて帰る気にもなれなかったから、生存者の他には何も回収せず、イカダの材木を繋いでいたロープを切り、イカダをバラバラにして、遺体は海へ落ちるにまかせたのである。けっしてドイツ海軍に好意を持っていなかった彼らとすれば、それでも精一杯の善意だった。
目の前で見ているカモメには、嬉しくない行為だろう。ギャアギャアと文句を言っている。死体がまた浮かんでくるには長い時間が必要だし、海中には海中で、今日を生きるための栄養源を求めている存在があるのだ。
「なに? それ」
「時計だよ。見ればわかるだろ」、手から鎖でぶら下がった金色の時計が、朝日にきらめきながらクルクルと回っている。
「盗ったの?」
「人聞きの悪いこと言うなよ。一人助けた礼に貰っただけさ。沈めちゃえば、誰にも使えなくなるしな。まだ動いてるんだから」
「…ま、いいか。このまま帰るんじゃ、今日は一文にもならないしね」
「そういうこった」
カイルハック副長が、精魂込めて書き上げた報告書は、そのイカダの一片に縛りつけられており、抱きかかえるようにしていた副長の遺体に覆われ、漁師の目にとまらなかった。
やがて、もう誰も見ていない海の中で、副長の体は報告書の袋を抱えたまま、バラバラになったイカダから転げ落ちた。しばらくは制服が空気を含んで浮いていたけれども、やがて浮力を失い、沈んでいく。浮力の大きな袋は、その腕の中から抜け出した。
袋は繋がれた木材とともに流れてゆき、それっきり誰の目にも触れなかった。
… 完 …
終わりに
ジュットランド海戦における『ヴィースバーデン』の戦死者
士官27名、下士官兵543名、合計570名
これは、ドイツの公刊戦史である北海海戦史からの数字です。これには、戦死者と負傷者、捕虜の統計数字があるものの、『ヴィースバーデン』を含め、無傷の生存者には数字がありません。乗組員の総数は、戦時増員のために把握できませんから、何人生きていたのかは判らないのです。
乗組員が全員死亡したような、特別な艦の場合には本文中に記載があり、本艦ではツェンネという焚火長が唯一人生存したとされています。ただ火夫とだけ書いているものや、ファースト・ネームをヒューゴー Hugo と特定している資料もあります。
この唯一の生存者というのは、ヘリゴランド・バイト海戦での沈没艦、軽巡洋艦『ケルン』にも存在し、ただ一人の生存者である機関員が、海戦の2日後に奇跡的に救出されたといいます。
この、奇妙に共通した奇跡的な生存者には、単純に信じることのできない部分が感じられます。
まず、防御甲板のある巡洋艦は、緩慢に沈没した場合には比較的生存者が多く、『ケルン』と同じ日にヘリゴランド・バイト海戦で『ヴィースバーデン』同様めった打ちにされ、魚雷の命中もあった『マインツ』では、およそ4分の3の乗組員がイギリス艦に救出されています。
同艦の場合、やはり艦上はメチャクチャに破壊され、煙突も半数以上が撃ち倒されています。ただし、命中した砲弾はすべて15センチ以下のもので、重砲弾では撃たれていません。最後には降伏し、自沈のために海水弁を開いたとされていますが、たとえ敵がいなくても、自力で帰るのは困難な程度の損傷だったと思われます。
また、同海戦で沈没した他の二隻についても、一部がイギリス側捕虜の場合もあるものの、多数の生存者があります。
ジュットランド海戦の場合でも、爆沈艦を除き、他沈没艦の乗組員は、大多数が救助されたか、まったく生存していないかです。特に、『ヴィースバーデン』の近くで沈没したドイツ駆逐艦『V48』にも生存者がありません。本文中で、「低速で南のほうへ逃げていった」とされている駆逐艦です。
この艦は沈没の直前まで、完全には行動力を失っておらず、かなりの人数が生きていたと推測できます。
イギリス側では、やはり『ヴィースバーデン』の近くで動けなくなった駆逐艦『シャーク』がありますが、小数ではあるものの乗組員は救助されています。
初期の戦闘で行動不能となり、撃沈されて生存者が全員捕虜となった駆逐艦『ネスター』と『ノーマッド』では、100人弱の乗り組みに対して、戦死者はいずれも一桁です。
大口径砲でめった撃ちにされ、海戦後に行動不能となり、浸水過多で放棄された装甲巡洋艦『ウォーリア』の場合でさえ、おそらく900人ほどの乗組員中、戦死者は1割に満たない71名です。負傷者も27名でしかありません。
夜戦で沈没した駆逐艦『チッペラリー』では、本話に出てくるような半没状態のイカダでの漂流があり、低体温症のために多くが死亡したと言われます。こちらでは翌朝、18人が救助されました。
これらのことから、戦闘が終わった時点の『ヴィースバーデン』には、かなりの数の生存者がいたと推測できます。戦闘後5時間も浮いていたのであれば、適切な援助が受けられれば沈まなかった可能性すらあるのです。本文中では、重傷者を含めて150人ほどが生きていたことにしていますが、かなり少なめの数字だとも考えています。
季節とすれば、『ケルン』の沈没は8月末であり、海水が暖かだったために生き延びたと言われ、『ヴィースバーデン』では、海水が冷たかったために一人しか生き残れなかったとされているのです。
あくまでも「比較的」であり、どちらも真冬ではないのですから、生きていること自体が異常なわけではなく、確率としてゼロでもないでしょう。しかし、軍艦の乗組員はそんなに都合よく、一人だけ生き残るものでしょうか。
さて、ドイツ海軍における、それぞれ唯一の生存者があったこの2件について、微妙な共通点を挙げてみましょう。
1、この二人の手記や公式記録がない。もしくは後の研究家によって重要視されていない。
2、どちらも海戦後24時間以上経ってから発見されている。
3、二人以上ではなく、唯一人である。
4、双方ともが機関部乗組員である。
5、いずれの場合も、沈没艦の最終状況について詳かでない。
もちろん、救助されたときには生きていたものの、短時間のうちに死亡した可能性はありますが、そうではなかったと仮定して話を進めます。
たとえ文字を書けない下級乗組員であったとしても、聞き取り調査はできるはずで、その記録は、存在するとすれば研究者にとって宝玉に等しいもののはずです。しかし、その具体的内容が引用されている研究書は見たことがありませんし、はっきりと文献の存在に触れているものもありません。ごく簡単な、又聞きのような記述があるだけです。
上記の疑問点は、たしかに偶然の範囲内にある問題であり、事実であることを否定できはしません。しかし、これらの生存者そのものが、当該艦の最終状況を作文するための捏造と考えると、疑問は氷解するのです。
聞き取りなどの記録が残っていないのは、それがそもそも存在しないからではないでしょうか。仮に捏造されたものがあったとしても、直後から専門家に疑問を持たれれば、誰もその内容を重視しようとは思わないでしょう。
丸一日以上発見が遅れているのは、一人しか生き残っていないことを正当化するためと、他の生存者がイギリス側に救助されていないことの確認のために必要な、時間幅ではないのかとも考えられます。実際に生存者が発表されたのは、もっと時間をおいてからの可能性もあります。
生存者が二人以上いたのでは、口裏合わせが困難になるでしょう。一人ならば、それも立場上知り得たことの少ない部署の人間とすれば、情報は出したいものだけに限定できます。
研究者とすれば、いくら疑問を感じたところで、決定的な証拠は容易につかめないでしょうし、事実であれば名誉に関わる問題ですから、安易に否定できはしません。それゆえ、そういう生存者があったという公式発表をなぞるだけで、この問題を追及していないのではないでしょうか。自己の書物に残すには、たしかに危険な話題であって、本題からは離れている問題でもあり、避けて通るのが自然だと思われます。
ドッガー・バンク海戦における『ザイドリッツ』での、誘爆寸前の弾薬庫周辺で行なわれたという決死的作業も、類似の逸話はあちこちに散見されるようであり、捏造ではないにせよ、尾鰭の付いた話とも思われます。このときに活躍したとされる兵士の名は文献で食い違い、人数までもが違っていることも珍しくありません。
たとえばイギリスでは、ジュットランド海戦での『ライオン』で、第三Q砲塔の被害時に弾薬庫誘爆を食い止めたのは、砲塔指揮官のハーベイ海兵隊少佐であると一致していて、叙勲の記録もありますが、これとても、誘爆が起きなかった実際の原因を含め、逸話がどこまで真実かは確認できないのです。
当時のイギリスのプロパガンダにおける手腕は定評のあるところで、それに比してドイツのそれは、あまり上手ではなかったとも言われています。
… * …
この物語を書こうと思ったとき、話の骨格にはいくつかの選択肢がありました。ひとつは、判明している事柄だけを並べ、足らない状況を推測という形で書き加える方法です。もうひとつは、非常に厳格な士官連中が、最後まで乗組員を支配化におき、判断ミスから結果として脱出が遅れ、ほとんどが助からなかったとするものです。反乱の要素を加えることも考えました。
しかしこれでは、前者はデータ不十分で消化不良かつ無味乾燥なものとなり、後者はあまりにも陰惨なお話になってしまいます。なにせ、ほとんど誰も助からないのですから。
そこで、今回はここに掲載したような、わりあい明るい、活発な展開にしてみました。ですから、艦上での士官と水兵のやりとりに、帝政ドイツ海軍では考えられないようなフランクな部分もあります。おそらくは、もっと厳格な会話でなければならないと思いましたが、意図的に今の我々に受け入れやすいだろう水準にしています。
それでも、最後はやはり、気の滅入るような話になってしまうのですが、読後感はどんなものだったでしょうか。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
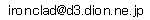
 戻る
戻る
 トップへ戻る
トップへ戻る
 戻る
戻る
 トップへ戻る
トップへ戻る
 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る