ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
第四章・漂流・その4
夜が明けはじめた。東の空が明るくなってきている。夜の間、星はまったく見えなかったから、方角は判らなかったのだが、ようやくどちらが北なのかが判る。この時期、太陽が昇るのは真東よりだいぶ南寄りだ。
艦が停止する前、最後に確認した位置はスカゲラック海峡の入口だった。風は西から吹いていたから、南からの海流と合わせ、やはり向かっている先はノルウェーのようだ。位置が判ったところで、漕ぐことすらできないイカダでは、何の意味もないのだが。
人数が減り、軽くなったイカダは浮き上がり、太股の半ばほどまでが海面上にある。イカダの安定としては危険な状態で、ちょっと動いても傾きかねない。皆は互いに励ましあい、眠ることもできない状態を耐えている。丸二日寝ておらず、半日休みなく戦っていたのだ、疲労は限度を越えている。
一人の男が、ボーッとなった頭で判断力を失ったのだろう。思わず、楽をしようとして目の前の樽に腰かけてしまった。
樽が沈み、片方の浮力を失ったイカダが傾く。慌てた男たちは、反射的に反対側へ移動しようとする。まだ、じっとしていれば腰かけた男が樽から落ちただけだったのだが、動いたことでイカダは反対側に傾いた。
「しゃがむんだ! 座れ !!」
間に合わなかった。樽に座った男は滑り落ち、浮かび上がった樽が反対側へ傾いたイカダを引っ張りあげる。海面が脚の高さで断面が小さいから、復元力はほとんど働かない。イカダはそのまま大きく傾き、つかまる物のない男たちは、叫び声とともに雪崩をうって海中へ転げ落ちた。
「うわあっ、危ない!」
「押すな! 落ちる!」
負荷の少なくなったイカダは、全体を揺さぶりながら斜めに滑るようにして海面へ浮きあがり、さらに残っていた男たちを振り落とした。木材の角やロープをつかみ、辛うじてイカダの上に残ったのは、10人といなかった。私は辛うじてロープにつかまり、落ちずに済んでいる。イカダの一部が壊れ、ひとかたまりの木材が切り離れてしまったが、幸い上には誰もいなかった。
イカダの近くに浮かんだ何人かは、すぐにイカダへ泳ぎつき、引っ張り上げられる。慌てた男たちは溺れ、保温のために着込んでいた衣服が邪魔になって泳げない。服から空気が抜けるに従って沈んでいく。
「助けてくれ!」
こんなにも自由に動けないということを、ほとんどの者が初めて経験している。ほんの10メートルと離れていないイカダへ向かって泳げないのだ。手が届いたものは助け上げられたが、風に流されるイカダは、水中の男たちからどんどん離れていく。
泳ぎを知らない者は、ただもがきながら騒ぐだけしかできない。助けを求める声と、絶望の絶叫、泣きわめく声が海に呑まれていく。落ちた者が多すぎ、残った者はほとんど何もできなかった。
なお数人がイカダにつかまっているのだが、服が水を吸い、重くなって持ち上げられない。なんとか片足でもイカダの上にあげられれば、よってたかって引き上げるのだが、腕だけでは引ききれないのだ。
身軽な副長は、一度は海に落ちたものの、自らイカダによじ登ると、イカダへ上がれない者の脇から海へ入り、下から持ち上げてくれる。
「シュタイン、お前は上から持ち上げるんだ。お前が落ちたら誰も持ち上げられん」
「手を握れ! 放すんじゃないぞ!」
3人、4人がイカダに押し上げられた。肩で息をしている副長が危ない。抜き上げるようにイカダの上へあげる。溺死の恐怖に体が動かないのか、ほんの1メートル先から呆然と見ているだけの顔がある。足元へフライターク掌砲長が泳ぎついた。
「しがみついていろ! 今、上げてやる」
「お願いします」
さすがに、体の大きなフライタークは持ち上げきれない。イカダも崩れてきていて、ふんばりが利かないのだ。
フライタークは緩んでいるロープを握ったが、次の瞬間、波に動いた角材に手を挟まれ、苦痛のうめきとともにロープを放してしまった。
「そこの樽につかまるんだ。放すんじゃないぞ!」
フライタークは、無事な方の手で、ロープに繋がれているだけになってしまった樽に手を伸ばしたが、ロープをつかみきれなかった。
「大尉、…足がつりました。もうダメです。すみません…」
フライターク掌砲長は、そのままイカダを離れてしまった。手を伸ばしたのだが、わずかに届かなかった。苦痛に歪んだ顔が、そのまま海に沈んでいく。
その後は、誰も手の届くところまで近寄れなかった。
イカダに残っているのは、わずかに17人にまで減っていた。もう、イカダの表面は海面上にあるから、全員が腰を下ろし、中央に寄り添っている。
「たった17人か。なんてことだ」
もう、落ちた者のほとんどは姿が見えない。いくつか服が浮いているだけだ。漕ぎ寄せる方法がないから、たまさか近くへきたものだけに手を伸ばす。これもまた、脱げた服だけだった。
「とにかく、17人は生き残っているんだ。俺はなんとしてでも生きて帰るぞ」
副長は、イカダの壊れた部分を直しはじめる。切れたりほどけたロープを結び直し、これ以上バラバラにならないように、がっちりと固定した。
「やれやれ、これでなんとかなるだろう」
時刻は午前7時40分。時計はまだ奇跡的に動いている。周囲はすっかり明るくなっているが、気になるのはカモメの姿が見えないことだ。あいつらは好奇心が旺盛で、何であれ、海面上にあるものを必ず見にくる。それがいないというのは、陸から大きく離れているということだ。
「シュタイン、メシにしよう。食いものはどこだ」
「イカダの縁、青い角材に繋いであります。水の中です」
「…どこだ?」
青い角材がない。どちら側にあったのか、記憶は定かではないけれども、たしかに目印にと考えて青い角材に繋いだのだ。食料の入った缶と真水の樽と。
「…!」
バラけた部分に繋がっていたんだ。イカダが傾いで滑るように浮かび上がったとき、重い水やら食料やらがぶら下がっていたために、イカダのあの部分が壊れたんだ。イカダの負担にならないようにと、海中に吊るしていたのが失敗だったか。
「ないのか !?」
イカダの周囲を探ってみるものの、樽や食料の缶は繋がっていない。最初に開けた飲み水の樽が、ほとんどからっぽになって浮き代わりに繋いであるだけでしかない。
「ありません。…イカダの、壊れた部分に繋がっていたんです」
「なんてこった。…全然ないのか」
「水が少し。この樽の中だけは真水のはずですが、いくらもないと思います」
大きな樽ではない。持ち上げて振ってみれば、数リットルほどの水が残っていると判った。樽にくくりつけてあったカップに移し、全員が一杯ずつをすする。いくらか塩気があるものの、贅沢を言える状況ではない。
水と食料を失ってしまったのでは、とうてい長い漂流には耐えられない。明るいうちに見つけてもらえなければ、夜を乗り越えられるかは疑問だ。
10時過ぎ、南西の方角に煙が見えた。小さな艦隊のようだ。イギリスともドイツとも判らない。煙は淡く、おそらく駆逐艦のものと思われる。我々のような漂流者を探しているのかもしれない。
しかし、こちらには連絡の手段が何もない。信号銃は用意してあったのだが、イカダが傾いたときに流されてしまった。マスト一本立てる余裕もなかったから、旗も上げられない。拾った服を広げ、振ってはみるものの、もっと近くへ来なければ見えるはずがない。
煙はいっこうに近寄ってこない。かなり離れた西側を通り過ぎてしまうようだ。数が減っているから散開したらしいと判るが、一番近い艦がやっと煙の見える距離なのだろう。
ザブンと水音がし、振り向くと一人が海へ入って泳ぎだしていた。泳ぐのに邪魔になる服と、靴が残されている。男は一言も言わず、振り返りもせずに泳いでいく。
「誰だ?」
「チルマンスだと思います。…そうです。あいつ、泳ぎには自信があると言ってたから…」
イカダから落ちたとき、最初に戻ってきた男だ。伸ばしてきた手を引いただけで、簡単にイカダへ上がってきたんだっけ。
「チルマンス、戻ってこーい。泳ぎきれやしないぞー」
わずかに手を振ったように見えたけれども、そのまま泳ぎ続けていく。確かに着実な泳ぎ方で、自信があると言うのも判るが、あの煙まではどう見ても10キロメートル以上ある。しかも向こうは、泳ぐのなど問題にならない速力で走っているはずだ。たどりつくはずもない。
「ばか野郎が…」
昼過ぎ、煙も見えなくなった頃、一人の水兵が痙攣を起こし、そのまま動かなくなった。いったい何が起きたのか、知る術もない。まだ生きてはいるものの、長くは持たないだろう。
西風が強くなり、波も高くなってきたが、荒れているというほどではない。艦にいれば、何とも感じない程度でしかないのだろうが、吹きさらしのイカダでは、わずかな風にも痛みを感じる。
昼の間、煙はいくつか見えたものの、近くへ来る気配はまったくなかった。おぼろな太陽はぐるりと空をひとまわりし、西を大きく過ぎてから海面に近付く。今、どのあたりにいるのか、何も判らない。水もとうとうなくなってしまった。
疲れきった男たちは、交替で眠る。いくらかでも気温の高い今のうちに寝ておかないと、夜になれば眠ることがそのまま死ぬことになってしまう。
日が暮れる頃、痙攣を起こした水兵、ルルと言う名だそうだ、が、冷たくなっていた。硬直した遺体を海に流したが、これほどまでに体力がなくなっていることに驚いた。人ひとりが持ち上げられないのだ。
日が落ちると、気温は急速に下がり、寒さが体を貫く。15人は体を寄せ合うが、強くなった風がイカダを乗り越える波をしぶきに変え、体を濡らしてしまう。食料も水もない男たちは、誰かが見つけてくれるのを待つばかりだ。
明るくなってきた。夜中に錯乱した水兵がひとり、渇きに耐えかねたのか海水を呑んで苦しみだし、海へ落ちて見えなくなった。残ったものも音を聞いていただけで、何もできなかった。次は自分の番だろう。
隣の男の体が冷たくなり、死んだのだろうとわかる。すでに自分自身、動くこともできず、口を開くのも苦痛だ。
「シュタイン…生きているか?」
「…はい。副長ですか?」
「そうだ。…もう、どうにもならんようだな。どうして、6月がこんなに寒いんだろう」
「さあ…」
「俺の隣も死んだようだ。冷たくなってきている。俺ももう、手足の感覚がない。何人生きているんだ?」
「…」、数えようとも思わない。
「心残りなのは、この記録だけだ。俺たちが死んでも、この記録は生き残る。さっき、袋はイカダに縛りつけた。たとえ全員が死んでも、誰かがイカダを見つけるだろうし、記録を拾ってくれるだろう。…ちくしょう、生きて帰れたらなあ、ミックにこの戦いのことを生涯語ってやるんだが」
「私には、話すべき子供もいないんですよ」
返事がない。もう、死んでしまったのかもしれない。それと確かめに行くこともできない。私の隣の男は、まだ体が暖かいから、生きているのだろう。
胸の上から、時計が時を刻みつづけている振動が伝わってくる。副長が言ったようになるのなら、この時計は袋の中へ入れたほうがいいのかもしれない。身に着けていれば、一緒に沈んでしまうだろう。もし、記録と一緒に回収されれば、時計はイレーネの元へ届けられるに違いない。
しかし、こうしてその針の動きを感じていると、これを体から離す気にもなれない。いずれ記録を入れた袋は、副長ががっちりと封をしたはずだから、簡単には開かないだろう。「重くなる」と、叱られるかもしれないな。
カモメどもが、格好の餌場を見つけたらしい。ギャアギャアとうるさい声が、頭の上を回っている。昨日よりは陸に近付いたということか。しかし、こいつらはイギリス人と同じだな、ドイツ人と見れば、襲って食い物にしようとする。
イカダの上に降り、様子を見ながら近付いてくるカモメは、死体をつつこうとしているのだろう。抵抗しないと判れば、遠慮なく群がってくるはずだ。そばに来た奴を、手を振って追い払う。それだけで体力がごっそりなくなるような気がする。しかし、生きたまま食われる気にもならない。
隣の男は、足をつつかれても反応しない。もう動けないのだろうか。カモメは分厚いズボンに閉口したらしく、剥き出しの顔を狙って近付いてくる。首を傾げ、慎重に様子を見ているようだ。彼らには、時間はいくらでもある。もし、まだ生きているなら、死ぬのを待てばよい。
そのとき、隣の男の腕が伸び、鈍重なカモメは簡単に首をつかまれた。ひと声悲鳴を上げただけで抵抗する間もなく、もう一方の腕が伸びると、ボキッと嫌な音がして、カモメは動かなくなる。男はカモメを投げ捨て、その白い体は波に漂いはじめた。
様子を見ていた他のカモメは、悲鳴にびっくりしてイカダから離れたようだ。そして、抵抗しない気楽な獲物、さっきまでの仲間だった、首を折られたカモメをついばみはじめる。
「名前は?」
「はあ…ツェンネです。…ボイラーです」
名前を聞いても顔が思いだせない。記憶も何も、すべてに遠く霞みがかかっている。ピチャピチャという波の音と、カモメのギャアギャアとうるさい朝食風景だけが、そこにあった。
一時の興奮は、必ず反動を伴う。またカモメが騒がしくなってくると、もう、その結果を考えるのが嫌になった。目を開けるのも面倒だ。
恐怖心が抜け、気持ちが穏やかになると、奇妙に暖かさが戻ってきて、体の芯を揺さぶるような快感がある。誰かが耳元で叫んでいる。副長かな。そんなに怒鳴らなくたって聞こえますってば。爆風で耳をやられたのは、もう…
…あれからどれだけ経ったんだろう。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
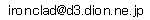
 戻る
戻る

 戻る
戻る

 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る