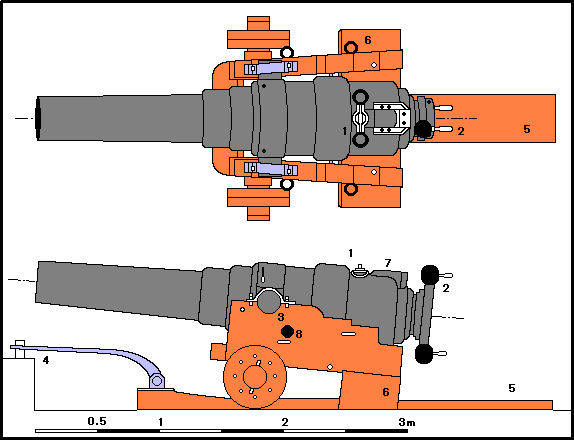
第一図
|
アームストロング後装砲 Armstrong's rifled breech loader |
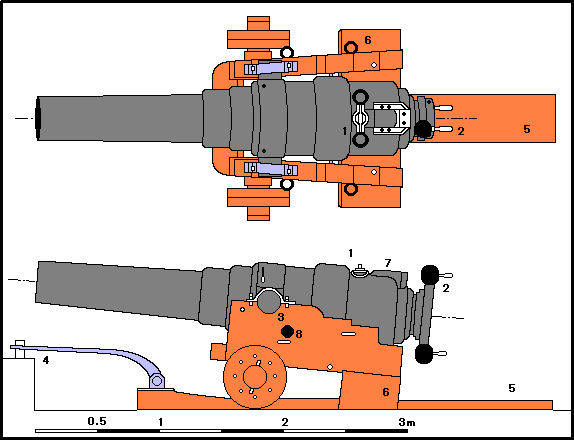
クリミア戦争時に英国兵器工廠でアームストロング (William G. Armstrong) が開発し、1855年に40ポンド砲が、1859年に110ポンド砲が制式採用され、陸海軍で用いられた初期の後装砲。初期のイギリス装甲艦も搭載していた。
幕末の日本でアームストロング砲というのはこれを指し、日清戦争当時のアームストロング社製速射砲は、これとはまったく別物である。砲は新型になったが、砲架は帆装戦列艦時代からいくらも進歩しておらず、基本的には大差ない。
冒頭の第一図は、これの7インチ(178ミリ)110ポンド砲の二面図である。砲身は前時代の単肉ではなく、大きな圧力のかかる部分に鉄環を嵌め込んだ層成砲身だった。図で最も太くなっているのが薬室部分にあたる。いくらか小さめに造った鉄環を熱して膨張させ、砲身に嵌め込んで冷やすことによって内側へ縮まろうとする応力を残し、内部の圧力に対抗しようとする原理である。
最も大きな特徴である尾栓は、垂直鎖栓式に分類できるだろう。鎖栓式尾栓は構造が単純で部品も少ない利点があるものの、発射ガスの緊塞が難しいという欠点があり、この砲では鎖栓を薬室に強く押しつけることで、この問題を解決しようとしている。
以下、#印は第一図中の番号に対応している。
#1は本砲の最も大きな特徴である垂直式鎖栓 (vent piece) の引き抜き用把手を示す。次の第二図で赤く塗られている部分であり、これが発射ガスを押さえ込む尾栓そのものである。
#2はこの尾栓を薬室に押し付けておくための、螺旋式のパイプ状中空尾栓 (breech screw) を回す取っ手で、螺旋式尾栓は第二図の黄色く着色された部分だ。
#3は俯仰軸 (trunnion)。この砲では直接砲身に取り付けられている。
#4はピボット・アーム (pivot arm) で、先端は砲門の中に設けられたピボットに連結され、砲の旋回角を管理するために位置を固定する役目を持っている。
#5は方位板 (directing bar)。#6の後部支架 (rear-chock) がこれをまたぐように置かれ、これによって発砲反動で後退する砲が左右にぶれないようにしている。
#7は尾栓の置台で、引き抜かれた鎖栓を寝かせ、この上に置いておくためのベッド (saddle) である。
#8は砲の後退を止めるための太索 (hawser = ホーザー) を通す穴であるが、通常、駐退は後部支架の床との摩擦か、この付近に取り付けられる摩擦駐退機 (compressor) によって行われるので、この索はあくまでも安全用の予備である。この点、昔の4輪式砲架とは少々様相が変わっている。
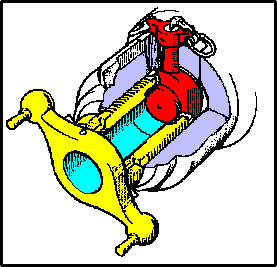
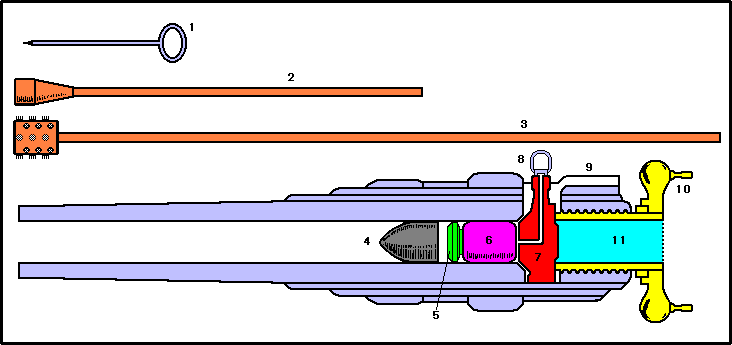
図二と三を使って、この砲の運用を説明しよう。以下*印は第三図の番号に対応している。
発砲を終えた砲は、まず滑車装置で前進させられ、最前部位置まで進められる。ついで螺旋尾栓*10が緩められるのだが、発射の圧力によって固着している場合、取っ手の付け根にある鉄球をハンマーで叩いて緩める。
砲の両側に立った砲員が、把手*8を持って鎖栓*7を持ち上げ、架台*9の上に寝かせる。砲身内に掃除棒*3を挿入し、装薬袋の燃え残り等を押し出す。
続いて砲弾*4、さらにガス緊塞器*5を取り付けた装薬*6が、それぞれラマー*2によって螺旋尾栓の空洞*11 (両図で水色に着色された部分) を通して砲へ押し込まれる。装薬の後ろにはガス圧を逃がさないための錫椀 (tin cup) が置かれる。
この間に火管が鎖栓に装着され、準備が終わったところで鎖栓が砲尾へ落としこまれると、螺旋尾栓が回され、鎖栓は薬室に強く押し付けられる。鎖栓の把手の間に開口している点火口に差し込まれた火管に点火されれば、炎は鎖栓の中をL字形に曲がって火門に達し、装薬に点火する。
*1は、この火門の先で、火管からの炎を確実に装薬に着火するため装薬の袋に破れ目を作るための用具 (primer) である。火門までの火炎通路が曲がっているので、おそらくフレキシブルに作られていると思われる。
以下の図は、「海図室」にリンクのある、「ハードな冒険」を開いておられる宮前さんからいただいたジフ・アニメである。アームストロング砲の装填要領がよく解るので、掲載させていただいた。(感謝!)
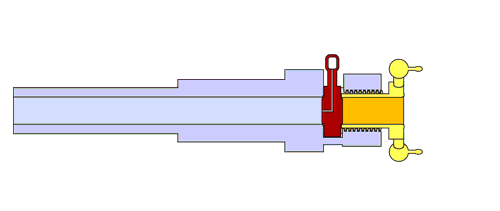
照準は砲そのものを移動させて行われる。旋回はテコ棒 (hand spikes) または左右の滑車装置で行われ、仰角は砲尾の下に差し込まれる楔 (quoin) によって調整された。原始的などと言ってはいけない。この砲でもちゃんと改良され、垂直に立てられたネジ棒とラチェット付きのナットによる俯仰機が取り付けられるようになり、レバーをガチャガチャやれば砲が頭を上げたり下げたりするようになったのだから。
この砲の砲身長は14.2口径で、特に徹甲性能を意識していなかったため、同時期の前装滑腔砲に比べて初速が低く、貫徹力は大きくない(後掲の表参照)。ただしライフルが効いているので弾道精度は高く、砲弾の空気抵抗が減ったことから有効射程は従来砲の2〜3倍に伸びて最大4,000メートルほどとなった。ライフル溝は76本、旋転率は1回転37口径で一定である。
砲弾は、それまでの球形弾からいわゆる弾丸型(椎実弾)になり、ライフル溝に食い込ませるため鉛でコーティングされている。信管については明確な資料がない。
鉄の塊である実質弾 (shot) の重量は、およそ110ポンド (50キログラム) で、炸薬を充填した榴弾 (shell)、円筒形のケースに入った榴散弾 (segment shell)、散弾 (case shot) も用いられている。
表・上3種は『ウォーリア』が装備したもの・7.5インチ砲は参考
| 名 称 | 形 式 | 口 径 | 口径長 | 砲身重量 | 砲弾重量 | 初 速 | 備 考 |
| 110ポンド砲 | 後装施条 | 178mm | 14.2 | 4.1t | 約50kg | 358m/s | アームストロング砲 |
| 68ポンド砲 | 前装滑腔 | 206mm | 14 | 6.0t | 約30kg | 482m/s | 球形弾 |
| 7 インチ砲 | 前装施条 | 178mm | 15.9 | 6.5t | 約51kg | 465m/s | 1866年に装備 |
| 7.5インチ砲 | 後装施条 | 190mm | 50 | 16t | 約91kg | 844m/s | 1904年頃 |
1859年、標的艦となっていた装甲浮き砲台『トラスティ』 Trusty に対する実弾射撃試験が行われ、40〜100ポンド砲(120〜152ミリ砲)のテストでは、いずれの砲も距離にかかわらず厚さ102ミリの錬鉄板を貫通できなかった。しかし、射程と弾道精度の利点から採用が決定されている。
新兵器として巡洋艦以上の艦にそれぞれ2門ずつ程度装備され、1861年に完成した装甲艦『ウォーリア』 Warrior では、40門の68ポンド前装滑腔砲中10門をこれと置き換えた。以後の艦でも順次採用されていたものの、生産が間に合わないためか、大型艦でこの砲だけを装備した艦はなかったようだ。
ところが、1863年の薩英戦争中、イギリス艦隊の使用した21門のアームストロング後装砲は、戦闘中に度重なる故障を起こし、旗艦『ユーリアラス』 Euryalus では、前部110ポンド砲の尾栓が吹き飛んで砲員のすべてが死傷するという事故が発生した。
この戦闘についてのキューパー提督の報告では、多くの砲の鎖栓が、十数発以上を発射したところで裂開したとされている。完全に破壊された鎖栓の検査によれば、残余部は砲腔内の定位置に確実に定着されており、操作上の過失ではなく、構造もしくは材質の欠陥だろうと推測されたようだ。この事件によって、それまでの高い評価は一変し、尾栓の強度に欠陥があるとみなされるようになった。
イギリス国内には、アームストロングの成功を妬む勢力があり、彼等はここぞとばかりに欠陥をあげつらい、ついにこれは廃棄されることになってしまう。
仮に事故がなかったとしても、いずれこの砲の構造様式が廃れるのは間違いないところだったが、なにより問題なのは鎖栓を人力で引き上げなければならないことだっただろう。本砲でもこれの重量は136ポンド (61.7キログラム) もあり、二人がかりでも持ち上げるのがやっとと思われる。より大口径となれば、天井から滑車装置でも使って吊り上げるしかない。これではとうてい実用になるまい。
事情はともかく、導入直後の主戦兵器の欠陥、廃棄が軍に与えた衝撃は小さくなく、彼等が対策に苦慮したのは当然だろう。当時の新聞などでは、尾栓事故については特に触れられていないようだ。イギリス艦隊の被害の一部はこの事故によるのだが、これが伏せられれば薩摩軍の戦果ということになってしまう。一部文献には、これを鵜呑みにしたような記述も見られるところだ。
この頃、日本の各軍が入手した兵器の中に、このアームストロング砲があったのは事実で、高い金を払って欠陥兵器を掴まされたことになる。しかし、その能力に対する評価は低くなく、比較的口径の小さな野砲では欠陥が露呈しなかったのだろう。また、砲の破裂は当時珍しい事故ではないから、発生したとしても問題にされなかったのかもしれない。事故の情報、イギリス軍における廃棄の実情は遠からず知れ渡ったはずだが、古い資料には、これについての記述は見られない。
翌年発生した長州と諸外国との紛争では、イギリス海軍のかなりが薩英戦争時と同じ船なのだが、本国から武装を取り寄せて交換する時間があったとは思えず、せいぜい在庫の旧式砲と取り替えるくらいだっただろう。艦隊内では砲の欠陥は周知のはずだから、下関砲撃にあたってどのような対策が講じられていたのか、興味は尽きない。
司馬遼太郎の「アームストロング砲」(講談社文庫・し-23・1988年) は、佐賀藩の手に入ったアームストロング砲を題材にして書かれたものであるが、執筆時点ではその構造が誤解されていたらしく、表現されている尾栓のイメージは速射砲のそれのようだ。
イギリス本国では、翌1864年には『ウォーリア』が予備役に入り、改装によって備砲は前装施条砲に換えられ、他の艦も順次砲を換装した。この間の発砲制限では、強装薬での発射が禁止されたという記述が見られる。
1866年頃から後の建造になる艦は、最初から前装施条砲を装備しているけれども、この時期には完成していながら就役がかなり遅れた艦があり、この砲の問題が影響したとも考えられる。イギリス海軍ではこの後、20年にわたって大口径の後装砲は採用されず、1886年の『コンカーラー』 Conqueror が、ようやく12インチ(305ミリ)後装砲を装備した。
アームストロングは工廠を辞して自ら工場を興し、世界一流の武器製造人となった。しばらくは前装施条砲を製造しており、海外へも多く輸出している。イタリアの砲塔艦『デュイリオ』 Duilio (1880年完成)が装備した世界最大の17.7インチ(450ミリ)前装施条砲も彼の手になる。
さらに、1880年代には大口径の後装砲を製造しはじめ、コルダイトなどの新装薬の開発によって新型砲へ移行する前に、最大17インチ(432ミリ)砲まで製造した。
その後も速射砲の開発などでは著名であり、会社は様々な兵器開発に携わっていった。
●参考文献
・The Immortal Warrior / Captain John Wells RN / Kenneth Mason
・Warrior "The First and The Last" / John Winton / Maritime Books
・The Armament of H.M.S.Warrior / E. F. Slaymaker / Warship / Conway
・海軍創設史 / 篠原宏 / リブロポート
 ワードルームへ戻る
ワードルームへ戻る
|