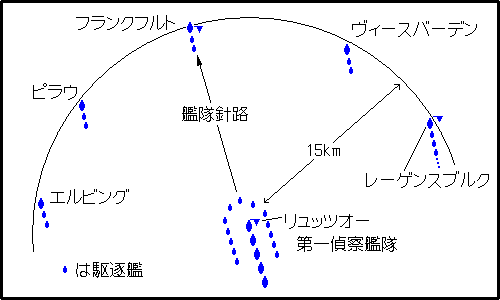
ヒッパー艦隊の隊列
|
ヴィースバーデンの時計 SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31 |
●第一章・凱歌・その2
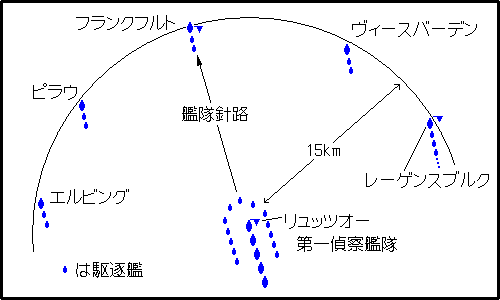
ヒッパー隊の周囲を取り囲んでいる駆逐艦は、当時の標準的な対潜水艦警戒隊形を示している。駆逐艦は全部で30隻が付属していた。
すでに時刻は15時半に近い。5月最後の日で、昼が最も長い季節の今、この緯度での日没は21時過ぎだが、このまま夜を迎えるのか、引き返すのか、シェーア司令長官がどう考えているのかは判らない。北を向いたまま夜になれば、巨大な艦隊の向きを変えるのは危険になるから、当然スカゲラック海峡を通過しての帰国になるだろう。ホーン・リーフズ方面へ戻るのならば、遠からず艦隊全体の向きを変えなければならないが、100隻ほどもいるから、準備作業だけだって大ごとだ。
今度は無線室からの声が叫んだ。
「『エルビング』から緊急通信! 『西方に複数の煤煙が見える』です」
艦橋が急に騒がしくなった。
「静かに! 慌てるようなことじゃない。艦長を呼べ」
まだ、何も判らないに等しい。複数の煙は、それがイギリスの艦隊であることを示している可能性が高いものの、単なるパトロール隊かもしれず、それならば獲物にすぎない。必要と認めれば、ヒッパー提督が飛びかかってなぎ倒すだろう。ここにいる艦隊は、半端なパトロール隊など問題にしない実力を持っているのだ。
背の高いライス艦長が、帽子を気にしながら艦橋へ入ってくるのと、無線室からの叫び声とが同時だった。
「緊急信! 駆逐艦『B109』より、『矩形164に複数の敵艦あり』」
『B109』は、『エルビング』に付属している駆逐艦だ。航海長はすぐに海図で位置を確かめる。ここからだと方角は西南西にあたる。
「戦闘配置!」
艦長の声にすかさず当直士官の手が伸び、警報が鳴り響く。艦内は一斉に騒がしくなり、兵が持ち場へ向かって走り出す音で溢れた。あちこちから機械を動かす音が続く。
持ち場である後部の射撃指揮所へ行こうとすると、艦長が呼び止めた。
「シュタイン君、ちょうどいい、まだここに居たまえ。様子が判ってからでも遅くないし、知っていたほうがいい。副長はどこだ。直接持ち場へ行ったのなら、ここへ来るように呼べ。主だった士官で、いないのは誰だ。艦橋へ呼べ。機関長もだ」
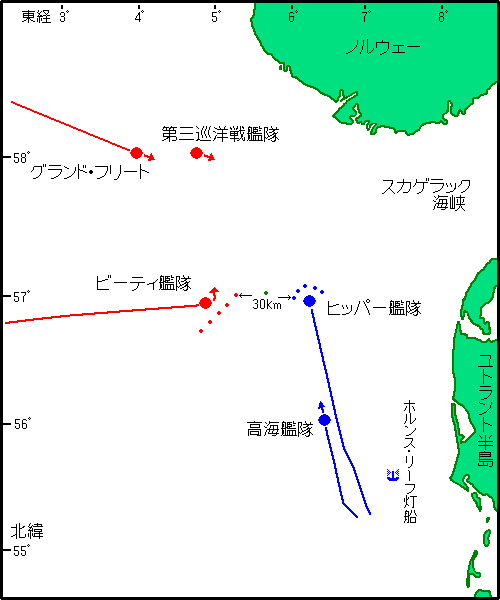
30kmと書かれているのは、独英双方の偵察線翼端艦同士の間隔。
この中間地点にノルウェーの貨物船がおり、これを視認した双方が接近したため、互いを発見することになった。
その直前、ビーティ艦隊は予定時刻になったので針路を北へ転じており、間に船がいなければ、互いに気付かないままだった可能性もある。
|
ほぼ平行した針路にあって、互いの偵察線の両端にあった艦同士が、偶然その中間地点にあった中立国商船を発見し、臨検のために近寄って相互に発見しあい、それぞれを敵と認めて砲戦を開始しました。 |
すぐに伝言が伝えられ、カイルハック副長とテーネ機関長が、ほどなく艦橋へ現れた。
「皆に話しておくことがある。おおよそ知っているだろうが、ヒッパー提督は今度の作戦に命を懸けておられる。もし、今、出会っているのがビーティの艦隊であるなら、彼を北海に沈めるまで、何も容赦しないはずだ。提督は逃げない。もちろん、作戦として敵をおびき寄せるために逃げるふりはするだろうが、決して敵を避けはしない。このことは、先日の艦長会議で提督自身の口から話されたことだ。もちろん、我々も逃げはしない」
艦長の厳しい青い目が、艦橋に居並ぶ士官の顔をひとつずつ見詰めて通り過ぎる。提督の並々ならぬ決意は、確かに皆の心に伝わった。
無線室からの伝令が艦橋へ入ってきたものの、雰囲気に気圧されて言葉を止めている。副長と目が合い、小さなうなずきを得てメモを読み上げた。
「『エルビング』からヒッパー提督への報告を傍受しました。『西微北に敵の装甲巡洋艦見ゆ』です」
時計は15時30分を過ぎたところだ。ジーグムント砲術長が口を開く。
「装甲巡洋艦だと? 正体は何かな。晩飯はイギリス人捕虜の衿章を眺めながらといきたいもんだ。艦長、そのときは艦長を士官室での食事にご招待させてください」
「ふむ、楽しみにしておこう。では、行け!」
後部指揮所というのは、艦橋の前にある装甲された主指揮所と違い、吹きさらしの場所に関連装備が備えられているだけだ。後檣の根元に、船首楼甲板より一段高くプラットホームが設けられ、測距儀と艦内通信装置が置かれている。
隔壁はなく、風避けのキャンバスで囲まれているが、防御などは何もない。今は弾片避けに、巻き締めたハンモック、いわゆるマントレットが並べて手すりに固縛されている。マストの周囲には艦橋などからの伝声管が取り付けられ、それぞれがすでにテストされていた。異常はない。
『エルビング』からの通信があるやいなや、ヒッパー提督は艦隊全体を西南西に向け、そのために『ヴィースバーデン』は、間隔の開いた隊列の最後方にいる形になっている。少なくとも、右半分の哨戒線は維持されたままだ。発見された敵がどれほどのものか、はっきりするまでは見張りを続けなければならないのである。
「寒いな」
「はい、もう5月も終わりなのですが」
話しかけた相手のリヒャルツは、まだ中尉になったばかりで、やっと制服が似合うようになった若者だ。私とは同郷であり、弟のような気分で接している。ほっそりした男で、ほっぺたの赤いことを田舎者のようだと、恥ずかしがっていた。
彼も背は高いほうだが、私は艦内でも一二を争うくらいに大きく、それなりに横幅もあるので、頼りになるイメージがあるらしい。大きすぎて困ることもしばしばで、天井の梁へ頭をぶつけるのなどは日常茶飯事だ。
砲術長は、「お前がここへ来ると狭くなってかなわん」と言い、司令塔へは歓迎してくれない。頭のつかえそうなあの場所は、スリットの高さが合わないこともあって好きな場所ではないから、あまり気にもならないが。
しかしここは寒い。もう少し煙突が近ければ、それなり熱も伝わってくるのだろうが、機関室を隔てた向こう側では煙が押し寄せるだけだ。なんの利益もない。暖房装置はあるものの、かすかに暖かいかなというだけで、艦が速力を上げれば、そんなものはどこかへ消し飛んでしまう。
煙突から吐きだされている煙は相当な量で、全速準備が下令されているのだろう。たまに火の粉が降ってくるから、気をつけていないと服に焼け焦げができる。今はほぼ向かい風になっているので、煙は頭の上を凄いスピードで飛び去っていく。そこには一段高く探照灯台が設けられており、ちょうど指揮所に小さな屋根を懸けたようになっている。雨を含め、何ひとつ遮ってはくれないが。
「敵は何ですか?」
「無線では装甲巡洋艦と言っていたが、どうかな」
ここにいたのでは、細かな情報には触れることができない。前方の『ピラウ』が旗艦に近付いているように見えるから、第二偵察艦隊には集合命令が出たのかもしれない。それならば、敵はそれなりの勢力ということになる。
速力はもう20ノットを越えたようだ。左方には巡洋戦艦の噴き上げる煙の塊が見える。あちらもかなり増速しているらしい。
「艦橋からです、大尉。『エルビング』が砲撃を受けたそうです。敵は軽巡洋艦」
「わかった。…大物はいないのかな」
軽巡洋艦ならば、ただのパトロール隊の可能性もある。うまく捕まえればヒッパー提督の敵ではないが、後ろからの追跡では追いつけないかもしれない。
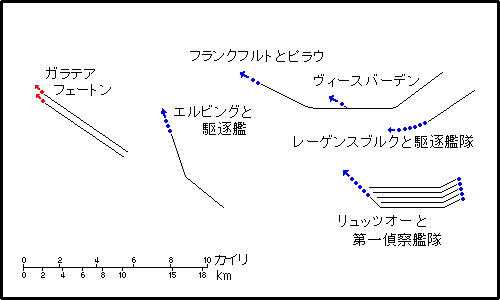
この頃、ヒッパーの西南西にあったビーティは、針路を東北東に変え、ヒッパーへ急速に接近している。
『エルビング』に追われて逃げている英軽巡洋艦は、第1、第3軽巡洋艦隊8隻で、視界内にある独軽巡洋艦は3隻でしかなく、どうみても逃げなければならない戦力ではない。
|
『エルビング』を認めたイギリス軽巡洋艦は、当初の計画に沿ってこれを主力の勢力範囲へ誘致するため、北西に針路を取って逃走を始めます。この間、『エルビング』から『ガラテア』へ1発の命中弾がありましたが、艦橋下へ命中した砲弾は不発で、被害は僅少でした。 |
ずいぶん速力が上がっている。振動は激しくなっているし、こんなところまで波しぶきが飛んでくるのでは、もう25ノットを越えただろう。煙突もゴーゴーと大きな音を立てている。普段は開け放しの機関室天窓もきっちりと閉ざされ、下は熱の逃げ場がなくなって灼熱地獄になっているに違いない。ほんの5度ばかりでいいから、分けてもらいたいもんだ。
しばらくすると、艦隊は右へ回り、さらにまた右へ回って、ほとんど真西を向いた。静かになったと思ったら速力が落ちている。逃げられたのか?
「艦橋からです、大尉」
「はい、シュタインです」
「艦長だ。敵は軽巡洋艦で逃げ腰だ。こっちは遠いからな、追いつくには時間がかかる。砲員を休ませておけ」
「了解しました」
低い位置でしぶきのかかる砲側に砲員を待機させておけば、彼等はじきに濡れネズミになってしまう。もう夏が近いのに北海の水は冷たい。放っておけば必要なときに凍えてしまって役に立たなくなる。
「砲側へ、砲員は遮蔽物に入れ。暖かなスープは付かないがな」
伝令が各砲側へ命令を伝える。砲員が甲板から消え、それぞれに手ごろな場所で暖を取りはじめた。速力が落ちたのは短時間だけで、艦は再び増速している。針路がまた変わり、西から北西へ向いた。まっすぐ先はスカパ・フローというわけだ。間違いなく追跡に入っている。
前方では、旗艦『フランクフルト』の後ろに『ピラウ』がぴったりと続き、だいぶ間をおいて『ヴィースバーデン』がついていく形だ。後ろには『レーゲンスブルク』がおり、その周囲に駆逐艦が集まりつつある。
針路が変わったために巡洋戦艦隊は後方に位置する形となり、それだけ軽巡洋艦が突出した状態になっている。西のほうからいくつかの煙が接近しているが、旗艦が警戒していないところを見ると、あの煙は『エルビング』と連れの駆逐艦なのだろう。靄に包まれたその影から、小さな閃光が走った。
「発砲しています!」
「そのようだな」
まだ、敵はまったく見えない。どこに何がいて、どういう対勢で何を意図して動いているのか、少なくとも艦橋にいなければ何も判らないに等しい。それらが見て取れるほど近くなれば、今度は忙しくて何も考えられなくなる。いずれ砲側では、指し示された目標へ砲弾を叩き込むことだけが問題なのであって、どこで誰が何をしているのかなど、興味を持ってもしかたがない。
時刻はすでに16時を回っている。西方の『エルビング』は左舷側を砲撃しており、靄の中に艦首砲発砲の閃光だけが見える。その針路は旗艦と交差方位を取っているらしく、双方は急速に接近していく。
「艦橋からです、大尉」
「シュタインです」
「『フランクフルト』から、敵の飛行機が活動していると通報がありました。上空監視を強化してください」
ベーレンス中尉だった。飛行機だと?
「了解。敵艦の情報は?」
「大型艦らしい煤煙が見えているそうです。おそらくは巡洋戦艦かと」
「出たか。いよいよだな」
誰が、どちらの方角に「大物」を見ているのか、細かい情報は何もない。前方の3隻は集合し、右へ針路を振ったようだ。第一偵察艦隊はほぼ真後ろにいて、針路を変えていない。駆逐艦を連れた『レーゲンスブルク』は、そのすぐ右舷側にいる。西側に「大物」が出たのだろうか。
「敵の飛行機が出ているそうだ。見張りに上空監視を」
「了解しました、大尉」
ツェッペリン飛行船のように大きければともかく、小さな飛行機など、いくらかでも離れてしまえば見つけるのは困難だ。軍艦より格段に速いから、見つけても目を離すと見失ってしまう。おそらくは水上機だろうから、偵察が目的で攻撃してくるようなことはないだろう。だいたい、高角砲を持っている艦隊を攻撃しようとしたのでは自殺行為だ。
だが、飛行機には、いったいどういう意味があるのだろうか。確かに上から艦隊の構成を見られれば有利には違いないし、天候がよければかなり遠くまで見通せるそうだから、偵察にはうってつけだ。
しかし、腰が座らないせいか爆弾を落としても当たらないし、数を積めないから、そのつど基地へ戻らなければならない。魚雷を積むものもあるけれども、やたらに足の速い水雷艇でしかなく、撃ち落とすのはそれほど難しくないそうだ。
「後方の第一偵察艦隊が回っています」
煙の下にマストが見えている。その間隔が広がり、またすぼまる。それが艦の数だけ繰り返され、艦隊が方向を変えたのがはっきりした。
「回頭警告です」
艦の速力が落ちた。警報が鳴ると、右に大きく舵が切られて艦は傾き、ほとんど180度向きを変える。西側に敵がいるのなら、これはまったく「逃げる」行動だ。戦うと言っていたのだから、そんなはずはない。それとも逃げるふりをして敵をおびき寄せ、シェーア提督の艦隊とで挟み討ちにしようというのだろうか。…きっとそれに違いない。
ドッガー・バンク海戦のとき、ビーティは自ら先頭を突っ走り、全速力で後先考えずに追いかけてきたという。それならば、罠を仕掛ければそのままその口の中へ飛び込むだろう。なるほど、それならうなずける。
回頭が終わり、艦が立ち直ると速力が上がりはじめた。いよいよだな。
「右舷70度に煙が見えます!」
「艦橋に報告しろ。測距儀!」
「追っています。まだ煙しか見えません」
「艦橋からです、敵は巡洋戦艦」
正真正銘のビーティ大先生だな。さて、厳しいことになるぞ。入れ替わって後方になった『フランクフルト』たちも回っているようだが、離れていて行動ははっきりしない。
|
このとき、ビーティ艦隊には、通常の編成である『インヴィンシブル』級巡洋戦艦からなる第三巡洋戦艦隊ではなく、新型の『クィーン・エリザベス』級高速戦艦で編成される第五戦艦戦隊が付属していました。ドイツ側はこのことを知りません。 |
 戻る
戻る
|
次へ

|
 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る
|