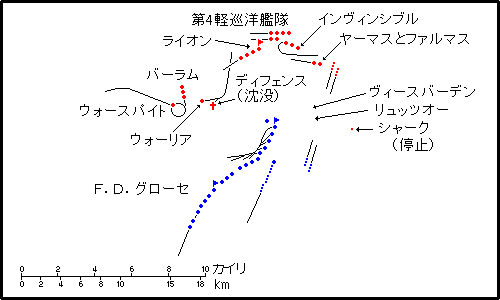
5月31日1920時の相互位置
|
ヴィースバーデンの時計 SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31 |
第二章・決戦・その2
振動が急速に静まった。それを確かめて、皆は掴まっていたものから手を離し、周囲を見まわす。また敵の砲弾が水柱を上げたが、艦首方向に大きく逸れ、命中したものはない。
今は砲撃も行われておらず、艦は元通り静かになっている。本当に元通りか?…静か過ぎないか?…耳が聞こえないからか。
「シュタイン、体はだいじょうぶか?」、副長が耳元で怒鳴る。
「ケガはしていないようです。どうなったんですか?」
「わからんが、機関が止まっている。下へ見に行かなきゃならん。後を頼む」、そう言ったんだと思う。ほとんど聞こえはしなかった。
副長は振り返りもせずにラッタルを降りていった。機関が止まっている?
まさにそうだ。さっきまで一定の振動でうなりをあげ、その働いていることを示していた機関が、今はまったく動いている様子がない。しかし、なにか別な振動が顔に感じられる。
見回すと、艦の右舷側が真っ白な霧に包まれ、何も見えない。何だ?
「蒸気です、大尉。艦の蒸気が全部出ていっているんです。聞こえますか?」、やはり耳に口を付けるように怒鳴られた。その水兵も耳を押さえている。
「あ、ああ、だいじょうぶだ。どうした、お前も耳をやられたのか?」
きょとんとした顔に理解が見え、頭の上が指差された。見上げると、煙突の蒸気捨管から、猛烈な勢いで蒸気が吹き出していた。機関が突然止まったために、全力運転していたボイラーの蒸気が、すべて捨てられているのだ。そうしなければボイラーが破裂してしまう。
そうか、あれだけ蒸気を捨てていれば、その音は物凄いもののはずだ。私は耳をやられたから、それが音として聞こえていないだけなのか。顔に感じる振動は、その音があまりに大きいので、空気の揺れとして感じられるわけだ。
やがて蒸気の噴出は少なくなり、それに連れて聴力が戻ってきた。艦は完全に停止し、波間に漂っている。こんなところで止まっていれば、好きなだけ的にされてしまうが、どのくらいで動けるようになるのだろうか。
虎の子の測距儀が壊れてしまった。あの強烈な振動で揺さぶられたのだから、精密な光学機械が無事で済むわけがない。何がどう壊れたのかは判らないものの、映像はまったく見えない。使えないことは明らかだ。兵に命じて、保管してあるポータブルの小型装置を取りに行かせる。
「敵はどうしている?」
「装甲巡洋艦も、巡洋戦艦も、北へ向かっていました。駆逐隊が突っ込んでいったんです、大尉」
なるほど、あちこちに小さな煙があり、そこここに水柱が見える。少し離れたところで、駆逐艦隊は両軍が入り乱れて激戦の最中というところか。今はたまたま砲弾が飛んできていないが、ここは人通りで溢れる駅前広場の真ん中というべき場所なのだな。いや、地獄の一丁目というほうが、当たっているかもしれない。
乱戦の中から、見慣れた姿が現れ、近付いてきた。『フランクフルト』だ。『ピラウ』も、『エルビング』もいる。もうもうと煙を吐きだして煙幕を作っており、敵からの視界を遮っている。『ピラウ』の艦橋には砲弾が命中したらしく、奇妙に傾き、火災らしい煙を出しているが、速力は落ちていないようだ。
手の空いている、とは言っても今はほとんどすることもないのだが、乗組員たちは同僚に手を振り、拳を突き上げてファイトを現す。向こうでも同じように手が振られた。
艦隊はしかし、動けなくなった『ヴィースバーデン』の目の前を通り過ぎながら、信号を交わすだけで、止まることなく駆け抜けていった。なんと言っていたのか、私には速すぎて読み取れなかった。
「左舷後方に駆逐艦。敵味方不明」
小さな点のような影が見える。まっすぐこちらへ向かっている小型艦は、艦型が判別できず、敵味方の識別が難しい。西方向にいた味方の駆逐艦かもしれない。艦橋に報告すれば、向こうで誰何するはずだ。
「左舷、装甲巡洋艦が接近してきます」
北からさっきの敵艦が引き返してきた。2隻の装甲巡洋艦である。向きを変えた『フランクフルト』たちを追いかけてきたのだろう。足さえ動けば捕まる相手ではないけれども、まったく動けないのだからどうしようもない。その姿は徐々に大きくなってきた。情けない、こんなのに食われるのか。
ただやられるのを待つことはない。一矢報いてやろうじゃないか。指揮所に戻り、主指揮所からの指示を見れば、これは動いている様子がない。電話も通じない。伝声管を開き、主指揮所を呼ぶ。
「シュタインです。伝達装置故障」
「ジーグムントだ。故障じゃない。電力がなくなったんだ。以後は口頭で伝える。目標は290度の装甲巡洋艦。測距儀は無事か?」
「いいえ、さっきの振動で壊れてしまいました」
「現在の距離は120。誰かこれに付けるから、伝達路を作れ」
「了解」
近くにいた兵を伝声管に付かせ、伝えられた射程を復唱させる。乗員を、知らされた射程が砲へ伝わるよう配置する。こちらは中心線と左舷側の砲3門が使え、艦首側でも2門ないし3門は使えるはずだ。
推進力がないために、風に吹かれて徐々に向きが変わっている。側面積の大きな艦首が風下を向くまで、動きつづけるだろう。砲撃に支障が出るほどの速い動きではないし、そう極端に向きも違わないようだ。今、艦がどっちを向いているのか、コンパスはでんぐりかえっていて読めず、太陽が見えないので判らない。あまり意味はないな。何時だ。…19時を過ぎたばかりか。時計は何事もなかったかのように、時を刻んでいる。
「右舷5番砲です。旋回装置故障…」
非戦闘側だ。とりあえず影響はない。
「後にしろ! 状況をまとめておくように言え。…砲員を左舷砲の応援に送れ。即応弾薬を左舷側へ移すんだ!」
電力がなくなり、揚弾機も止まっているので、砲弾は人力で運び上げるしかない。こうなると10.5センチ砲弾なら抱えて運べるから楽なのだが、重い15センチ砲弾は45キログラムもあり、持って歩くのがやっとだ。とてもラッタルは上がれない。揚弾機のホイストを人力で動かすしかなく、砲弾をできるだけ上甲板に上げておくように命じる。砲側の準備弾薬だけでは、すぐになくなってしまう。28センチ砲だったら、それこそどうしようもないだろう。
待っていても意味はないと考えたのか、砲術長はかなり遠距離から射撃を始めさせた。初弾は近すぎたけれども、2斉射目で夾叉する。なまじこういうハンデがあると成績がよくなるというのも皮肉だな。
「命中しました! 敵艦首」
「いいぞ、続けろ」
ジーグムント砲術長の腕は確かだ。敵の艦首砲塔に命中したと思われる。しかし、相手は15センチ砲では致命傷を与えられない装甲巡洋艦だし、向こうの射撃指揮装置は死んでいない。たちまち夾叉される。
「負けるな! 撃つのを止めたら、ただの的だぞ !!」
みるみる砲弾がなくなっていく。速射砲の発射速度というのは、砂漠に水を撒いているようなものだ。また一発、命中させたものの、敵はまったくひるむ様子がない。舷側にずらりと並んだ砲塔が一斉に火を噴く。なんで、あんなにたくさんの砲を持っているんだろう。
パアッと右手の方向が明るくなり、轟音と衝撃が襲う。どこかへ命中したのか。ガラガラと破片の降る音がするものの、近くへは落ちてこない。
「艦橋に被弾!」
「火災発生!」
「声がしません。射程が伝わってきません!」
主指揮所が叩かれたか。指揮所の端から艦首方向を見れば、煙に包まれて何が起きているのか判らない。射程の伝達はなく、こちらにも測距儀が届いていないから、射撃は砲側での目見当になってしまった。
「各砲、10秒おきに100下げで連射。リヒャルツ君、観測を報告せよ。伝令、艦橋の様子を見てこい!」
兵が走りだした途端に、また前部に命中弾があった。衝撃波と火の玉。煙。ラッタルから転げ落ちた水兵が立ちあがり、足を引きずるように艦首方向へ走っていく。
艦が動いていないから、煙は風に乗って艦首のほうへ流れていく。また命中弾。砲弾の炸裂する音と、艦が壊れていく音。まるで現実感がない。艦の前半分は煙に包まれており、どうなっているのかはまったく見えない。見上げれば、もうもうたる煙の中で、前マストが傾いていた。だいぶ手ひどくやられたな。
「伝達します! 艦長戦死。艦長が戦死なさいました」
なんと、今のでやられたのか。艦橋か司令塔にいたはずだが、主指揮所も一緒にやられたのだろうか。伝達がないのは、途中で伝声管が切れただけかもしれない。
「大尉、副長からです。伝声管へ」
「シュタインです」
「聞いたか? 艦長が戦死されたそうだ。まだ確認できんが、はっきりするまで私が指揮を取る。状況は?」
「測距儀が壊れていますが、今、小型のを取りに行かせています。後部砲に損傷なし。主指揮所からの指示なし」
「それもやられたか。敵は?」
「北から装甲巡洋艦2隻が接近中。砲3門で射撃しています」
艦首側では発砲していない。どこまでやられたのか、まったく判らない。見張りが指差しながら叫んでいる。
「左舷後方に駆逐艦! 敵のようです!」
「副長、別な方向から敵駆逐艦が接近しています」
「近付けるな!…くそぅ」
駆逐艦はいつのまにかずいぶん接近しているけれども、まっすぐこちらへ向かっているわけでもない。1隻だけのようだが、単独でいったい何が目的なのか。
しかし、敵の装甲巡洋艦がどんどん接近してくるから、駆逐艦にかまってはいられない。近付くにつれて敵の射撃も激しくなり、また命中弾があった。不思議と艦首側だけで、後部には当たらない。ようやく測距儀が到着した。ケースから取り出し、包んであった布をはぎとる。
三脚に乗せられた基線長1メートルほどの測距儀は、本来のものに比べて格段に能力が劣るけれども、この際ないよりマシである。これを使うのも久しぶりだ。目を押し付け、慎重にピントを合わせていると、レンズの中で敵艦に水柱が覆いかぶさった。15センチ砲の大きさではない。
「味方の巡洋戦艦です! ヒッパー提督です !!」、水兵が腕を振りまわしながら叫んでいる。
振り向くと、そこには確かに『リュッツオー』の姿があった。『デアフリンガー』も続いている。その主砲がパッときらめき、オレンジ色の炎が吐き出された。測距儀に戻って着弾を見る。
いくつかの砲弾が、敵装甲巡洋艦へ立て続けに命中した。向きを変えようとしたのか、グラリと傾いた途端に、その艦首が爆発して、装甲巡洋艦は二つにちぎれる。後部もまた爆発した。何か巨大なものが空中に浮いている。丸のままの砲塔がひとつ、空を飛んでいた。それが海面に落ち、そのしぶきの中へ煙突が倒れていく。
装甲巡洋艦は煙に包まれるヒマもなく、赤い腹を見せてひっくり返ると、本当にあっというまに沈没した。2隻目は大きく向きを変え、必死に逃走を始めるが、数えきれないほどの水柱と、命中を示す閃光に包まれている。
周囲の兵たちが歓声をあげ、我がことのように巡洋戦艦の戦果を喜んでいる。感動のあまり泣いている水兵もいた。これで敵艦が爆発したのを見たのは2隻目だ。それもほんの5千メートルの距離でだ。なんという稀有な経験だろう。全身に鳥肌が立っている。
「左舷! 駆逐艦接近しています !!」
いつのまにか、装甲巡洋艦より近くへ寄られていた。もう4000メートルかそこらだ。
「左舷砲、240度の駆逐艦を撃て! 急げ !!」
砲を振り回している間に、接近していた駆逐艦は巡洋戦艦の副砲に射撃され、命中弾を受けたようだ。大きく舵を切って離れていく。その跡を追って砲弾が飛んでいくものの、なかなか当たらない。巡洋戦艦はまっすぐこちらへ向かってくる。間違いなく、我々を救助しに来ているのだ。
「左舷に魚雷! 雷跡が近付いています!」
さっきの駆逐艦だ。ゾオッと背すじに冷たいものが走る。水兵の指差す方向を見れば、不気味な白い泡の筋が、まっすぐに向かってきていた。こちらはまったく動けないのだから、避けるもなにもなく、ただ、逸れてくれるのを祈るだけだ。一回外れてくれれば、救助が間に合う。しかし、この祈りは天に通じなかった。
「雷跡接近します!…当たります !!」
「衝撃に備えろ!」
魚雷は狙いたがわず、ほぼ艦の中央部に命中した。艦全体が突き飛ばされたような衝撃があり、水柱があがる。艦は爆発の反動で右に傾き、甲板に汚れた海水が大量に降り注ぐ。砲員が何人か海へ流された。これではもう、浮いていることさえ難しいだろう。
魚雷を撃った駆逐艦は、砲弾の水柱を縫うようにして逃げていく。命中弾を示す火災を発生しているし、速力も落ちているようだが、なんとも勇敢で冷静な奴だった。それでも、装甲巡洋艦が注意を引きつけていなければ、これほど命中が確実な距離にまでは近付けなかっただろう。
振動が収まり、艦はいくらか傾いたところで安定した。缶室に浸水しているだろうが、それが拡大するか否かで、いつまで浮いていられるかが決まる。機関室の損傷がどの程度のものかは判らないが、浸水はほとんどなかったようだし、火災も大きくなかった。ボイラー室も四つあって全滅ということはなかろうから、修理できれば動けるかもしれない。
「溺者救助! カッターを降ろせ」
浮き輪が投げられ、大急ぎでボートが送られた。何人流されたのか。少なくとも一人が浮き輪にしがみつき、助けを求めている。
艦首側では火災が続いているけれども、ここからでは様子がつかめない。煙はちょうど煙幕のようになっているが、この艦を隠してくれるには風向きが悪い。
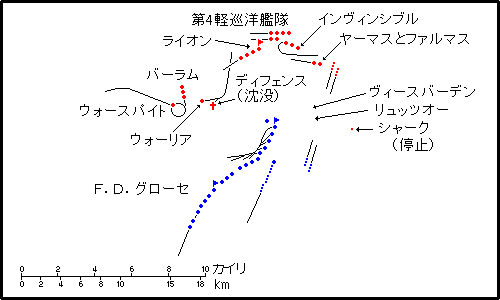
ヒッパー艦隊はかなり不規則な艦隊運動をしているけれども、これが停止した『ヴィースバーデン』の存在を意識しているのは明らかである。
『ヴィースバーデン』からは火災の煙が東北東方向へ流れており、両軍巡洋戦艦同士の視認を妨げている。退却する駆逐艦の中にも、煙幕を張っているものがいる。
ヒッパー提督の巡洋戦艦の隊列が接近してくる。もう2000メートルもないだろう。その姿は美しく、素晴らしく頼もしく見えた。このまま敵を蹴散らしてくれれば、救助の艦も近付ける。
太陽の位置がつかめ、巡洋戦艦隊が南西から接近していて、我々の南側を通過しようとしているのが判った。『フランクフルト』は南へ向かっていたことになる。周囲の乗組員は巡洋戦艦に向かって手を振り、その力強さに憧れの目を向けている。
装甲巡洋艦を吹き飛ばしたヒッパー艦隊は、今度はビーティ艦隊と砲撃戦を始めた。北方を西から東へ横切るビーティ艦隊と、南西からそれに接近しようとするヒッパー艦隊の砲撃戦を、その中間の位置で見ているのだから、なんとも素晴らしい特等席ではある。問題は、ショーが終わるまで生きていられるかと、終わったあと家に帰れるかだ。
戻ってきたカッターが吊り上げられようとしている。そのままにしておけと言おうかと思ったが、まだ沈むと決まったわけではないし、下手な言い方をすれば兵の間にパニックが生まれることもある。艦に魚雷が命中したことは、皆が知っているのだ。
巡洋戦艦は、水柱に包まれながらも射撃を続けている。彼らの陰にかばわれれば、少なくとも駆逐艦が横付けするくらいの余裕はできるだろう。そう期待した矢先、巡洋戦艦隊は一斉に南へ回頭した。
兵たちは声もなく、この光景を見詰めている。敵前に停止した自分たちを残し、頼もしい巡洋戦艦は5隻が5隻とも、艦尾をこちらへ向けて離れていく。何が起きたのか。北を見てもビーティの巡洋戦艦は針路を変えていない。危険を感じるような、接近してくる敵艦はいないのだ。
呆然と見詰める目の前で、巡洋戦艦はまた一斉に向きを変えた。180度回り、横一線に並んで、再びこちらへ向かってくる。何がなんだか判らない。
「あれを…南南西に煙が見えます」
リヒャルツが指差す靄の向こうに、かなりの量の煙がある。敵だろうか。…いや、あれはシェーア提督の艦隊のはずだ。1時間ほど前、南から北へ向きを変えたとき、南方にわずかに見えただけだったが、あの煙は高海艦隊に違いない。
 戻る
戻る
|
次へ

|
 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る
|