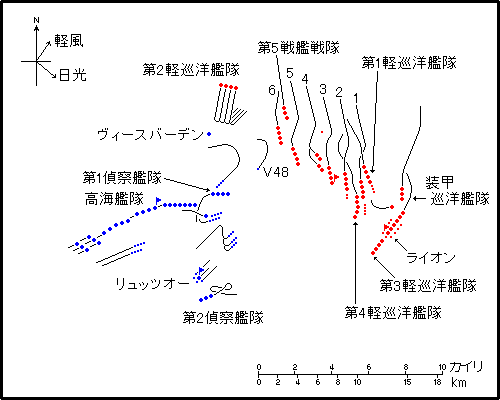
5月31日2015時の相互位置
|
ヴィースバーデンの時計 SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31 |
第三章・絶望・その2
測距儀の視野に入ったのは、ひとつしかない三脚檣が逆向きに立っている戦艦だった。艦首の砲塔が背負い式になっているから、34センチ砲を装備した新型艦ということになる。その後ろのは、少し旧式な初期のド級戦艦だ。三脚檣は2本あるので、『ドレッドノート』それ自身ではないのが判る。
前にいる新型戦艦と比べるとひ弱に見えるが、いずれ15センチ砲でどうにかなる相手ではない。どうせ意味がないのならば、戦隊旗艦だろう先頭艦のほうが目標にはよさそうだ。慎重にピントを合わせ、指標を読む。
「122…当ててみせろよ。ビールおごるぜ」
「言いましたね。ようがす、当てましょう」
本当に当たった。戦艦の砲塔側面の装甲に煙が立っただけだったが。
「チェッ、あれじゃあ痒くもないかな」
「いい腕だな。今度は28センチ砲を撃たせてやるよ。ヒッパー提督に推薦してやるさ」
「どうせなら新型の38センチ砲にしてください。天国にも軍艦ってあるのかなあ」
「そこが人間の世界ならな、ケンカの道具はなくならないだろうさ。神様の世界だったら、大砲は磨くためにだけ存在するんだ」
次の砲弾が発射されるのと同時に、戦艦からの報復の砲弾が命中した。最後の煙突が空中に浮き、横倒しに落ちてきた。主マストが道連れになり、探照灯台の下でポッキリと折れ、左舷砲の後ろに倒れる。左舷砲そのものには当たらなかったのだが、砲員はそれ以前に、破片と爆風で残らず打ち倒されてしまった。
後部指揮所にいたら、助からなかっただろう。幸運にも誰もいなかった。7番砲は幸運とは言えず、破片を浴びて、砲員の大半は死んだが大ケガを負っている。これで、無事な砲は艦尾の8番砲だけになった。
「砲が使えるかどうか、点検しろ。生き残った兵員を再編成するんだ」
リヒャルツが青い顔で走っていった。若者には酷に過ぎる経験だろう。しかし、なにかしていなければ、頭がおかしくなってしまう。幸い最後の戦艦戦隊は、それ以上の損害を与えることなく、遠ざかっていった。ようやく終わりかと思ったのだが。
「北から軽巡洋艦が接近してきます!」
敵艦隊の後衛部隊だろう。まだ配給があるのか…。しかし、まっすぐこちらへ向かっていた敵艦隊は、東へ向きを変えて、何か別なものを攻撃しはじめた。
「東方に駆逐艦です! 味方だと思われます !!」
先程の乱戦で突出し、損傷した駆逐艦だろう。速力が落ちてしまって、引き上げる味方から取り残されたようだ。火災を起こしているらしく、ボイラーからではない煙を引いており、その周囲は水柱に取り囲まれている。
敵の軽巡洋艦は4隻。綺麗に一列に並んだまま、哀れな駆逐艦へ迫っていく。黙って見てはいられない。
「射撃するぞ。配置に付け!」
幸い、左舷後部の6番砲は破壊されておらず、砲員が死傷しただけだった。7番砲は駐退機が破損している。直せるかもしれないが、今は間に合わない。残った砲員をかき集め、他のものに砲弾運びをさせる。
左舷側に測距儀を移し、距離を計っていると、副長が戻ってきた。
「どうした」
「敵の軽巡洋艦です。味方の駆逐艦を攻撃しています」
「ふむ。…よし、続けろ。当てたら一週間の休暇だ」
「そいつはいいですね。…距離65、射撃開始!」
すでに、本来の砲員で、まっとうな照準の訓練を受けていた生き残りは二人しかいない。砲も2門しかないから、過不足なしではある。こういう砲配置の巡洋艦では、戦闘による砲員の損耗は当然に発生するので、かなり多くの乗組員に砲の操作を教えていたのだが、これほど酷いことになるとは考えようがなかった。
こちらが動いておらず、振動もない状態だと、照準はかなり正確になる。初弾から敵先頭艦の至近距離に着弾したが、惜しくも命中しなかった。
「いいぞ、狙いは正確だ。続けろ。…あれはタウン級だな」
「15センチ砲が8門ずつですか。9門の奴もいるんですよね。相手にとって不足はないか」
とは言うものの、こちらの使える砲は2門しかないし、砲員はにわか仕立てだ。発射速度は速くなく、夾叉してもゲタを履いてしまう。
敵は艦首砲で駆逐艦を狙い、艦尾砲がこちらを撃ちはじめた。ほとんど損害を受けていないように見える軽巡洋艦4隻に対し、動くことのできない浮いているだけの残骸が一個である。勝敗など見えているが、これで駆逐艦が逃げ切れるのなら、代償としては安いものだ。どうせもう、支払い済みみたいなものなのだから。
「当たった!」
先頭艦の後部に、確かに命中を示す閃光があり、ひと塊の煙が見える。
「よくやった! どんどん撃て !!」
次の砲弾がまた近くへ落ちると、敵は反応した。一斉に向きを変え、4隻が横一列に並ぶと、艦首を向けてこちらへ向かってくる。
「いよいよだな。こいつは助からんだろう。シュタイン、世話になった。最後にいいものを見せてもらったよ」
「こちらこそ。あの戦艦は速力が落ちたに違いありませんから、味方にトドメを刺されるでしょう」
「そうあってほしいね」
がっちりと握手し、日に焼けたたくましい顔でニヤリと笑った副長は、砲弾運びを手伝いに行った。もう、射撃くらいしかすることが残っていない。
敵艦隊はずらりと等間隔に並び、まっすぐこちらへ艦首を向けている。こうされると、着弾の観測は非常に難しくなる。水柱と船体が重ならないので、遠近が判らなくなってしまうからだ。仕方がないから、少し手前に着弾させ、そこへ敵が突っ込んでくるような射撃をする。しかし、2門しかない砲が緩慢に撃っているだけなのだから、敵は軽く艦首を振るだけで、容易にこの着弾地点をかわしてしまえる。
口惜しいけれども、敵の指揮が見事なことは認めなければならない。あれはボンクラ指揮官のノロマ艦隊ではない。どんな男が艦橋にいるのだろうか、その艦橋に一発撃ち込んで、せめて慌てさせてやりたいが。
敵は艦首砲から砲弾を撃ち出しながら、ぐんぐん接近してくる。さすがに距離の詰まりかたが速すぎて当たらないけれども、十分に接近すれば向きを変えて、一斉射撃を始めるだろう。こちらはそれで終わりだ。
刻一刻、死神が迫ってくる。いったい何人目の死神かな。水柱がひっきりなしとなり、一発が中央部に命中した。誰かが倒れ、誰かがそれに代わる。残った2門の砲は、休むことなく射撃を続けている。
距離はもう3000メートルを切り、敵艦隊が向きを変えはじめた。必殺というには少し遠いだろうが、遠すぎるほどではない。いよいよだな。
「砲弾がありません!」
艦尾砲の砲員が叫んでいる。砲弾がなくなるほど撃ったはずはないから、運ぶのが間に合わないだけなのだろうが、これで抵抗もできなくなった。
見事な一斉回頭を見せ、敵艦は側面を向けると、必殺の一斉射撃を始めた。身を伏せてみても意味はない。これが最期だ。その瞬間くらい、見届けてやろうじゃないか。
砲弾はしかし、ほんのわずか射程が長すぎた。命中したのは2発だけ。それも1発は傾いていた前檣を直撃したもので、もう一発は7番砲の砲盾を削り取っただけで爆発しなかった。それでも、敵はこちらが沈むまで砲撃を止めはしないだろう。早いか遅いかだけの違いでしかない。
だが、誰の目にも信じられないことに、回頭して一列になった敵艦隊は、そのまま回って艦尾を向け、速力を上げて一目散に遠ざかっていく。煙幕を焚き、もうもうと煙を出して、その影に隠れようとしているらしい。なにごとだ?
「後ろ…右舷後方に艦隊です。…味方です!」
『ヴィースバーデン』が一斉に振り向いた。そこには、まごうかたなき高海艦隊全力の姿があった。シェーア提督は我々を見捨てていない。乗組員は口々に提督を称え、互いに肩を組んで涙を流し、勇ましい軍歌を歌いはじめる。これで助かる。誰しもがそう考えているようだ。しかし…
艦隊は南西から接近し、どうやら東へ向かって進んでいる。だが、東側には敵の戦列がある。ほとんどは、もう煙しか見えないけれども、その位置ははっきりしているのだ。近寄ってきた副長が左腕を吊っている。冷静に味方の艦隊を眺めながら、南東の方向を指差した。
「あの煙が、グランド・フリートだな」
「そうです。双眼鏡でなら、まだマストが見えます」
「いかんな。あれでは敵艦隊に理想的なT字を作られる」
「負傷なされたんですか?」
「たいしたことはない、肩を捻挫しただけだ。砲弾があんなに重いなんて、すっかり忘れていたよ。…こうしておけば重傷に見えるだろうからな、拳銃を隠しておくためのカモフラージュさ。イギリス兵が乗り込んできたら、一発お見舞いしてやろうと思ってだよ」
出血している様子はないのでホッとする。今は、全艦が副長のバイタリティだけで動いているようなものだ。小柄な副長は背伸びするように、もう一度味方の戦艦列を見渡している。
「まずい。これは本当に良くない。わかるか?」
「おおよそは。…あれでは、シェーア提督は敵の懐へ一直線です」
「しかも、南へ回り込まれる。退路を断たれ、包囲されてしまう」
敵艦隊の先頭はすでに見えないものの、進んでいた方角からして、味方の主力先頭からは南東方向にあるはずだ。シェーア提督は、おそらく敵の位置を正確には把握しておらず、これほど悪い状況とは考えていないのだろう。
高海艦隊の先頭が、グランド・フリートの艦列を発見したとき、それはほぼ一斉に視界に入るはずだ。正面にずらりと並んだ30隻ものド級艦に向かって、数で3分の2しかいない艦隊が、後部砲を使えない不利な対勢で突っ込むことになる。先頭が集中攻撃を受けて撃破されている間、後方の艦は何が起きているのかも十分に把握できないまま、前の艦に続いて悪魔の口の中へ落ちていくだろう。
「これじゃあ、ジェリコーが東郷になってしまうじゃないか」
リヒャルツがつぶやく。アドミラル・トーゴー…その名は一種の呪文のようなものだ。ネルソン、東郷、3番目に並び称されるのが誰になるのか、ここで高海艦隊が全滅すれば、間違いなくジェリコーが名を連ねることになる。
ツシマ海戦の研究なら、海軍艦隊の指揮を夢見る者である限り、避けて通ることはしない。今、ジェリコーはまさに、敵前での転回を終えた東郷の位置にいる。捕らえた敵が向かうべき根拠地との間にいて、優速かつ優勢な艦隊を指揮しているのだ。一国の運命を左右するほどの艦隊を率いて、これほど絶対的に有利な立場に立つことなど、望んでも得られるものではない。
自分たちが十分に絶望の淵にいながら、皆は主力艦隊の運命を案じ、固唾を呑んで情勢を見守っている。
砲撃が始まった。案の定、東側のイギリス艦隊は、ずらりと並んでオレンジ色の炎を吐き出した。予想していたよりも、先頭はいくらか東寄りに進んでいたらしい。だが、この程度では、結果にどれほども違いはあるまい。
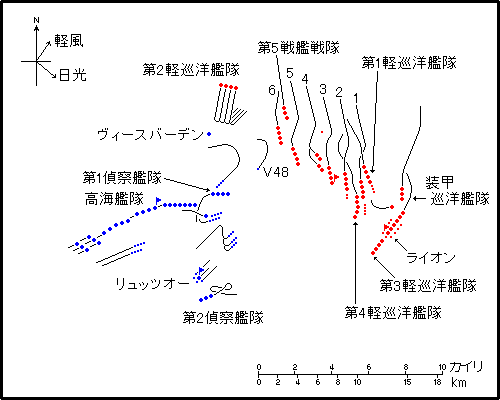
まさに絶望的な突撃に見えるが、実際にはシェーア提督は位置関係をそれなり把握しており、脱出をより容易にするための攻撃企画だったとされる。
この瞬間、シェーア提督も状況を悟っただろうが、もうどうしようもない。北へ逃げれば根拠地から切り離され、後ろから順繰りに食われてしまう。全力で逃げたとしても、真夜中にスカゲラック海峡へ突っ込むハメになり、半分はノルウェーの海岸へどし上げるだろう。奴らなら海峡の中まで追ってくるに違いない。
南へ逃げれば、敵の懐の中で、撃たれるのに好都合な同航戦になる。頭を押さえられているから、前へ前へと回り込まれ、文字通り袋だたきにされる。ツシマ海戦の再現だ。
味方艦隊が完膚なきまでに叩き潰される光景が、まさに目の前に展開しようとしている。握りしめた手のひらに、汗がじっとリと浮いていた。遠い雷鳴のようなゴロゴロという音が聞こえてくる。世界最強艦隊の一斉射撃の音。
絶体絶命。
しかしそのとき、我らが提督は、おそらく他の誰にもできないだろう手腕で、この窮地を切り抜けた。
戦艦がみるみる小さくなる。次々に幅が狭くなり、また広がっていく。そして、艦隊は全体が東から西へ向きを変え、前後を入れ替えて敵から遠ざかりはじめた。
「すごい……敵前で一斉回頭とは。それも16点…」
「巡洋艦の艦隊でもやらないですよ。訓練でも、あれは危険すぎます」
縦一列の単縦陣では、理論上、16点一斉回頭によって艦隊の向きを変えることができる。命令信号を掲げ、各艦に準備させておいて、発動と同時に一斉に向きを変えるのだ。
実際には、後方の艦が先に舵を取り、それを見た前艦が舵を切るという具合に、後ろから前へと行動が伝播していく。それでも、信号を誤解したり、行動が遅れたりで隊列は乱れてしまうし、下手をすれば衝突事故も起こる。
16点の回頭は、艦の向きを180度変えることだから、その難度は8点、90度の回頭とでは桁違いに高い。事故の確率は跳ね上がり、隊列の乱れは避けようもない。現実にいくらか混乱はあるようだが、シェーア提督の艦隊は、見事にこの運動をやりとげた。
 戻る
戻る
|
次へ

|
 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る
|