ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
お急ぎの方はこちらからどうぞ
第三章・絶望・その1
それからの30分間、『ヴィースバーデン』は、ほぼすべての英戦艦に撃たれた。イギリス艦隊が不自然な形に展開したため、互いが邪魔になって撃てなかった艦がいたし、煙と靄も味方をしてくれたから、ひっきりなしに砲弾は降ってくるものの、命中したものはいくらもなかった。
グランド・フリートは、こんな動けない残骸がそれなり邪魔になるらしく、踏み込んで来ずに大回りするような弧を描いている。15センチ砲で狙える範囲へも近付いてくれない。遠間から、及び腰で戦闘をしているかのようだ。
見ていると、前の戦隊の動きに追従しきれず、つっかえて止まり、余剰蒸気を噴き上げる戦艦がいる。追突しそうになって後進をかける艦があり、団子のように固まってしまう戦隊もいる。なんとも情けないノロマ艦隊だ。指揮官のボンクラぶりが目に浮かぶ。
その狙いの悪い砲弾の雨の中、撃たれることに無頓着になった我々は、リヒャルツに砲を任せて、最大射程に近い距離で緩慢な射撃を行ないながら、せっせと自分たちの仕事に精を出していた。
「シュタイン大尉、副長です」
「はい、シュタインです」
伝声管は艦橋からのものだ。あそこには誰もいないはず。
「34センチ砲の斉射なんか見ていても楽しくないからな、ちょっとひと仕事さ。水中発射管をようやく発射できるようにしたんだが、指揮装置がダメだから、なんとかしようっていう相談だよ」
「どこにおられるんですか?」
「艦橋の真下だ。伝声管を途中でちょんぎって、ラッパをつけただけさ。さて、ここまでは声が届くわけだ。そこで照準して、発射角度を伝達してくれんか」
なんというバイタリティだろう。
「判りました。誰か、そちらに照準のできる水雷課員はいますか?」
「いや、上の発射管にいるだろう。そっちで探してくれ」
「判りました」
下の発射管室では、自分で照準するということがないわけだ。
「兵を何人か貸してくれ。ここから発射管室までは伝令せにゃならん」
「了解しました」
すぐに人数を手配し、簡易照準盤を用意させる。水雷課のクライン少尉が手伝ってくれ、使い方を思いだした。
「一応は勉強したからな。劣等生だったが」
基本は砲と同じだが、よほど単純だ。現在の方角と的艦の速力、距離、進行方向といったデータは同じで、魚雷の進行に時間がかかる分、計算すべき数字が大きくなる。違うのは修正という考え方がないことだ。外れると、どっちへ外れたのかも判らない。
「副長が、まだ撃てないかと聞いておられます」
「遠すぎる。魚雷が届かないと言ってくれ」
「ちくしょう。いくじなしどもめが」、リヒャルツが副長の気持ちを代弁してくれた。
多分、下でも副長が同じことを言っているだろうと想像し、思わず笑みがもれる。
ときおり命中する砲弾があり、数えきれないほどの至近弾がある。しかし、どうやらイギリス戦艦は、戦艦を撃つつもりで徹甲弾を用意していたらしく、爆発する砲弾は多くない。大半はただ水柱を上げるだけで、まったく無害だった。命中したものも、半分は不発だったのである。
副長が、連絡の不自由な発射管室にいるため、被害報告は私のところへ来る。その伝令も、だんだん勢いがなくなってきた。
「艦首に命中弾。司令塔に直撃しました。艦首砲についていた者は全滅です」
走って報告にきた兵は、ボロボロと涙を流している。
「砲は?」
「わかりません。…また火災が発生して、…下の甲板が燃えています。…近付けないんです…」
すすりあげ、泣きじゃくる少年は、途切れ途切れに話すのがやっとだ。
「泣くんじゃない。辛いのはわかるが、見たことを報告するんだ」
「はい…でも、ハンスが…ニーマン二等水兵が、…海の中へ飛ばされちゃったんです」
ハンスは友達のことなのか。この水兵もせいぜい16か17、ほんの子供だ。
「もうすぐ、また一緒になれるさ。でも、砲が無事なら、そんなことをした敵に、一発でもぶちかましてやれるじゃないか」
「はい…」
かつて、これほどの恐怖と絶望が、一艦を覆ったことがあるだろうか。すべての味方を合わせたより強力な敵艦隊が目の前にいて、まったく動けない自分たちを、よってたかって殺そうとしている。砲弾が落ちるたびに誰かが死に、生き残った者も、その死が、単に偶然の順番にすぎないと思い知る。
左舷の発射管が破壊されたと報告が上がってきた。水中発射管室は無事で、まだ連絡は確保されており、発射準備はできているままだ。
15センチ砲のほうも、射程に入った敵を攻撃しようにも、砲弾が上がってこないのでポツポツと撃つだけだ。人数が減り、皆が疲れているから、砲弾を持ち上げられなくなってきている。砲側には、うっかり接近してくるかもしれない、15センチ砲弾が意味を持つだろう相手のために、1門あたり10発ずつが取り置かれている。
それを越えた分が発射されるものの、目標は戦艦だから、当たったところでどうにもならない。一人か二人死ぬかもしれないというだけだ。
「敵戦艦が回頭しています」
こちらをかわすのに我慢しきれなくなったのか、なにか他の理由かは判らないが、敵戦艦艦隊は戦隊ごとに針路を変えている。これだと、一番しんがりの戦隊はかなり接近することになる。
「副長、伝声管へ」
「どうした」
「手ごろなのが来ます。敵艦隊が回頭したので、一番後ろの戦隊がかなり近くなりそうです」
「ようし、一発ぶちこんでやる。方位は?」
「現在295度です。距離は110ヘクトメートル。推定速力は18ノット」
「針路は?」
「東南東に近いようですが、まだ定針していません」
「どんな奴だ」
「新型の戦艦です。ジェリコーの『アイアン・デューク』かもしれません。いい的ですよ」
「ようし。まさか、こんな残骸から魚雷が来るとは思っていないだろう。一泡吹かせてやる」
観測した数字を表の上で連続的に追っていく。あまり接近するまで待っていれば、こちらが先に吹き飛ばされるだろうし、角度が悪くなって撃てなくなる。
定針した敵戦艦との諸元を確認し、数字を割りだす。私の前にリヒャルツとクラインが頭を寄せ合い、発射のタイミングと魚雷の針路を決めた。副長に伝達して魚雷が調定される。
「準備できたそうです。いつでもいい、と」
「判った。秒読みするから、声を合わせてくれ」
艦の中心線に合わせた発射盤を睨み、その上に時計をかざしてタイミングを計る。イレーネ、当てさせてくれよ。
「用意…3、2、1、発射!」
「発射!」、伝声管の向こうで、副長の声が小さく聞こえた。
一呼吸おいて軽い振動を感じ、魚雷が発射されたと判る。ほどなく白い泡の帯が浮かび上がってきた。
「どうだ !?」、心配そうな副長の声。
「雷跡進んでいます。魚雷正常」
まずはひと安心。後は神頼みだ。
今の距離を魚雷が進み、敵艦の未来位置へ到達するには、10分ほど時間がかかる。その間、こちらは撃たれっぱなしだが、今は気にもならない。魚雷の跡を追うだけだ。発射した時刻は19時47分。雷跡は順調に進んでいて、見ている限りでは命中コースにある。敵が気付いて回避するのが遅れれば、命中するに違いない。
「追えるか?」
息せききって副長が駆け上がってきた。測距儀を譲る。
「うん、うん、いいぞ、そのまま行け!」
握りこぶしを振り回す副長は、測距儀から目を離そうとしない。
やがて、こちらから雷跡が見えなくなり、残り時間が少なくなった頃、敵戦艦が傾いたように見えた。魚雷に気付いて舵をとったのかもしれない。
「ふん、そいつは織り込み済みだ。そんなノロマな舵じゃあ逃げられんぞ」
測距儀を覗いたままの副長が怒鳴っている。まだ、それと判るほど戦艦の針路は変わっていない。大きく、重い戦艦は鈍重だ、駆逐艦のようにひらりひらりとは動けない。
「そうだ、そうだ、それでいい、そのままだ! 当たるぞ、ざまあみろ!」
まるで雷跡が見えているかのようだな。そんなはずはないが、副長の魂は魚雷に乗り移っているのだろう。双眼鏡を向けて敵艦を見ていると、ポーンと横腹に水柱が立った。誰もあれを砲撃してはいないから、間違いなく魚雷の命中だ。ちょうど艦橋の真下あたりに当たった。
自分で照準した魚雷が、思い描いた通りに命中したのだ。ジーンと腹の中に熱いものが湧いてくる。
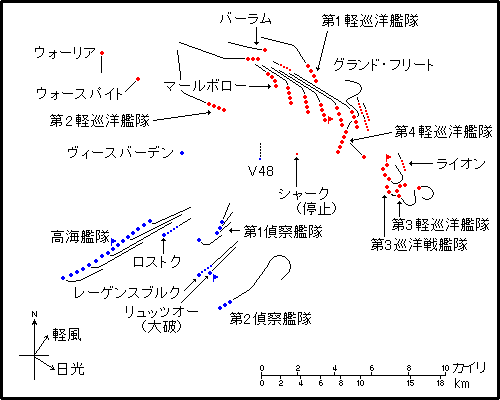
5月31日2000時の相互位置
19時57分、英戦艦『マールボロー』Marlborough に魚雷が命中した。同艦では爆発するまで魚雷の接近に気がついておらず、最初は機雷と考えられ、魚雷の破片が発見されてからも潜水艦の雷撃を受けたと考えられた。
この魚雷は位置関係からして、『ヴィースバーデン』か駆逐艦『V48』かのいずれかが発射したものでしかない。
『マールボロー』は、ジェリコーの旗艦『アイアン・デューク』と同型である。
「全艦に伝達。本艦の魚雷が敵戦艦に命中した」、リヒャルツの声はうきうきしている。クライン少尉も嬉しそうだ。
ニュースは歓声と共に受け取られ、上甲板に人が溢れる。まだこんなに生き残っているのか。時刻はもう20時になる。命中したのは19時57分か58分というところだな。副長は嬉しそうにメモを取っている。幸運に感謝して、蓋の裏の名前を撫でた。
魚雷の当たった敵戦艦がどうなるか、皆がなんらかの変化を期待して見詰めている。しかし、魚雷を受けた戦艦は、若干遠ざかる針路をとったものの、そのまま戦列を崩さずにいる。
ひっくり返るか、爆発して消えてなくなりでもすれば、皆はもう満足の極地に達するのだろうが、蜂が刺した程度の軽傷では、フラストレーションは解消しない。お返しの砲弾が飛んできているのを思い出すと、上甲板に人影はなくなる。
魚雷を命中させた戦艦隊の後方に、別な艦隊が見えてきた。最初の南下戦のとき、後ろから追いついてきた38センチ砲装備の最新型高速戦艦のようだ。4隻いたのが3隻に減っている。敵も相当に損害が大きくなっているのだな。それでも、高海艦隊全体に追われて1隻しか失わなかったとすれば、やはり相当にタフなのだろう。
「右舷側は発射できんかな」
「この角度では難しいですね。撃てる範囲に入るかどうか」
「こっちが浮かせておいてもらえるか、もだな」
そういえば味方が見えない。どっちへ行ったんだ?
「さっき、一斉に南へ向きを変えて、遠ざかっていきました。ちょうど、魚雷を発射した頃です」
見張りの兵は見ていた。こちらが魚雷に夢中だったので、あえて報告はしなかったらしい。
おいていかれたか。…仕方あるまい。グランド・フリートの全力が出撃してきているからには、シェーア提督といえども、艦隊を無事に持って帰るだけで大ごとだ。捕まれば大変なことになるが、日没が近いから逃げきれるかもしれない。いや、逃げきれるに違いない。
もう、救助はアテにできないだろう。自分の面倒は自分で見るしかない。延々と続くイギリス戦艦の艦列は、まだ途切れそうもなく、次々に砲弾が飛んでくる。当たらないのが不思議なくらいだ。
不遜なことを考えるからいけないのだな。なぜ当たらないかと思った途端に、巨大な砲弾が命中した。衝撃と共に一番前の第三煙突が傾き、右舷側へ横倒しになった。第二煙突も大きく傾いている。第一煙突のおかげで、後部指揮所にはほとんど破片が飛んでこなかったけれども、両舷の砲員に損害が出たようだ。被害報告が錯綜する。
別な一発は左舷舷側に命中し、大穴が開いているという。命中の衝撃は大きく、振動も凄まじかったが、艦が傾いているような様子はない。なぜだろう。
「やられたか。でもなあ、もう手当てする方法がないんだ。軍医は死んだし、病室そのものが吹き飛ばされて、何も残っていない」
副長が悲しげにつぶやく。どうせ最後の運命は同じでも、目の前で苦しむ同僚に、何もしてやれないのは悲しすぎる。
後部砲2門が、右舷艦首寄りギリギリの角度で仰角をとり、7番砲のギュンター掌砲長が手を振っている。
「撃てるのか?」
「ギリギリ撃てそうです。射程をお願いできますか」
「今行く。…指揮所退避。遮蔽物へ入れ。…副長、ここにいると耳を潰されます」
「そうだな」
下へ降りると、副長は艦内の状況を調べに行った。
測距儀の三脚を抱えて後甲板へ降り、砲弾を抱えた乗組員たちの間を抜けて、艦尾8番砲の右舷側後方に三脚を据えると、測距儀を向けて敵との距離を計る。掌砲長のフライタークが、準備を終えて指示を待っていた。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
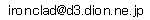
 第1章
第1章
 第2章
第2章
 第4章
第4章
 第1章
第1章
 第2章
第2章
 第4章
第4章
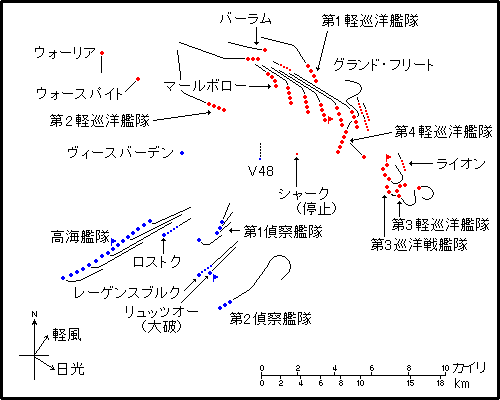
 戻る
戻る

 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る