ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
第三章・絶望・その3
「敵へ突っ込んでいく部隊があります!」
駆逐艦の突撃は当然だが、その中にひときわ大きな一団がいる。双眼鏡を向け、その姿を見詰めた。
「ヒッパー提督の艦隊です。…1隻足りません。『リュッツオー』か『デアフリンガー』がいません!」
「やられたのかな…」
時間はもう20時を20分ほど回っている。あたりは薄暗くなり、日没まで1時間かそこらだ。太陽が沈んでも、この緯度では真っ暗になるには時間がかかるが、敵味方識別も、照準も非常に困難になる。おそらく、これが最後の大規模な戦闘になるだろう。
敵艦を何隻も爆沈させた殊勲の第一偵察艦隊だが、当然に無傷のはずはなく、被害は累積しているに違いない。現に、その艦上で発砲している砲の数は、明らかに少なくなっている。その姿は数知れぬ水柱に取り囲まれており、命中弾を示す閃光と煙があがるたびに、まるで自分が刺されているかのような痛みが感じられた。
1隻足らない艦が沈んだのか、ただ落伍しているだけなのか、情報から切り離されて久しい『ヴィースバーデン』からは何も判らない。電力はまったく回復せず、無線の送受信は完全に途絶えたままだ。助けを呼ぶのすら困難なのだが、味方ももう、この艦を助けにくる余裕はあるまい。
シェーア艦隊は急速に西へ向かい、何が起きたのか把握できていないだろうボンクラジェリコー提督は、やはりトーゴーでもネルソンでもなかった。艦隊を回して追うこともできずに、まっすぐ南へ走っている。見事な艦隊運動が、絶対優勢な敵を振り切ったのだ。胸の中に熱い塊がある。
もし、立場が逆ならば、シェーア提督こそが、ネルソン、東郷と並んだはずなのだ。確かに、いくら見事に逃げおおせても、脱出は勝利ではない。誰も、勝ったとは認めてくれまい。それでも、負けを取り返して引き分けに持ち込むならば、それは勝ったに等しいと主張できる。少なくとも私の中では、シェーア提督は二人の偉大な提督と肩を並べる存在になった。
どんどん暗くなってきているから、もう全体が捕まってしまうことはあるまい。やれやれひと安心というところか。…しかし、駆逐艦の1隻くらいは、こっちへ回してほしかったな。
「東の方に駆逐艦らしい艦が止まっています」、リヒャルツはまだ元気だ。
これほどに気を奪われる光景が続いても、自分のするべきことを忘れていない。生き残れれば、立派な士官になれるだろうに。
「どこだ?」
「艦首から30度…35度くらいです」
100ヘクトメートルくらい先に、暗い灰色の影が、うずくまるように動かないでいる。大きさからすれば駆逐艦だが、敵か味方か、この距離ではまったく判別できない。
さっき、敵の軽巡洋艦に追われていた駆逐艦ではない。あれは低速でヨタヨタと南のほうへ逃げていったのを見ている。それとは別な艦なので、敵味方を推測する方法はない。いずれ動けないことに変わりはないようだから、同病相哀れむで、いちかばちか攻撃するなどという気にもならない。
それに、救助が来ていないところからすれば、味方の可能性が高い。イギリス艦なら、誰か救助に残すくらいの余裕はあるだろう。信号を送る方法はないし、旗が見える距離でもない。もう十分に暗いから、見えるのは信号弾くらいだろうが、下手なことをすれば敵を呼び寄せるだけだ。
その、呼びもしない敵が、また襲ってきた。
「艦首方向、敵巡洋艦です!」
「さっきの奴らだ。しつこいイギリス人め!」
一度は逃げた軽巡洋艦隊が、シェーア提督の一斉回頭を見て獲物のことを思い出したらしい。北から南東へ向かいながら接近してくる。
しかも、今度はさっきよりも艦首寄りなので、後部の8番砲は射撃できない。撃てるのは左舷の6番砲だけだ。それも、かなりギリギリ艦首方向へ向けてである。
倒れた煙突が邪魔になって、測距儀を据える場所がない。背の高い構造物はほとんど残っておらず、横たわった煙突が視界を塞いでいる。艦首側へ行かなければ。
三脚を持ったまま移動しなければならないし、真っ暗だから、艦内は通りにくい。両舷の通路へ水兵を走らせ、艦首までの通路を確認させる。リヒャルツに命じて、測距儀を三脚から外させた。
「左舷側はダメです。煙突が邪魔で通れません!」、大声が聞こえる。
「右舷は発射管のところまで行かれます」
とりあえず右舷側だな。測距儀を握りしめ、畳んだ三脚をリヒャルツに担がせて、伝令要員に8番砲の砲員を連れ、瓦礫をかわしながら進みはじめる。まさか、自分の艦でこんな障害物競争をやるとは。
機関室上の甲板は、最初の砲弾の命中で歪み、凸凹になっている。右舷後部の5番砲は、砲そのものの損傷はともかく、真下の支えを撃ち飛ばされて傾き、使えるような状態ではない。こうなったのが誰に撃たれた時だったか、思い出せない。
倒れかかった第二煙突の下をくぐり、へし折れたボート・ダビットのジャングル・ジムをかわして、前へ出てから預けた測距儀を受け取る。持ったままでは通れないのだ。ぶつけないように、慎重に。さらに前進すると、一見無傷そうな発射管の先で、第一煙突に遮られた。ひしゃげた煙突が道を塞いでいる。
「上は行けるか?」
「前へは行かれませんが、左舷側へ出れば、なんとかなりそうです。でも、ラッタルがありません。壊れてます」
上の甲板にいる兵の報告だ。こちら側は上がれるが、下りる道がないと言う。甲板室の切れ目にある左右通路は、缶詰の蓋を開けたように砲弾で切り開かれた、ギザギザの鉄板がとおせんぼをしていた。すぐ脇に甲板室の入口があるものの、中は真っ暗だし、誰も内部を確認していないから、入ること自体が危険だ。突然、床がなくなっているかもしれない。
ほんとに浮かぶ残骸だな。ほとんど艦尾から離れなかったので、艦首側がどうなっているのかは副長から聞いただけだった。調べれば甲板室を横断できる場所があるかもしれないが、登ったほうが速そうだ。
船首楼甲板に上がると、第三煙突を根こそぎひっくり返した砲弾が、甲板室を削り取っており、前へ行く方法がない。どのみち、少し先で艦橋が潰れているから、通りぬけられはしないだろう。甲板の穴を覗き込むと下は真っ暗で、どうなっているのかまるで判らない。この下は何の部屋だったかな。
第二煙突は、途中で空気が抜けたかのように潰れ、右舷側に大きく傾いている。左舷の発射管も、ポッキリ折れて前半分がお辞儀をしている。砲弾の破片か何かが、ラッタルの上半分を削り取っていた。
見渡せば、ところどころにボート・ダビットが残っているが、ボートはどこにもない。とっくに全部が吹き飛ばされたのだ。いや、一パイだけが、煙突の下で潰れている。
ひとりずつ左舷の上甲板に飛び降り、測距儀と三脚を手渡しで下ろす。そうしている間にも、艦の周りに水柱が立ちだした。ここからなら、辛うじて敵艦が見えるが、もう少し前へ行ったほうが視界が広がる。
大きな声がした。倒れた第一煙突を挟んで、向こう側の乗組員が何か叫んでいる。
「どうした」
「ちょっと待ってください。…煙突が邪魔で砲が向けられないと言っています!」
倒れた煙突の先端は甲板から食みだし、2メートルくらい海の上へ突き出している。これが邪魔になり、左舷の砲からは敵が見えないという。艦尾の砲は敵には向けられない。つまり、敵は完全に死角に入っているのだ。
もう、艦首ほぼ正面にまで回り込まれた。これではどうしようもない。
「艦首砲はどんなだ?」
「ダメです。右砲は砲架から落ちていますし、左砲はひん曲がっています」
右舷の3番砲は艦橋の瓦礫の下だ。それは見たばかりである。目の前の4番砲は、魚雷の命中で取り付けられた甲板そのものが歪んでいる。見て判るほど傾いているのだ。
測距儀と三脚も、こうなれば宝の持ちぐされだ。5千メートルほどに接近した敵艦は、容赦のない砲弾を浴びせてくる。まるで、この艦がまだ浮いていることが、犯罪だと言わんばかりに。
つっ立っていても意味がないので、隔壁を背に座りこむ。遠からず艦が沈むだろうと思えば、下へ降りる気にもならない。ついてきた者たちもそれに倣った。
こうすれば敵は見えないが、飛び越えていく砲弾のシュルシュルという不気味な音と、水柱は隠しようもない。音がしたときには、砲弾はすでに通り過ぎているのだから、何をしてみても無意味なのは知っているけれども、どうしたってあの音には首がすくんでしまう。
砲弾が、自分のいる場所に落ちてくるかもしれないという感触は、不思議なほどに現実的でない。実際、直撃している砲弾はほとんどなく、景気のいい水柱だけが、攻撃されていると実感させてくれる。あの指揮官の操艦は見事だったが、砲術訓練は不十分だったらしい。
ポケットに手を入れ、時計を握りしめる。時間を見る気にはならない。それは、生き残ったら考えることにしよう。
一発の砲弾が、艦から20メートルとない海面で炸裂した。ほとんど水面直下で爆発したらしく、その閃光がはっきりと見えた。ガンガンという音がし、バケツというより、風呂桶でぶっかけたような海水が浴びせかけられる。
脇へ立てかけてあった測距儀が流され、あやういところで飛びついた。その目の前の船体に突き刺さった鉄片が、海水を浴びてシューシューと湯気を立てている。あの音は、砲弾の破片が艦に当たる音だったのだ。
「リヒャルツ中尉…」
うめき声が聞こえて振り向くと、リヒャルツが自分の腹を押さえていた。
リヒャルツの体の下には、海水に混ざっておびただしい量の血が流れている。たぶん、砲弾の破片が大動脈を断ち切って、背中まで抜けたのだろう。手当てをする方法など何もない。体の中身が抜けて、まるで風船が縮むかのように、一言も発しないまま、リヒャルツは息絶えた。傷口を押さえていた腕が落ち、がっくりと首がうなだれる。
すぐ隣にいた私と、リヒャルツの反対側にいた水兵には、小さな破片ひとつ当たっていない。たまたま砲弾が当たった場所にいた誰かが死に、当たらなかった者が何分か生き延びる。いずれ、行く先は同じだ。フライタークはさっき、天国と言っていたが、イギリス人なら地獄に違いないと言うだろう。我々ドイツ人が死んでから行く先は、地獄に決まっているのだと。
砲撃が止んだ。撃ち疲れたのか、何か他の理由か、艦首甲板へ出てみれば、遠ざかっていく煙だけしか見えなかった。主力から相当に遅れていたから、道草を食っているヒマがなかったのだろう。
我々に引導を渡し、生存者を救助して手柄にするより、艦隊内での位置を確保するほうを優先したわけだ。まだ彼らの戦いは終わっていないのだから、賢明な判断と言える。さすがに腕利きの指揮官だ。
まだ足元はしっかりしており、急速に沈むような様子ではない。だいぶ乾舷が低くなり、海面が近くなっているのは間違いないけれども。
砲弾はいくつも当たらなかったが、至近弾による弾片で、船体の穴の数は確実に増えている。魚雷を貰っていなければ、吃水線付近は装甲があるから海へ繋がっていないはずで、かなり長いこと浮いていられるだろうが、すでに艦首はずいぶん沈下しており、装甲のない部分の穴の多くは水面下にあるから、遅かれ早かれ沈没は免れない。
敵も味方も南へ去ってしまい、はるか遠くにチカチカと発砲の閃光が見えている。どちらもこちらのほうへ戻ってくることはあるまい。明日の朝まで浮いていられれば、誰かが見つけてくれるかもしれないが。
「駆逐艦が見えなくなりました」
半闇を透かしてみるが、たしかに見えなくなっている。暗くなって見えなくなっただけなのか、沈んでしまったのか。敵の軽巡洋艦にトドメを刺されたのかもしれない。もし敵だったにしても、見えなくなっただけだと思いたい。こんな夜の海で、誰も見ていない中で沈んでしまうなど、悲しすぎる。
21時過ぎ、ほぼ日没と同時刻に、敵味方の船は一切が見えなくなった。孤独な『ヴィースバーデン』は、静かな北海にただ一人、動くこともできずに横たわっている。
第三章・終わり
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
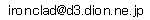
 戻る
戻る

 戻る
戻る

 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る