ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
お急ぎの方はこちらからどうぞ
第四章・漂流・その1
これほど異様に静かな海は、長い海軍生活でも初めての経験だ。まったく機械が動いていないから、舷側に当たる波と、揺れてこすれる鉄の音がするだけで、他には何も物音がしない。
明日の朝まで艦を救う手立てを講じるか、逃げ出して生き延びる算段をするか、何もせずに沈むのを待つか。我らが副長は、黙って待つ性分ではあるまい。死んだという報告はないから、どこかで何かをやっているに違いない。あの人のエネルギーが尽きることはあるのだろうか。
後甲板へ戻り、砲の状態を詳細に点検させる。こうなれば懐中電灯の光くらいは問題にならないだろう。左舷の6番砲は、いつのまにか破壊されていた。破片に砲身が叩かれ、内側が膨らんでいる。これでは、撃っても砲弾は砲身から出ていけず、砲身が爆発する。破片の当たった傷は、だいぶ前からあったと言う者もいるから、最後の軽巡洋艦へ向けて撃っていれば、そういう事故になったかもしれない。
「シュタイン、何かしているか?」、早速だ。
「砲を調べさせています。いますぐに使えるのは、この1門だけです」
「誰かに記録をとらせろ。何がどう壊れたか、どう修理したか、どのくらいの範囲で能力が回復するか、をだ」
「はい、早速…なにか?」
「君がするんじゃない。誰か他のものにやらせるんだ。これから艦内をまわって、状況を調査する。一緒にきてくれ」
後を8番砲のフライターク掌砲長に任せ、副長について行く。見るべきものがどれほどあるのか、ずっと艦尾上甲板を離れなかったから、何も判らない。さっきわずかに見ただけでも、知っている艦とは思えないような変わりようだった。
艦内は真っ暗なのだが、無事な懐中電灯は浸水防止作業に使われ、手元には二つしかない。人のいる部屋にはランプが灯されていた。部屋は奇妙に暖かく、聞いてみると暖房が入っているという。しかし、ぬくぬくと温まっていられる状況ではない。書記役の主計課員と伝令を連れた我々は、状況を見ながら各部の生き残りに行動を指示していく。
艦尾の諸室は、舷側に弾片で穴が開いているというだけで、あまり破壊されておらず、浸水もほとんどない。消火に使われた水が、排出しきれずに残っているだけだ。もともと燃えるものが少なかったからか、大きな火災は兵員居住区の艦首側でしか起きなかった。
戦闘中に士官私室のいくつかが燃え、すぐに消火されている。機関長の私室には、火災の跡があったものの、報告はなかったし、消火の痕跡もない。自然に消えたようだ。燃える物のない艦というのは、それだけで意味があるのだな。
舵機室は異常なし。操舵機も人力で正常に動作するが、艦が動けないのだから、まったく意味はない。
後部の弾薬庫は、砲弾がだいぶ減っているというだけで損傷はない。まだ残っていた兵には、すべての15センチ砲弾を上甲板へ上げるように命じた。人力でホイストを動かさなければならないが、1発45キログラムだから、急ぐのでなければ重労働ではない。箱に入った大量の52ミリ砲弾は、砲そのものが使えないので、無用の長物になっている。
艦の水線下では、隣の部屋へ移るにも、一々中甲板まで戻らなければならない。水密横隔壁に扉が付いていないからだ。不便ではあるけれども、だからこそ浸水が拡大せず、まだ艦が浮いているのである。
直前の補機室を覗いてから、機関室へ下りる。推進機械は、完全に息の根を止められていた。浸水は多くないけれども、舷側の大破口が海面に達するまで、どのくらいかかるかで沈没時期が変わる。この破口から海水がなだれこめば、艦はあっという間に沈む。
砲弾は、機関室の右舷舷側の一番高いあたりに命中し、斜め後方へ向かって甲板装甲の傾斜部、水平部との取り合い付近を貫通していた。機関室から見ると、天井に大穴が開いている形だ。
2発がほぼ同じように命中したらしいが、爆発した位置の違いで、穴の開き方はまったく異なる。いくらか艦尾寄りに当たった砲弾は、後方の横隔壁を破り、補機室をメチャクチャにしていた。
「ポンプは無事か?」
「ヤー・ヘル、今のところは。あの穴から水が入ってきたら、どうしようもありませんが」
返事をしたのは、現在の責任者、機関兵曹のグリュンベルグである。本来の機関室乗員は、噴出した蒸気で蒸し焼きになったか、弾片で切り刻まれたかだった。見る影もなくなって散乱していた遺体は、機関長の事務室に運び込まれている。誰も、それを上甲板まで上げようとは考えていない。
どのみち動く機械はないから、今は少しずつ入ってくる海水を、人力ポンプで排出するしかすることがない。この広い部屋が無事だったから、まだ浮いているのだ。
後方の補機室も、中はボロボロで二重底との隔壁も穴だらけだったが、浸水は少なく、すでに応急処置でほとんど止まっている。今は、状況を監視する兵が残っているだけだった。
「なにも発電機まで潰さんでもなあ…」
「悪いことは重なるものです。ディーゼルまでダメだなんて」
副長が補機室との隔壁の穴を懐中電灯で照らしている。ここへ来る前に入ってきたが、途中からラッタルがなくなっていて、ロープを使わなければ下りることができなかったそうだ。今はハシゴがかけてあった。
補機室の下にいた兵は、無事な機械はひとつしかないと言い、唯一動くというディーゼル・エンジンを撫でまわしていた。貫通した砲弾は、ちょうど発電機そのものに当たったところで不全爆発したらしい。割れたコップのような弾体の半分は、部屋の隅に転がっていた。イギリスの砲弾は出来が悪い。
冗長性確保とテストの目的で、2種類の発電機を積んでいたものの、発電機そのものが両方とも壊れてしまっては、どうしようもない。ディーゼル・エンジン自体は、損傷も軽く修理が終わっているそうだが、燃料もないのだ。タンクからの配管が壊れ、流れてしまった。それに気付いたときには、燃料はすでに残っていなかったのである。しかし、燃料があったところで、回転を伝えるべき何かはない。なにもかもが、二重三重に壊れている。
隔壁を見上げていた副長の目は、機関室のタービンに戻った。
「これは生きているのか?」
「直せば回ると思いますが、接手が…」
「判っている。せめて逆だったならなあ」
左舷機には、新開発の小さなギア付タービンが、巡航用に備えられている。テストとして片方にだけ取り付けられ、右舷機にはついていない。左舷の軸系がちぎれたとき、主タービンは過回転でバラバラになったけれども、繋がっていなかった巡航タービンは軽傷だったのだ。
軸系が切り離れてしまっているのだから、タービンだけ生きていてもどうにもならない。水に漬かっているのではっきりとは判らないけれども、砲弾はどうやら、流体接手の船体への取り付け部を破壊したらしい。回転力は土台に固定していたボルトの残りを引きちぎり、機械全体が全速力のタービンに振り回されて、両方ともが壊れながら荒れ狂い、周囲をすべてぶち壊してくれたように見える。専門家なら、興味深い調査の対象にするだろう。
右舷機の軸系は無事なものの、こちらのタービンはケーシングがパックリと切り開かれ、動くはずがない顔をしている。中の羽根もバラバラに飛び散っていた。もし、こちらに巡航機が付いていて、同じように無事だったのなら、10ノットくらいでは動けただろう。
壊れた部分を入れ替えようにも、大きすぎて手が出せない。造船所のクレーンがなければ、動くようなものではないのだ。取り付け部がどのくらい歪んでいるかもはっきりしない。
軸が暴れたときに歪みが出たらしく、左舷の軸路は浸水している。機関室への漏水の、最大の源がこれなのだ。いろいろな物を隙間に突っ込み、押し当てているけれども、深さがあって水圧が強いために、水は完全には止まっていない。
砲弾の破片でできた船体の破口は、ほとんどが二重構造の内側で止まっている。二重底は水びたしだが、そちらから入ってくる水は多くないそうだ。ほとんどの区画では、軸路からの浸水が流れ込んで、溜まっているだけらしい。
「しっかり記録しておけよ。何かの方法で記録が残れば、後の助けになるし、俺たちが生きていた証にもなるんだ」
生き残っている乗組員の名簿も作られている。艦橋が全滅したために海図や一部の書類はなくなったが、艦尾にあった控えは残った。副長は今日の出来事を可能な限りで綿密に記録している。
四つあるボイラー室のうち、最後部のボイラー室は無事で、魚雷を受けて浸水した艦首側ボイラー室との隔壁を角材で支えている。わずかに蒸気があり、この部屋は暖かい。
「この周りの炭庫だけでも、この程度に焚くだけなら二日や三日は持ちます。運んでくればもっとね。でも、蒸気を送る先がありません」
キャプスタンとか、いくつかの蒸気機関は動かせるが、肝心なものは電動になっていたので、まったく役に立たない。氷を溶かすための蒸気ホースがあり、艦のどこへでも、入れる限り蒸気を引くことはできる。しかし、その先に蒸気を使うための機械がない。
今は艦内の暖房だけをしている。循環ポンプは動かないが、どうせ蒸気管系はズタズタなので、末端を開け放しているのと同じことになり、蒸気が送れている。破断した部分を適当に回避して、艦内には蒸気の通り道ができている。バルブを開けば蒸気が出るから、風呂も沸かせる。水は自分で汲まなければならないが。
「水はあるのか?」
「いいえ、海水です。じきに壊れてしまうでしょうが、気にしてもしょうがないと思いまして」
副長は苦笑している。ここの機関兵はだいぶ歳をとった男で、昔のボイラーを知っているから、海水を使ったからといっても圧力を上げなければ、ボイラーが右から左に壊れるものでないことを知っている。タービンはすぐに壊れるそうだが、やってみたことはない。
真上の煙突はなくなっているものの、潰れたのではなく断ち切られたので、空に向かって口が開いているだけだ。どういうわけか、ボイラー室へはいくらも弾片が降らなかったそうだ。砲弾の気まぐれというのは、どうにも理解できない。
魚雷は、前から2番目の缶室側面に命中しており、前二つの缶室は逃げる余裕もなく満水した。脱出できた者は一人もいない。3番目の缶室は、浸水そのものは緩慢だったけれども、止めようがなく、逃げ出すしかなかったという。前部のボイラー室と、さらにその前の炭庫が満水したため、直前の水中発射管室が浸水と戦っていた。ここもつっかえ棒だらけだ。
「魚雷はまだ残っているんですね」
「発射できゃせんよ。圧搾空気がないんだ。コンプレッサーが動かないからな」
あの一本を発射するのに、どれだけ苦労したことか。おそらくそのノウハウも、報告書には細大漏らさず記録されているのだろう。
「上の発射管は使えるんですか?」
左舷側のものは二つに折れていた。
「右舷側のはな。魚雷は気室に穴が開いて使えんが、発射管は修理すればなんとかなる」
煙突は倒れかかっていたが、押し潰されてはいなかった。
「魚雷を上げられますかね」
副長は手のひらを上へ向けた。もう、左腕は吊っていない。魚雷室のリューマン兵曹長が、代わりに答えてくれた。
「ハッチをすべて開放し、手動のホイストで吊り上げるしかありませんが、かなり困難です。…いえ、魚雷ではありません。甲板の搭載用ハッチが、開かないのではないかと思います。昇降口のハッチも開けにくいですから。…艦の中央部に大きく浸水していますから、艦は前後部の浮力で浮いています。…全体が歪んでいるんですよ」
ハッチと言っても、通常の開閉自在なものではない。がっちりとボルト止めされた装甲鈑なのだ。無理にハッチを開くと、それだけ強度を失った甲板が歪み、浸水が酷くなるかもしれない。少なくとも、良くなる可能性はほとんどない。そもそも歪んでいるとすれば、ボルトが抜けるかどうかも怪しい。
それで、昇降口は開け放しなわけだ。閉じておいて、いざ開けようと思ったら動かない、は、想像したくない悪夢だろう。
私の思いつくようなことは、とっくに副長が考えた後のようだ。確かに可能かもしれないが、とりあえず敵がいるわけではないし、急ぐ理由はない。それに、上甲板へ上げたところで、発射管までの道のりは障害物だらけだ。
「まあ、それは余裕があったらにしよう。まず、艦をなんとかせんとな」
上甲板に戻り、艦橋界隈で唯一無事な昇降口から外へ出る。他の扉は?
「開かないか、開けっ放しすぎて近付けないかだな。水密性ゼロだから、がぶったら桶で水を汲んでいるようなものさ」
幸い海は静かだが、あまり意味はない。機関室の破口が水面下になったら、それで終わりなのだ。
艦橋はまさに跡形もなかった。完全に破壊され、前マストも根こそぎ傾いて半分に折れている。使えるものは何もない。いつも使っていた昇降口は、コーミングの縁を砲弾が削り取っていて、枠全体が奇妙な形に歪み、扉は押しても引いてもびくとも動かない。
右舷の3番砲は、潰れた艦橋の下敷きになっていて近寄ることもできない。砲員の一人は下敷きになったままだが、助け出す術はないし、すでに動かなくなっているそうだ。
左舷砲は、魚雷の衝撃で甲板が歪んだために根こそぎ傾き、使えないことは明らかである。壊れていない部品を取り外されているので、奇妙にアンバランスな形をしている。
舷側から体を乗り出し、兵の指し示す場所を懐中電灯で照らしてみると、戦艦に撃たれた傷跡が大きな穴になっていた。幸いと言うか、当たった場所は魚雷の命中で満水していたボイラー室だったから、いまさら穴が増えても何も変わりはない。どうりで、損傷の割には傾きもしなかったわけだ。
艦首の右砲は、砲盾が壊れて砲が砲架から落ちており、左砲はくの字に曲がっている。砲弾か大破片の直撃で、折れかかっていると言ったほうが当たっているだろう。
艦が止まってしまった後、装甲巡洋艦から撃ち込まれた最初の砲弾は、艦橋直下の甲板室を砕き、その弾片が右舷側の脚をへし折ったため、艦橋は全体が傾いてしまったのだという。その後も何発か被弾しているから、艦橋は構造そのものが潰れてしまい、さらには火にあぶられて、ただの赤錆びた金屑の山になってしまった。
艦長と砲術長は、艦橋への最初の命中弾で戦死した。司令塔は確かに無事だったが、その後の直撃弾で、装甲に大穴が開いている。貫通はしなかったらしく、砲弾は命中した場所で炸裂したようだ。装甲表面で砲弾が爆発するとこうなりますという、見事な模様が描かれている。
無事だった時も、伝声管以外に生きている機器はなかったし、スリットから外を見るのだから視界は限られている。青天井の後部指揮所とは雲泥の差だったから、あえてここを使おうとは思わなかったのだ。
「後部指揮所は無事なのですか?」
「指揮所は主マストと一緒に倒れたよ。幸い、そのときそこに居なかったから助かったがね」
「運が良かったのですね」
…どうかな。死んでいたほうが気楽だったかもしれない。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
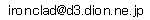
 第1章
第1章
 第2章
第2章
 第3章
第3章
 第1章
第1章
 第2章
第2章
 第3章
第3章
 戻る
戻る

 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る