ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
第四章・漂流・その2
艦首側で生き残った砲員は、何人でもない。この男は、弾薬庫の配置だったので、何も知らずにいたのだ。前部弾薬庫に問題はないものの、昇降口は途中の甲板が浸水しているために使えず、揚弾筒をよじ登って出てきたという。
彼らには、可能な限りの砲弾を運び出し、艦尾砲へ運んでおくように命じた。
いつ沈むか判らない艦で、脱出もままならない真っ暗な弾薬庫へ下りていかねばならないと考えた顔は、懐中電灯の明かりで奇妙に歪んで見える。
「使える砲が艦尾の1門だけだからな。それに、すぐに沈むような状況じゃない。心配せんでいいぞ」、副長が言葉を継いでくれる。
半分しか納得していない顔が仲間へ向けられる。不安な作業を始めなければならないが、軍艦である以上、命令は、それが不可能でない限り、遂行されなければならない。
司令塔天蓋の上にあった主測距儀は、爆風で根こそぎ持っていかれた。高かったのに。…いくらだかは知らないが、砲術長はそう言っていた。
艦首の諸室には、無事なものがひとつもない。どこかに必ず穴が開いていて、波が当たるたびに海水が入ってきている。浸水の多い部屋は諦め、少ない部屋へはポンプを入れて排水しているのだが、乾舷が減れば加速度的に浸水も激しくなる。防御甲板でもある主甲板の部屋は、すでにほとんどが水びたしだ。火災のあった部屋は焼けただれ、焦げた匂いがたち込めている。
「長くは持ちませんか」
「無理だな。朝までは浮いていないだろう」
居住区の排水は、まだ若いホールマン少尉が指揮をとっているのだが、どの部屋が水びたしで、どの部屋に浸水していないか、しっかり把握していた。士官になったばかりで、ほんの若造だが、これだけの経験を積めば、もう立派なベテランだ。あちこちに擦り傷を作ったススけた顔で報告している。
「火災がありましたから、パッキンの類が焼けてしまって、水密が保てていません。水位が上がると、どこからともなく水が入ってきます」
焼けた部屋は、電線の貫通穴などからの浸水が防ぎきれない。それをポンプで排水しているから、沈没が先へ伸びているわけだが、ポンプの数が足らないので、どうにもならない部屋ができてしまう。それゆえ、確実に沈み続けてもいるわけだ。ザルから水を汲んでいるのに等しいな。動力ポンプが使えれば、そのザルからでも、水を汲み尽くせるかもしれないが。
艦は、防御甲板の下に浸水が少ないから、やっと浮力を保っている。堅牢な設計が効を奏しているわけだが、推進機関が全滅するという想定は、そうなればどうしようもないと考えられたのだろう。まさか、あれだけの攻撃を受けても、なお沈まないなどとは想像もできなかったに違いない。
艦首に立って振り返ると、艦の上は滑稽なほどに何もない。暗い中にぼんやり見えるだけだが、およそ見慣れた船の形とは違ってしまっている。
「これが『ヴィースバーデン』なんですかね」
「我が目を疑うよ。…これは、仮に持って帰れても無意味だろうな。元のように再生できるとは思えん」
「あちこち歪んでいますし、機関もバラバラですからね。造船所でも、新しく造ったほうが早いと言うんじゃないですか?」
「だろうな。さて、こうなると俺たちの仕事は、いかに生き残るか、だ」
「艦が長くは浮いていないとすれば、ボートは残っていませんから、イカダでも作りますか」
「それだな。俺は艦をなるべく長く浮かせておく努力にかかる。君は艦内の材料でイカダを作ってくれ。生き残りの全員が乗って、デンマークまで漕いでいける奴をだぞ。イギリスへ流れつくのはごめんだ」
「この風ならデンマークですよ。そんなに遠くないはずですし」
しかし、戦時中に完成した鋼鉄製軍艦というのは、およそ工作できる材料に乏しい。火災が少なかったのは、そもそも燃えるものがなかったからだが、それはつまり、木製のものがほとんどないということなのだ。
艦首の兵員居住区には、まだしもテーブルやらなにやらがあったのだが、かなりが火災で焼けてしまった。戦闘中には消火も満足にできなかったものの、一部は敵が水をかけて消してくれた。
燃えなかった木材は片っ端から引き剥がされる。半分炭になったテーブルも、水に浮く限りは貴重な資材である。集まった水兵たちが、手当たりしだいに運んでいく。
応急資材として準備されていた角材は、浸水した区画の隔壁にあてがってあるので、使うわけにいかない。戦前の巡洋艦のような調度品も少なく、目に付くのは浮かぶはずのないものばかりだ。
それでも、海軍の古参下士官というのは、どこからか何かを見つけてくる連中だ。破壊を免れている後甲板に資材が集められ、手際よくイカダが作り上げられていく。士官室界隈の見慣れた調度品が、つぎつぎに運び出されてきた。艦長室のものもある。
「何人生き残っているんですか?」
「無傷と軽傷者で126人、重傷が1時間前で22人だったな。減っているだろうが」
「500人以上もいたのにですか?」
「呼んで、返事をしたのはそれだけだ。どうしてまだ艦が浮いているのか、不思議なくらいだからな」
開戦直後、ヘリゴランド・バイトで沈められた軽巡洋艦『マインツ』は、437名の乗り組みで、300人以上が救助された。全員がイギリスの捕虜という形でだが。あの艦もボロボロになるまで砲弾を撃ち込まれ、魚雷も命中したとされる。それでも艦上での戦死者は、乗組員の4分の1だった。
『ヴィースバーデン』では、すでに4分の1も生き残っていない。息をしているだけの者も入れるなら、もう少し増えるし、体はまったく無傷だが、呼んでも反応を示さない水兵もいた。精神的に死んでしまっているのだ。
ケガをした者も、何も手当てなどできない。普段なら簡単に治療できるような傷でも、あり合わせの布をあてがって出血を抑えるだけなのだ。軍医は死に、看護能力のある兵もろくに残っていない。漂流することになれば、連れていくかどうかすら問題である。苦痛を長引かせるだけかもしれない。
百人を乗せるイカダが、どのくらいの大きさを必要とするのか、そんな知識は誰にもない。しかし、集まった材料がそれに足らないだろうことは、経験のない目から見ても明らかだった。
「まるで足りませんね。隔壁を補強していた角材も、いくつか外してきたんですが」
木造船なら、船の上半分をバラしてでもイカダが作れるだろうが、鋼鉄ではどうしようもない。甲板の板張りを引き剥がそうにも、今はリノリウム張りになっているから、剥がすべきものがない。
「薬缶が使えればなあ…」
「何をだって?」
「装薬の薬缶です。大口径砲を持っている艦なら、弾薬庫に山とありますから、がっちり蓋をしてつなぎ合わせるとけっこうなイカダができるんですよ」
15センチ砲は薬莢だけだし、使った分は邪魔になるのでとっくに捨ててしまった。薬莢は底に点火用の穴があるし、しっかりした蓋がないから、使ったとしても信頼性は高くないという。
樽や缶といった容器は、どれほど数があるわけでもなかった。その種のものを保管していた倉庫は、ほとんどが艦首にあり、今は水の中か、とっくに焼けてしまったかなのだ。
すでに発射管室より前の防御甲板の下には誰もおらず、その上がほとんどすべて浸水している。さっきも、発射管室より前の区画では、揚弾機を通る以外、防御甲板の下へは降りられなかった。
とにかく、あるだけの材料でイカダを作るしかない。ロープは誰かがどこからか見つけてくる。足らないのは木材だけだ。
「どうだ、こちらは」
「副長、あまり芳しくありません。全員が乗れるだけのイカダにはなりませんね」
「4分の1しかいないのにか。…まあ、ボートも全部吹き飛ばされたからな」
厳しい顔だ。普段楽天的な人だけに、状況がそれだけ難しいということだ。
「こちらも望みはない。少しずつだが、艦は確実に沈んでいる。沈んだ分だけ浸水する穴が増えるから、加速度的に沈没は早まる。2時か3時頃までは持つだろうが、その先は読めん」
今、時刻は22時半を回ったところだ。夜明けまでは浮いていないか。
「小さな穴に木栓や布を押し込んで防水しているんだが、なにせ多すぎてどうしようもない。大きな奴にはシートを被せるんだがな、全部に被せるほどシートはないし、機関室側面のは大きすぎて間に合わん。あれが水中に入ったら、一気に沈むぞ」
とりあえず浮いているのは、機関室への浸水が少ないからだ。浸水した缶室の前後隔壁が破れても、あっというまに沈むだろう。
「これ以上補強を抜かなければ、とりあえずだいじょうぶだ。ん?…なんだ」
「前部弾薬庫のクラスマンです。油で、使えるものはあるでしょうか?」
さっき、砲弾運びを命じられた男だ。後部へ砲弾を持ってきたところで、そのままイカダ資材徴発に命令が変わった。ホッとしたような顔をしていたっけ。
「何に使うんだ?」
「燃します。炎をあげれば、誰か気付いてくれるかもしれません」
燃料油は、衣類に染み込ませて燃せば炎と煙が上がるだろうが、そもそも取り出すのが難しい。海水と混ざってしまっている可能性も高い。
「それが敵だったらどうする?…まあ、海よりは味方に近いだろうな」
副長が初めて、降伏を匂わせる言い方をした。この状況なら当然とも思えるが。
「…残念だが、油は簡単には取り出せない。タンクは前缶室の脇だし、取り出し口は水びたしの缶室の中だ。給油口から吸い出すポンプでもあればいいが、出す方法はないだろう」
「手動のポンプは…」
「全部、海水をかい出すのに使っているよ。それより、タンクへ差しこんで使うようなホースがない。ホースは、内側からの圧力には強くても、吸い出すには使えないからな。だいたい、出てくるのは海水かもしれないんだ。少なくとも左舷側のタンクは無事とは思えん。魚雷の当たった場所のすぐ前だからな」
「ダメですか…」
「いや、アイデアは結構だ。少なくとも、俺はそのことを考えてなかったからな。…みんな、何か思いついたことがあったら、なんでもいい。口に出してみろ。誰も考えつかなかった方法で生還できたら、俺が勲章を貰ってやる。請けあうぞ」
水兵の一人が、恐る恐る手を挙げた。
「ポンプはダメでも、布に染み込ませれば出せるんじゃないでしょうか?」
ふむ、給油管が曲がりくねっていなければ可能性はあるな。やってみる価値はあるだろう。副長は、アイデアを出した二人に古参の下士官を加え、作戦会議を始めた。
「細いロープを芯にして、裂いた布を巻きつける。先に錘を付けて給油口から下ろしてみよう。まず、錘に布を巻いてロープにつけるんだ。タンクまで届くかどうか、やってみるさ。クラスマン、そいつを作ってくれ。フンクは俺と来い、給油口がどうなっているか見てみよう」
右舷の給油口は壊れていなかった。真鍮の口金を回しても、中から空気の噴出する様子はない。油の揮発した匂いがする。
「タンクに海水が入っていても、油は上に浮いているはずだ。匂いはするから空っぽってことはないな」
「これでどうでしょうか」
細いロープの先に、52ミリ砲の砲弾を芯にした布の玉がついている。給油口の中へ差し込み、そっと下ろしていく。それを見て思いついた。
「そうだ。残っている砲弾を捨てさせよう。他にも役に立たない瓦礫を捨てるんだ。いくらかでも軽くなる」
「砲弾全部は捨てるなよ。せめて1発は残しておかんと、助けに来たのが味方だったときに言い訳に困る」、副長は変なことを心配する。
「全部、撃ってしまったことにすればいいじゃないですか」
「それもそうだな。よし、そっちは任す。目方でしかないものは捨ててくれ」
後甲板へ戻ってみると、もうイカダはあらかたできあがり、手持ち無沙汰にしている者も多い。彼らを配置につかせ、艦底の砲弾を吊り出しては海に捨てる。一個45キログラムの15センチ砲弾は、すでにあるだけ甲板に上げられていて、どれほども残っていない。砲戦には使えない照明弾などだけだ。52ミリ砲の砲弾はほとんど全部残っているが、薬莢ともで1発5キログラムくらいしかないから、焼石に水である。
それでも、何もしないよりはいい。余った人数には、手当たりしだいにガラクタを捨てさせる。残しておくのは水に浮くものだけだ。
「ハンモックは、イカダにならないんですか?」
「しばらくは浮いているがな、水を含むと沈んでしまうんだ。布は水より重いんだよ。防水布で包んだところで、どれだけ長持ちもしない」
まったく水を通さない袋のようなものがあればいいのだが、密封できなければいずれ水が入ってしまう。
「蒸気があるんですから、その圧力で水を押し出せないんですか?」
いかにも素人の発想だ。
「蒸気はな、元は水なんだよ。温度が高いから気体になっているだけで、水の中へ吹きこんだら、そのまま水に戻ってしまうだけなんだ」
理解できている顔ではないが、ここで物理の授業をするわけにもいかない。大気圧ポンプかあ、初歩の授業だったな、あれは。
水兵たちが騒ぎはじめた。なんだ?
艦首で火が燃えている。してみると油を取り出せたのか、やってみるもんだな。誰か、あの火を見れば様子を見に来るだろう。ここはデンマークの海岸に近く、彼らの漁場だから、朝になれば漁船が出てくる。夜のうちに出てくる働き者だっているかもしれない。
副長が戻ってきた。
「上手くいきましたね」
「いや、ダメだったよ。給油口にはタンク側にもバルブがあるんだ。ハンドルは缶室の中さ。あたりまえのことで、思い出せなかったのが恥ずかしいくらいだよ。…ああ、あれは燃料油じゃない。烹炊所にあった食料油さ。どれだけあるわけでもないから、いくらも燃せやしない」
「そうですか…」
「石炭ならあるからな、手の届くところにある分をくべてみた。あいつらは、ありあわせの材料でカマドまで作りやがる」
嬉しそうな顔をしている。人間の能力というものを見ると、なにかしか希望の元にはなるものだ。石炭の炎は大きくなりにくいから、遠くから見つけてもらう目的には不向きである。カマドにしてしまえばなおさらだ。
それでも、火には何か魔力がある。交替でポンプをついている乗組員たちは、火の周りに集まって休み、タバコを回し、歌う。重傷者を見に行くと、彼らもまた、苦しい息の下で歌っていた。懐かしい故郷の歌。
もう、日付が替わっている。あとは、いつイカダを海に浮かべ、乗り移るかしか、考えることはない。艦内にあって手の届く場所に残っていた食料と真水は、すべて集められた。信頼できる容器に入った水は、空気を残して浮力を調節し、イカダからロープで海中にぶら下げる。
食料はできるだけ食べてしまうことにした。量は十分にあって、節約しなければならないほど、長い漂流にはならないだろうし、この気温、水温では、長く生きられるはずもない。空きっ腹では、すぐに体が冷えて死んでしまう。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
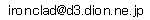
 戻る
戻る

 戻る
戻る

 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る