ヴィースバーデンの時計
SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31
|
第四章・漂流・その3
肉を火であぶって食うという、艦の上でできるとは思えない経験をし、時ならぬ宴会が始まったようで、腹の満たされた男たちは、つかのま楽観的になり、希望を持ちはじめる。
「これで酒があればねえ…」
「お前、それだけは禁句だ。言ったってないものはどうしようもない。そう思って誰も言わずにいるんだ」
「ありゃあいいなあってだけじゃないか。小うるさいこと言うなよ」
「それだけ気が滅入るだろうが」
「俺の知ったことか。ギャアギャア言うんじゃねえよ。カモメじゃあるまいし」
「なんだと…」
こういう場合は、ガタイの大きな私のような人間が出ていったほうが、事は収まりやすい。罵り合っている二人の間に割って入る。
「静かにしろ! これから一晩生き延びる努力をしなきゃならんのだ。余計なことにエネルギーを使うんじゃない」
「だってこいつが…」
言いかけた水兵が、顔を見合わせるなり言葉を止め、噴き出した。もう一人も下を向いて笑いをこらえている。
「どうした?」
「だって、大尉の顔…」
副長が下から覗き込む。
「こいつは無理もないな。昼間の爆風でやられたアザだよ。目の周りが真っ黒なんだ。さっきまでは暗くてろくに見えなかったがな、まるでブチの犬みたいな顔だぞ」
目の周りの殴られたようなアザは、片目でも十分に無様だが、両目では滑稽でしかない。炎に照らされた私の顔は、笑いを誘わずにはいないピエロのようになっている…らしい。
こんな状況ではいさかいも当然で、整然としていられるほうがどうかしているのだが、顔ひとつで人間は笑うこともできる。それを見ることのできない自分は、憮然としているしかないのだが。
突然、ガタンと艦に振動が走り、小さく揺れた。何人かが立ちあがる。
「いかん、何か外れたな」
どこで音がしたのか判らない。副長は缶室の艦首側へ降りていく。私はそのまま走りすぎ、機関室へのラッタルを駆け下りた。カンカンカンと靴が鉄のラッタルを叩く音が、静かな艦内にこだまする。別な足音もする。下から水兵が上がってきた。
「どうした!」
「判りません。急に浸水が増えました。どこから来ているのか判らないんです」
「水が噴き出しているだろう」
「いいえ、ただ水かさが増えているだけで、どこから入っているのか判らないんです。暗くて…」
機関室へのハッチからは、下で騒いでいる声が聞こえる。
「よし、発射管室あたりに副長がいるはずだから、原因は機関室だと伝えるんだ。俺はここにいる」
「ハイッ」
ラッタルを駆けくだり、キャット・ウォークまで下りると、ランプ明かりの中に人影がいくつかある。懐中電灯の光が揺れていた。
「シュタインだ。どうした」
「あ、大尉。軸路ではないようです。ずっと隙間から噴いてはいたんですが、変化はありません。なにか下のほうで音がして、急に水の増えかたが速くなりました。真っ暗で見えませんから、何がどうなっているのか」
すると二重底か? 原因が水中では、何をするにも真っ暗で手さぐりになるし、水圧が強いから、何かをあてがって塞ぐこともできないだろう。グリュンベルグをつかまえて聞く。
「水かさはどのくらいの率で増えている?」
「1センチ上がるのに5秒かかりませんでした」
それだけ激しくては、手さぐりの水中作業で塞ぐのは無理だな。部屋の面積からすれば、かなりの浸水量だ。水面が上がれば速度は落ちるだろうが、隔壁が耐えられなくなるかもしれないし、後部の補機室と繋がってしまっていることも考えなければならない。いずれ時間はない。
「わかった。すぐに上へあがれ。ここにいてもどうしようもない」
上の破口から水が入りはじめたら、ラッタルを上がることも難しくなる。さっき見たときで、破口から水面まで1メートルもなかったのだ。
今、午前2時35分。すぐ脇を水兵たちが駆け上がっていく。グリュンベルグは呆然としてつっ立ったままだ。
「先に行け。イカダを海に下ろすんだ!」
「大尉は?」
「すぐに行く。早くしろ」
「遅れないでください。お願いです」
「だいじょうぶだ」
ランプを持ってラッタルを下り、水の中へ入る。前かがみになり、手すりに水面を探して指を当て、秒を数える。ランプの火の下で、はっきりと水面が上がってくる。恐怖心を押さえつけ、時計を見詰めて水面の上がる速度を計る。人差し指の先端から第二関節までが5センチ。…20秒、30秒、34、35、グリュンベルグが言ったよりは緩やかだが、時間の問題だ。
ラッタルを上がり、ハッチを閉めようとして、無意味なことを思いだした。空気の抜ける穴なら、これよりはるかに広いのがあるんだっけ。周囲の暗闇へ向かって叫ぶ。
「誰もいないか! これが聞こえたらすぐに上甲板へ行け! 聞こえた者は他の者へ伝えろ!」
返事はない。待っていても仕方がないから、上へあがって露天甲板へ出る。水兵が待っていた。
「大尉です。シュタイン大尉が戻られました!」
「よし、それで全員だ。こっちへ来い。艦尾だ」
沈むと判っている艦だ。みんな逃げ足は速い。艦尾の右舷側には、すでにイカダが浮かべられていた。何人かが乗っており、ロープを握って艦から離れないように押さえている。
「グリュンベルグから様子は聞いた。どうにもならんだろう」
「はい。残念ですが…」
副長が全員の不安を代弁した。
「乗れるのか?」
「問題はそこです。全員が乗れば、間違いなくイカダは沈んでしまいます。ですが、ボートとは違いますから、沈没はしないんです。イカダが水面下になり、乗った人間の体が海水に漬かるにつれて、浮力が増して釣り合います。ある程度沈んだところで、止まるはずなのです」
そのために、本来は重ねるはずの材料を広げて作ってある。それでも120人あまりが立ち並ぶのに大きな余裕はない。
「この樽は?」
「それがないと、わずかな不均衡でイカダは大きく傾きます。ひっくり返りはしませんが、滑り落ちてしまうかも」
縁にロープをつけ、空樽やドラム缶がいくつか吊ってある。イカダ全体が水面下に入ったとき、この樽が釣り合いを維持するのだ。
「最初に傾いてしまうと、どうにもならなくなります。まず沈むギリギリの人数まで乗って、後は一人ずつです」
「間に合うのか?」
「さっきは、1分間で8センチくらいでした。せいぜい20分ですね」
「急ごう」
「ケガ人はどこです?」
「おいていく。彼らとも話をしたが、どうにもならん。イカダで夜の海をのりきれる状態じゃない」
一瞬、形容のしようがない感情が湧きあがったが、冷たい現実が目の前にある。半没状態のイカダで、重傷者をどう支えられるだろうか。血液を大量に失っている人間を、冷たい海水に漬けたら…
「…そうですね。ご心中、お察しします」
「俺は冷酷な男だからな。感傷に浸っている余裕はない。行くぞ」
10人ずつ乗り移る。およそ半数が乗ったところで、イカダの上すれすれまで水が来た。樽を浮かべ、ひとりずつ乗っては位置を決めていく。
全員が乗り移り、腰まで水に漬かった状態で、イカダは安定した。樽が半分くらい水面から出るように、吊っているロープを調節する。全員が体を寄せて、イカダの真ん中へ集まる。それでも、端の人間は縁まで一歩半しかない。最後に乗った副長は、皆が体を入れ替えるようにして、人垣の真ん中へと送りこまれた。
懐中電灯を向ければ、機関室の大穴は、もう水面まで30センチとない。波の頭は縁を越え、ほどなく大浸水が始まるとわかった。
「よし、放せ」
ロープが放たれると、艦とイカダは静かに離れはじめた。観察してみれば、艦のほうが風に流されているのだ。半没状態のイカダは、ほとんど風の影響を受けない。…しまった。これでは、デンマークへ流れつくのではなく、行く先はノルウェーだ。距離は倍にもなる。
離れるにつれ、艦の全貌が見えてくる。光はわずかな空の明るさだけだが、その姿がおよそ軽巡洋艦らしくないことは、はっきりとわかる。艦の上に立っているものは何もない。
いや、ひとつだけある。艦尾の旗棹だ。そこにはまだ、海軍旗が掲げられたままになっている。誰かが取り替えたのだろう、真新しい旗のようだ。いくらか強くなってきた風に、揺れ動くのは旗一枚のみ。
午前2時50分、濡らさないようにしてきた時計は、律儀に時を刻んでいる。まだ艦は沈んでいない。このまま離れていき、重傷者だけを乗せた艦が、先にデンマークへ着いてしまうのではないかという妄想が頭をよぎった。そんなバカなことは起きないはずだ。
近かったときには急速に離れていく感じだったが、距離が開くとそういう感触ではなくなる。徐々に離れてはいるのだろうが、そうとは実感できないのだ。
「艦に明かりが見えます!」
誰かが重傷をおして、甲板へ出てきたのだろう。別れを告げているつもりなのか、ランプが振られている。人の塊の中から、名前を呼び、すすり泣く声が聞こえる。友人を残してきた者もいるのだ。
「艦が…『ヴィースバーデン』が…」
沈んでいる。明らかにそれと判る音が、海面を伝わってくる。海水が激しく流れ込み、押し出されて艦内の空気が抜けているのだ。ゴゥゴゥと、ちょうどボイラーの強制通風のような音がしている。
やがて、ドスンという腹に響く振動と共に、すでにシルエットになった艦が、艦首を海中に沈めはじめた。おそらく、水中発射管室との隔壁が破れたのだろう。転覆するか、艦尾が立ちあがるかと思ったのだが、全身を穴だらけにされた巡洋艦は抵抗する余力もなく、大きく傾いただけで、そのまま静かに沈んでいった。
「『ヴィースバーデン』に万歳三唱!」
全員が、声を限りに乗艦へ別れを告げる。シルエットはすぐに見えなくなり、空気の噴きだす音が、ゴボゴボという泡の音に変わった。断末魔の様々な音は水中を伝わり、それぞれの腹へ直接聞こえてくる。北海の海底は浅い。『ヴィースバーデン』はほどなく、その墓場にたどり着くだろう。
すでに、誰も一言も発していない。これで終わったわけではないのだ。これから、126人の生き残りをかけた戦いが始まる。
もう6月だというのに、海水は冷たい。ここに半身を漬けていたのでは、すぐに体温を失ってしまうだろう。副長が声をあげた。
「カイルハック副長だ。全員、よく聞くように」
すぐ近くにいる連中には迷惑なほどの大声。
「我々は艦を失った。これから先、最大の義務は、生きて祖国へ帰ることだ。しかし、状況は厳しい。我々は今、海から生えているような状態だ。立っていられるだけで、座ることも難しい。このまま、誰かが見つけてくれるのを待つしかない」
誰もが、その状況をイヤでも実感していた。腰まで漬かった海水の冷たさは、想像をはるかに越えている。しかし、これが3ヶ月前の海ならば、何を考える間もなく、すでに全員が凍死しているだろう。今が6月だということは、それだけ運が良いとも言えるのだ。
「立っていられなくなった者は、座ってよろしい。横になってもかまわない。そうしたいのならな。死ぬのもお咎めなしだ。…立っていられなくなった者は海面に浮かべ、死んだ者は捨てる。そうすればイカダはそれだけ軽くなり、他の者の体が浮きあがるわけだ。海水に漬かっていなければ、それだけ生き残るチャンスが増える。人数が減れば、イカダは生き残っている者の体を海から切り離してくれるだろう」
誰も、何も言葉を挟めない。厳しすぎる現実は、それぞれの目前に提示されている。
「…我々が重傷者を艦に残してきたことを忘れるな。我々の義務は生き残ることだ。たとえ最後の一人になっても、『ヴィースバーデン』がどれだけ頑張ったかを伝えるのだ。それが、戦死した者、艦と一緒に沈んでいった者たちへのはなむけであり、彼らが生きていたことの証になるのだ」
「…ここに、今日の『ヴィースバーデン』に何が起きたかを、詳細に記した記録がある。お前たち全員の氏名も、最後に艦に残った者たちの名もだ。誰でもいい。生き残った者は、これを司令部へ届けてくれ。けっして恥じるようなものではない。我々が立派に戦い、死んでいった報告書だ。たとえ全員が死んでも、これだけは残さなければならない。これだけが、我々のやってきたことの記録なのだから」
ほんのひと抱えほどの布袋。防水布で作られた袋の中には、濡れても読めるように鉛筆で記された記録が入っている。副長がそれを書き、私が補足し、生き残っていた士官全員が署名した。その中には、右腕を失って艦に残ったベーレンス中尉の、左手で書かれた歪んだサインもある。
まだ奇跡的に動いている時計のゼンマイを巻き、蓋の裏の名前に生きている幸運を感謝してから、濡れないように胸の内ポケットへ移す。午前3時15分。時間が判ったところで、たいして意味はないのだが、何かが止まるというのは、今の状況では耐えがたく不吉なことだから。
しかし、これだけの努力も意味をなさぬほど、北海の水は冷たかった。そればかりではない。乗組員は、今日一日絶え間なく続いた戦闘に、疲労が重なっている。さらには、おとといの出港準備以来、誰もがほとんど寝ていないのだ。立っていること自体が辛いし、睡魔は容赦なく襲ってくる。寒さに震えることも、わずかに残っている体力を消耗させてしまう。
やがて震えることもできなくなると座り込み、冷たい海水に体温を奪われて、二度と立ちあがれなくなる。バランスを失った体は浮きあがり、しばらくは近くの誰かが頭を支えてやって息をさせているものの、低下する体温は肉体の生理限界を越え、ほどなく生命活動は止まってしまう。
乗組員は、ほんの2時間ほどの間にバタバタと倒れ、遺体が捨てられるにしたがって、イカダは海面に近付いてきた。
「俺はいくぞ。こんなイカダにいたら死んじまうからな。東はあっちだ。デンマークまで泳げばすぐさ」
そう言って、止めるのも聞かずに泳ぎだしたものも何人かいた。すぐに見えなくなったから、彼らがどうなったのかは判らない。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
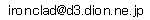
 戻る
戻る

 戻る
戻る

 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る