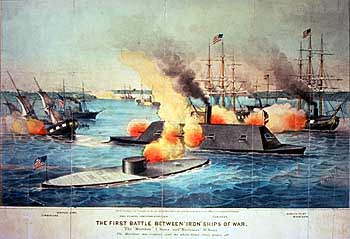
戦闘を描いた絵画・4
この絵ではどうやら、8日と9日の戦いが一緒くたに描かれているようだ。
左側で沈みかかっているのは、『コングレス』か、『カンバーランド』か。
|
翼をなくした大鷲 CSSヴァージニア物語・第九章 Unflyable Eagle: CSS Virginia stories 1862 |
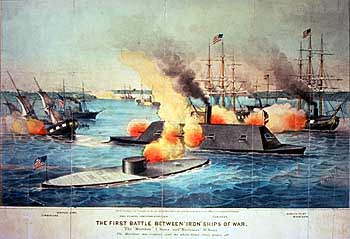
第九章・承前
強烈な衝撃だった。内部の木梁の一本がはっきりと折れ、生木の割れ目が見えている。湯気とも、ホコリの集まりとも見える霞んだ煙のようなものが、あたりに漂っていた。木の匂いがする。たくさんの材木の中に、乾燥不十分で強度の足らないものがあるのは仕方がない。
スパー・デッキへ上がってみると、2枚重ねた鉄板のうち、上側のものが一部折れ飛んでいた。こんな打撃を受け続けていれば、そのうちには突破されてしまう。見下ろせばその装甲の末端は、たしかに水面に届いていない。舷側を流れる波は、装甲の斜面へ上がってきていないのだ。
吃水線付近に弱点がさらけ出されていることは、ジョーンズの意識の中に闇を作り、薄暗く居座る。敵はまだ、ほぼ砲門の高さを狙っているから、気づいていないのだろう。しかし、次のすれ違いで狙いを変えてくるかもしれず、最初の一発が致命傷になるかもしれない。
30分以上かけて『ヴァージニア』が一周する間に、10分ほどの間隔で『モニター』がすれ違い、撃てるだけの砲から砲弾が交換される。何発かが当たり、なにかしらの損傷が積み上がる。『モニター』にも同じような負荷があるのか、知る術はない。
見た者の報告では、『モニター』は砲塔を回したまま射撃していると言う。なぜそんなことをするのか理解できない。どう考えてもこちらには、ある程度近ければ絶対に外れないだけの的の大きさがあるのだ。自分が撃たれないためか? 砲門を狙われるのが、そんなにも怖いのだろうか。それしか弱点がないのか?
次の接近では、それまでより幾分離れたところを『モニター』が通過した。砲弾は1発だけ命中したが、効果のあるような強烈さはなかった。
「敵が回っています! 突っ込んできます!」
砲弾をやり過ごした直後、使われていない砲門から敵を見ていた乗組員が、下から大声で知らせてきた。ジョーンズが頭を出すと、『モニター』は大きく舵を切り、側面へ向かって突っ込んでくるところだった。
「前進全速! 取舵いっぱい! いっぱいだ! いっぱいに切れっ?」
まさか、『モニター』が突っ込んでくるとは思わなかった。速くて小回りが利くのだから、ぶつけるつもりならいくらでもチャンスはあったはずだ。なぜ、今ごろ突然…
艦尾か! きっと水上に顔を出して見えているんだ。そこに当然舵とスクリューがあり、外へ突き出してぶら下げたような、ひ弱な構造だと気付かれたんだ。
ジョーンズの胸に冷たい塊ができ、ゆっくりと腹の中へ沈んでいく。心臓は早鐘のようだ。息苦しくなり、不快な冷たい汗が、真っ黒に汚れた軍服の中を流れる。『モニター』はまるで、意志を持った獣のように飛びかかってきた。鈍重な牛の尾を狙って、敏捷な狼が牙をむき、噛みつこうとしている。
「ぶつかる…」
目が離せなかった。命令は声にならず、するべき命令も考えつかなかった。艦は舵のままに左へ緩やかに回り、はるかに小さな円を描いて、『モニター』が内側へ入ってくる。砲はまったく準備が間に合わない。見ているだけだ。
目をつぶることもできなかった。この一瞬に、350人の運命が決まる。『モニター』の艦首は、『ヴァージニア』の艦尾に牙を立てた。思わず知らず、体に力が入り、身をよじって敵のへさきをかわそうとしている。
轟音とともに振動が走り、艦が行動する能力を失うと、覚悟したその刹那、『モニター』はまったく触れることもなく、艦尾を通りすぎた。間違いなくぶつかったと思ったのだが…。その砲塔の上に顔が見え、びっくりしたような目が向けられていた。
艦内のほとんどのものは、どれほどきわどい状態だったか知りもしない。ジョーンズは膝が震えるのを抑えられなかった。ラッタルの段に腰を降ろし、離れていく『モニター』を見詰める。…後部砲は射撃しなかったな。
「敵が離れていきます。どうかしたんでしょうか?」
『モニター』が、明らかにそれまでと針路を変え、自分たちから離れていく。体当たりに失敗したことで、なにか戦法を変えようと言うのだろうか。まっすぐに進んでいるのでもないから、舵が壊れたわけでもなさそうだ。
「なにか損害を与えたのかもしれんな。よーし、トドメを刺してやる」
危機を脱したジョーンズは、怒りとともに闘志が湧いてくるのを実感している。姑息な手を使いやがって…
「あの方向は浅瀬です。この艦の吃水では無理です」
パリッシュが指差すとおり、『モニター』は浅瀬へ近づき、『ヴァージニア』が絶対に入れない深さのところに停止した。何をしているんだろう。
「ミスタ・ウッドを呼べ。ここへ来るように」
後部7インチ砲を担当しているウッドは、汚れた顔をラッタルの下へ覗かせた。真っ黒くなった顔に目だけが光っている。
「お呼びですか、副長」
「今、敵艦が艦尾を通過したときに発砲しなかったな。なぜだ?」
「見えませんでした。すれ違って、後方から射撃できるように左舷の砲門に砲を突き出していたのですが、外はほとんど見えませんので、タイミングを計っていました。『モニター』は予想よりずっと早く、至近距離で艦尾を横切りましたので、気がついた時には砲門の前を通り過ぎていたのです。誰か、敵の動きを教えて下されば、準備も間に合ったのですが」
「…わかった。敵はどうやら、本艦の艦尾へぶつけようとしたらしい。また同じ戦法を使う可能性があるから、部下を空いている砲門につけて、動きを監視させろ。変化する状況に対処できなければ、士官たる資格はないぞ」
「はいっ、申し訳ありませんでした、副長。誓って次は外しません!」
ビシッと敬礼したウッドは、きびすを返して持ち場へ戻った。
ウッドを叱りながら、ジョーンズは自分を叱咤していた。『モニター』に意表を突かれたのは自分も同じだ。あの瞬間、自分だって思考が止まり、何も指示できなかったではないか。恥ずべきは己だ。
見渡せば、『モニター』は浅瀬から動こうとしない。損傷があったようには見えないけれども、なにか戦闘を継続できない不都合が起きているのは間違いない。
「よし、今のうちに『ミネソタ』を叩くぞ。このままじゃラチが明かん」
気を取りなおしたジョーンズは、初心に戻って敵の主力を攻撃することにした。『ヴァージニア』は三度、一周して『ミネソタ』へ向かうべく、針路を変えていく。じれったいほどにゆっくりとしか、その艦首は回らない。
 戻る
戻る
|
目次へ戻る |
次へ

|
 ガンルームへ戻る
ガンルームへ戻る
|