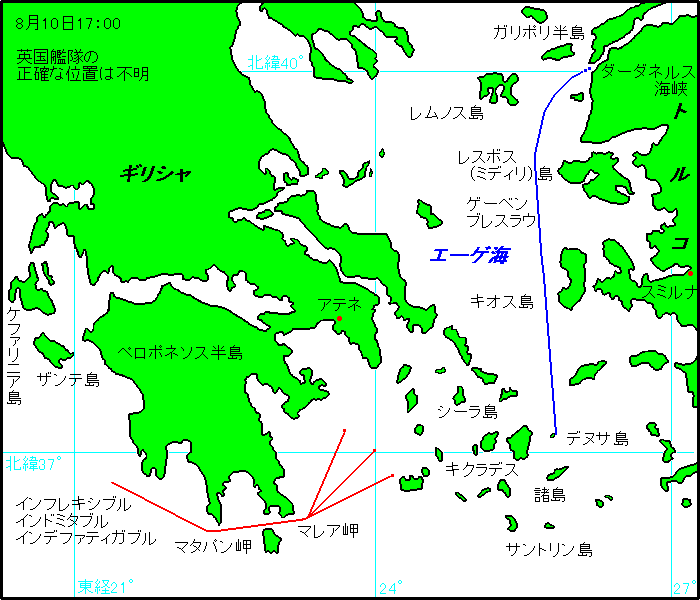
8月10日17時の位置
|
ゲーベンが開きし門 第一部・第十二章 The Goeben opens the gate : part 1 : chap.12 |
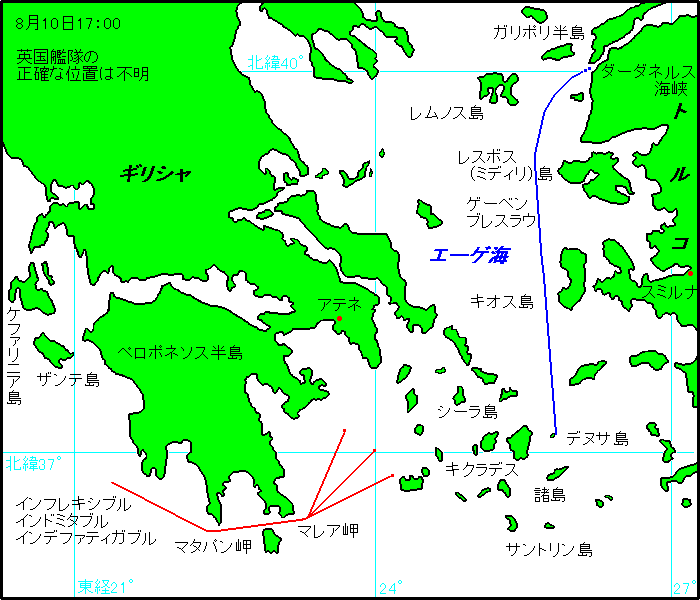
第12章・ダーダネルス海峡
■"Two lone ships"より
8月10日の朝が訪れた。今、重要なのは接近してくるイギリス艦隊から、できるだけ距離を開けたままで移動を始めることだった。載炭は直ちに中止された。石炭船は動きはじめ、私たちは山の上からハイカーを呼び戻す。艦橋から命令が下った。「航海に備えて艦を整頓せよ!」
『ゲーベン』の煙突からは、すでに分厚い黒煙が立ち昇っていた。『ブレスラウ』もまた、真っ青な空へ向かって黒い煙を噴き上げている。錨鎖がガラガラと巻き上げられ、『ゲーベン』を海底に固定していた錨が引き上げられる。そして、艦は滑るように入江から顔を出した。
慎重に、強力な灰色の船体が外洋へと押し出されていく。『ブレスラウ』はその航跡に乗り、後ろへ従った。やがて、十分に広い海面へ出ると、2隻の軍艦は生気を取り戻す。エンジンは力強い蒸気を当てられて回転を増し、スクリューは海水を後方へと押しやる。速力が上がり、艦首が波を切り分け、かすかな振動がやがて明確なエンジンの鼓動となる。目的地はダーダネルス。
夜が明けてから数時間で、秘密の載炭場所ははるか後方に取り残された。焼け付くような日差しの下、私たちはエーゲ海の広い海面を見詰めている。海面は白っぽく見えるほどに輝き、艦隊は快速で航海を続ける。見張りの者たちは、特に目の良いメンバーが後方に集められ、敵艦が吐き出しているだろう黒煙を見つけようと、南の水平線に目を凝らしている。
時間は飛ぶように過ぎ去った。私たちは着実に北へ向かって進んでいる。しかし、この航海には不安がつきまとっていた。ダーダネルス海峡の前で、何者が私たちを待ち受けているだろうか。
この疑問には、猶予がなかった。誰もがそのことを考え、誰もが結果を恐れていた。『ゲネラル』からは、何も有益な通知はなかった。トルコ政府はまだ、海峡通過の許可を出していない。
私たちは未知の領域へ進んでいた。しかし、それはどのような犠牲を払ってでも、成し遂げられなくてはならない問題だった。
滑らかなうねりの中を進む『ゲーベン』は、それに続く『ブレスラウ』から見れば、目がくらむほどの白いしぶきが、船体の側面を洗うように通り過ぎているだろう。それはまるで『ゲーベン』が、泡立つ波に押されているかのようだった。速力のせいで、艦尾は水中に深く沈み、艦首は波から浮き上がっているように見えた。
艦全体が、だんだんに大きくなっているように思われた。長い船体はきれいに片付けられ、がっしりとした砲塔が力強く、強力なエンジンの力によって前へ前へと推し進められていく。うねるような黒煙が、煙突から途切れることなく噴出している。後方に残った黒雲は、しばらくそこに留まり、やがてゆっくりと消えていった。小さな島が見えてくると、程なく後方へ過ぎ去り、置き残されていった。
正午頃、霧が出て視界が悪くなってきた。海は太陽の熱に押さえつけられているようだった。単調で緩やかなうねりの中を、2隻はさらに進んでいく。
テネドス島を過ぎ、艦隊はなおもダーダネルスへ向けて、北へ進み続けている。やがて太陽の角度は低くなり、西の空が壮麗に燃え上がった頃、トロイの古代遺跡が見えてきた。もう、ダーダネルスまではいくらの距離でもない。
時刻は17時を回り、私たちはついにダーダネルス海峡の入口に到達していた。そしてそこには、イギリス艦の影はまったくなく、私たちがついに最後まで、彼らを出し抜き続けたのが明らかとなった。よくやった『ゲーベン』! そして『ブレスラウ』! これは地中海最後の誇り高い航海だった。私たちはさらに東へと進んでいくだろう。
しかし、海峡へ入ってよいという許可は、まだ与えられていなかった。私たちは何をするべきなのか。すでに小アジアの、海へ流れ込んでいるかのような陸地が、細長いガリポリ半島の先端と切り分けられている部分が見分けられる。ダーダネルス海峡はすぐ目の前にあった。
『ゲーベン』と『ブレスラウ』は速力を落とし、やがて1万メートルほどの距離を残して、海峡入口の手前に止まった。海流は海峡から吐き出すように流れ続けているから、私たちは押し戻されないよう、わずかな行き足を残している。
特に必要な配置にいる者以外、すべての乗組員は上甲板に出ていた。あらゆる目が、海峡両側の茶色い丘を見詰めていた。そこには小アジア側にクム・カレの要塞があり、ヨーロッパ側にはセデル・バールの要塞があって、海峡を防御している。三日月旗が、威嚇的な要塞の上で、夕凪のわずかな風の中に揺れていた。
2隻は海峡の手前で止まり、ほとんど動いていない。万物が息を凝らしているかのような、不可思議な静寂がそこにあった。私たちは興奮を募らせつつ、陸地を凝視していた。
重苦しい静寂は、自らの鼓動を感じるかのようであり、陸地は今にも立ち上がるかのように思われた。私たちは案内を待ち、その時間は際限なく長く感じられたけれども、一向に何も見えてはこず、案内者は姿を見せなかった。
耐え難いほどの緊張を伴った時間が過ぎていく。私たちには、何をするべきなのかが判らなかった。静寂は突然、甲高い警報によって引き裂かれた。命令が口々に伝えられる。「戦闘配置につけ!」
全員がいっせいに、イナズマのごとくに走り出した。それぞれが自分の持ち場へ向かって走っていく。短い混乱があり、やがて再びの静寂がすべてを覆った。甲板にはもはや、生気のある何物も残っていなかった。
しかし外から見えない内部では、さまざまな活動のための準備が進んでいる。隠された生命の証として、外から見える28センチ砲の砲塔がゆっくりと回り、砲口が陸上の要塞へ向けられた。砲廓の15センチ砲もまた、頭をもたげて照準を合わせるように回った。あたかもそこには誰もおらず、幽霊がすべてを動かしているような不気味な滑らかさで動き、突然に止まった。
それに応え、要塞にも動きがあった。要塞の砲もまた、仰角を取り、旋回して私たちの方へ向けられたのだ。そこここで同じ動きが繰り返されていく。緊張はいやがうえにも高まっていく。
私たちの砲も陸の砲台に照準を合わせ、そこには髪の毛一本ほどの誤差もなかった。フィリップヴィルへの砲撃以来、砲弾はまだ込められたままだった。次の瞬間、その砲弾はあの砲台に命中しているのだろうか。
いったいなぜ、このような唐突な行動が始まったのか。トルコが私たちの通過を拒絶したのだろうか。私たちは袋の底を打ち破り、私たちが平和裏に欲した結果を得るために、力づくで押し通らなければならないのか。まだ、『ゲネラル』からの通信はない。ギリギリに張り詰めた緊張の糸の先で、私たちは発砲命令を待っていた。
この瞬間、スション提督の脳はあらゆる鋭敏なセンサーをすべて全開にし、知識が総動員されて、猛烈な勢いで解決策を求めていたのである。彼は実際に、要塞の旧式な砲を私たちの新式砲で攻撃し、強引に海峡を突破するつもりなのだろうか。そんなことをしたら、どんな反応が待っているのだろう。結果は恐るべきものであるに違いない。彼は、あまりの責任の重さにためらいを持った。私たちはここへ、戦いをしに来たわけではない。他に選択肢がないから、黒海へ入りたいと望んでいるだけだ。
「後方に煙が見えるぞ!」、これには驚いた。水平線に目を凝らしていた見張りが叫んでいる。確かに煙の影らしいものが見えた。それは二つに増え、さらに増えていく。
イギリスの艦隊だ。
もう逃げることはできない。退路は完全に断たれてしまった。前進するしかないのか?
しかし、トルコの砲は私たちに向けられている。行き詰ってしまった。どうしたらいいのかわからない。鼓動が大きくなり、血管が脈打つのが感じられた。
その瞬間、電光のように新しい考えが生まれた。『ゲーベン』の無線室では、ダーダネルス到着の少し前に、コンスタンチノープルから『ゲネラル』へ宛てた無線通信が傍受されていた。その内容は解読できず、意味不明だったのだが、しかしそれには、待ち望んでいる通航許可が含まれているのかもしれない。
危機の瞬間に拾い出された最後の可能性が、そこにあった。私たちはその可能性を、慎重に推し進めなければならない。素早く、しかし落ち着いた決断をくだした提督は、ひとつの命令を与えた。その命令に従って、『ゲーベン』のマストに信号旗が掲げられる。「水先案内人を求む」
万国共通信号は、マスト高く掲げられた。
ほどなく、ダーダネルス海峡の奥に二つの黒い点が認められた。それは接近するにつれて急速に大きくなっていく。その2隻は、私たちに向かって最大速力で進んでくる水雷艇だった。緊張が大きくなる。
これは魚雷攻撃なのだろうか。それとも、平和的な接近なのか。小口径砲が近付いてくる水雷艇に向けられる。発射準備は完了していた。
信号旗が嚮導艇に掲げられた。その意味を読み取ろうと、すべての目がそそがれる。
「何と言っている?」
「『我に続け』、だ!」
すべては解決した。一気に緊張が解ける。私たちはやっと、忘れていた息を吸い込んだ。
身軽な黒い水雷艇は、海峡の入口へと向きを変え、その航跡を『ゲーベン』と『ブレスラウ』が進んでいく。圧倒的な絶望から解放され、私たちは巨大な安らぎを感じていた。砲は仰角を下げて定位置へ戻され、要塞の砲もまた、筒先を下げた。
私たちは狭い海峡の中へと進んでいく。両側には扁平な丘の連なった陸地があり、私たちはその間に招き入れられている。西に傾いた太陽は暖かく、赤い光が丘のブドウ畑を美しく染めている。村の家々もピンクに染まっていた。
『ゲーベン』と『ブレスラウ』は、海流に逆らってゆっくりと進んでいる。すでに入口の二つの要塞は後方へ離れ、さらに時代遅れの、古びたいくつもの要塞や砲台の前を通り過ぎた。それらは低く、半分以上が壁に隠されていた。
安全な航路は狭くなっていく。私たちはチャナッカレの狭隘部を通過し、ナガラの鋭い先端を回ろうとしている。日没が訪れ、古びた要塞が海峡を見下ろしていた。長い時間の間に風化し、錆びたような赤茶色の壁は、それでも丘の頂上に聳え立っている。
ヨーロッパ側には、キリド・バールの要塞が、狭い水路を見下ろしている。私たちはさらに流れを遡っていく。丘は狭くなり、後退して、そして幅広い丘に代わった。
ナガラの陸嘴は、小さな川を守るかのように突き出している。私たちはゆっくりと艦首をめぐらせ、その内側へ滑り込んだ。
私たちは、敵の艦隊が私たちの後を追って、ダーダネルス海峡へ突入しようとするかもしれないことを、真剣に考慮していた。しかし、この突き出た岬を回ってしまうことで、『ゲーベン』は陸地に守られ、いかなる攻撃者からも保護されるようになったのである。
すでに時刻は19時を回っている。錨が下ろされ、錨鎖の滑り出していく音が全艦内で聞き取られた。夕食は、それまでよりずっと暖かい、好みの味になっているように思われた。当直の一班は緊張を解き、残った者が砲の脇にたたずんでいる。
ダーダネルスに夜が訪れた。最初のイギリス軍艦が、ダーダネルスの沖に視認されたのは、22時頃だったという。私たちは虎口を逃れていた。追跡は失敗したのである。しかし、イギリス艦隊にも通航許可が与えられるかもしれない。それとも彼らは、『ゲーベン』と『ブレスラウ』が決断しようとした、強行突破を試みるかもしれない。時間は熱い緊張を伴ったままだった。
イギリス海軍の提督は、海峡の通航許可を求めたが、これは拒絶された。彼はこれに、あえて逆らおうとはしなかった。彼らがもし、戦うつもりであったなら、それは成功しただろう。後でわかったことだが、このときの海岸の要塞は、役に立つようなものではなかったのだ。
今、『ゲーベン』と『ブレスラウ』は、ダーダネルス海峡の中にいる!
事件を見詰めている世界は、圧倒的に有力な敵艦隊の追及を逃れ、破滅を免れた2隻の軍艦に、その目の焦点を合わせている。不可解な運命が2隻の軍艦をもてあそび、この先にどんな任務が待ち受けているのか、私たちはまだ何も知らなかった。
複雑怪奇な国際情勢の狭間で、私たちがどんな役割を果たすことになるのか、当事者である私たちには何の自覚もなく、世界大戦の方向すら左右する大事件の主役を務めることになるのだなどということは、まったく想像だにされていなかった。
振り返ってみれば、私たちはなんと大胆な冒険を成し遂げてきたのだろうか。フランス領土への砲撃、メッシナからの脱出、エーゲ海での彷徨、ダーダネルスへの到着、『ゲーベン』と『ブレスラウ』は、祖国から切り離された地中海で圧倒的な敵に囲まれながらも、なんら支援を受けることなく、この大業を成し終えたのである。そして私たちは、後にイギリスの歴史家が「歴史を変えた」と評した、敵味方の誰しもが認める大きな役割の一翼を担うことになったのである。
私たちは、この偉大な任務を果たすにあたって、自らの生命をその犠牲とした、4人のボイラー室の気高い仲間に対し、敬意を込めて深い哀悼の意を捧げるものである。

●ドイツ海軍
8月6日に『ゲーベン』と『ブレスラウ』を追うようにして、メッシナを出港していたフィドラー船長の客船『ゲネラル』は、黒白赤の目立つ派手な塗色の煙突を黒く塗り変え、シチリア島東岸に沿って航行した後、シラクザ沖から南へ転じていた。首尾よくマルタへの主航路を横切ると、ポートサイドへ向かう客船を装って航海を続け、サントリーニ島へ向かっていたが、『ゲーベン』からの命令によって進路を変え、スミルナへ9日に到着した。
『ゲネラル』は、大声を発するわけにいかないスション提督のメッセンジャーとなり、ドイツ艦隊のダーダネルス海峡通過にたとえようのない大役を果たしている。
8月9日にドイツ軍令部から発された海峡進入の許可は、スション提督におよそ11時間遅れて到達し、10日17時、海峡入り口に現れたドイツ艦隊はトルコ水雷艇の案内で海峡へ入ると、17時35分にはチャナッカレに投錨している。ただちに『ゲネラル』もスミルナを離れ、11日朝にはダーダネルスへ到着、艦隊に合流した。
交戦国軍艦が入港した中立国の義務として、これの追放もしくは抑留が英仏大使によってトルコ政府へ申し入れられたが、トルコ当局はこれらがドイツからトルコへ譲渡されたものだとして、いずれの要求にも応じなかった。その裏には、開戦の直前に回航予定だった2隻の新型戦艦がイギリス政府に徴発された問題が大きく横たわり、その代替であるという主張に、イギリス大使は口をつぐむしかなかったのである。
8月16日、『ゲーベン』と『ブレスラウ』はドイツ国旗を降ろしてトルコ国旗を掲げ、正式にトルコ海軍に編入された。コンスタンチノープル沖に投錨した2隻には、若干のトルコ人が乗り組んでいたものの、ほとんどは元からのドイツ人がそのまま乗務していたのであり、ただ赤いトルコ帽をかぶっていただけだった。
この、虚構とも言える譲渡が行われた後、『ゲーベン』は『ヤウズ・スルタン・セリム』、『ブレスラウ』は『ミディリ』となり、スション提督はトルコ海軍の司令官に任命された。続いて両艦は皇帝の臨御をあおぎ、トルコ艦隊の先頭に立って観艦式を行い、国民に喝采を持って迎えられたのである。
★ヤウズ・スルタン・セリムは、1512年から1519年まで帝位にあった皇帝で、厳帝というあだ名もあるきわめて冷厳な人物であったとされる。ミディリは島の名で、現在のギリシャ領レスヴォス島のことである。
★開戦直前、イギリス政府に接収されたトルコの新戦艦については、当三脚檣HPの士官室にある「大戦艦」の項を参照のこと。
▲イギリス海軍
スションがデヌサ島での載炭を終えるより1時間ほど前、10日午前4時にミルンの艦隊はマレア岬を通過し、14ノットで北東へ向かっている。ミルンには、「『ゲーベン』は8日、シロス島付近で載炭したもよう」と、通知された。この情報はすでに丸一日遅れており、どれほど役に立つか疑問だったが、問題はミルンが、この情報を正しく解釈しなかったことだった。
彼はまったく行方が掴めないドイツ艦隊を捜索するため、詳細な作戦計画を立てていた。しかし、スションの意図が読めず、この期に及んでも西方への突破を心配していて、巡洋戦艦をエーゲ海の西部にとどめた計画でしかない。
彼にとって、ドイツ艦隊のダーダネルス遁入は大きな脅威ではなく、海峡の入口で待ち伏せるといった、簡単ではあるが袋の反対側の口を開いてしまうような手段は考えられなかったのだ。
10日9時半に『ゲーベン』のものと思われる通信が傍受され、彼らがまだ近くにいると推測されると、3隻の巡洋戦艦と2隻の軽巡洋艦は分散して捜索を開始するが、それはキクラデス諸島の島嶼線の西側、ミルトア海に限られていた。
旗艦『インフレキシブル』を中心にして、マレア岬から各艦は分散し、それぞれに異なった航路で島嶼線まで前進する。軽巡洋艦は途中の島々の間を探索していくが、当然のことに彼らは何も発見できなかった。
丸一日がかりの捜索が無に帰した後、翌11日になって、マルタ島経由の衝撃的な報告が到着する。
「『ゲーベン』と『ブレスラウ』は8月10日20時30分現在、ダーダネルス海峡内にある。この報告の受信を確認せよ。貴艦隊は当座の処置としてダーダネルス海峡を封鎖し、監視すべきだが、機雷の危険があるため海峡外に留まること」
この元情報はダーダネルス界隈にいたイギリスの副領事から発されたものだが、通信は大幅に遅れ、ロンドンがこれを受信したのは発信から14時間後となり、ミルンへはさらに6時間後になって到着している。
ミルンは折り返し海軍省宛に問いを発している。「ダーダネルス海峡は全艦船について通行を許可されているのか? それともドイツ艦にのみ許可が与えられたのか? もし公式に封鎖されるのであれば、本国政府による宣言が為されるのであろうか?」
海軍省はこれに対して、「公式な封鎖ではない。単に敵巡洋艦の出現に備えるだけである。慎重に監視せよ」と答えている。
イギリス艦隊がダーダネルス海峡入口に到達したのは、軽巡洋艦『ウェイマス』が最初で、ドイツ艦隊の通過からすでに24時間が経過していた。開戦から一週間、8月11日の午後遅くになって、ドイツ艦隊が逃げ込んだ袋小路の門は、ようやくのことに鍵を掛けられたのである。しかしすでに、主力どころか、捨石になってなんら不思議ではなかったはずの客船『ゲネラル』や、低速の貨物船『ロドスト』までもが門を抜けてしまっていたのだ。
海峡から3浬の位置に『ウェイマス』が接近すると、2隻のトルコ海軍水雷艇が姿を見せ、停止を要求した。『ウェイマス』は艦を止め、水雷艇は軽巡洋艦を一周して旗と艦名を確認し、『ウェイマス』からの水先案内人を要求するものを含む一切の信号を無視して、海峡内へと戻っていった。
『ウェイマス』のチャーチ艦長は、艦を流れに乗せて漂流するまま、岸に近づけた。陸岸までおよそ1浬に接近すると、要塞の大砲は2発の空砲を発射し、警告を発すると同時に砲を軽巡洋艦へと向けている。重ねて要求された水先案内人派遣の要求は、「応じられない」という返答で拒絶された。『ウェイマス』はその場から動けないまま、夜を明かすことになる。
翌朝、水雷艇がトルコ陸軍中尉を運んでくると、彼は『ウェイマス』に乗艦し、ブロークンな英語で2隻のドイツ軍艦がコンスタンチノープルにあり、トルコ政府へ譲渡されることになっていると説明した。
チャーチ艦長は、『ウェイマス』を海峡内に入れる許可が得られるかどうか尋ねたけれども、中尉はまったく問題外であると返答している。
『ゲーベン』と『ブレスラウ』が自ら押し開けた扉は、イギリス海軍に対して明確に閉ざされてしまった。2隻のドイツ巡洋艦は、『ヤウズ・スルタン・セリム』と『ミディリ』になり、歴史の流れに大きなクサビを打ち込む存在となったのである。
それでもこの段階では、2隻は連合軍にとって漠然とした脅威でしかなく、トルコがこれらを抑留せず、武装解除しないとしても、自由な活動を許すはずもなく、地中海にとっての危険性は大幅に軽減されるとしか受け止められていなかった。トルコが敵対して戦争に加わる可能性は、無視できないにせよ大きくはなく、失敗はあくまで地中海艦隊の問題であって、戦争全体に影響が及ぶとは考えられていない。
しかし、2隻の存在はトルコ民心にとって巨大な意味を持ち、歴史の流れを動かしてしまう。この戦争を4年も続く世界大戦にし、いくつかの国体を消滅させる結果を導いた根のひとつは、明らかにここに端を発している。この2隻、なかんずく『ゲーベン』のコンスタンチノープル到達が、この戦争において歴史を変えたと評価されているのも、けだし当然と言えよう。
第12章終わり
 前へ
前へ
|
次へ

|
 士官室へ戻る
士官室へ戻る
|