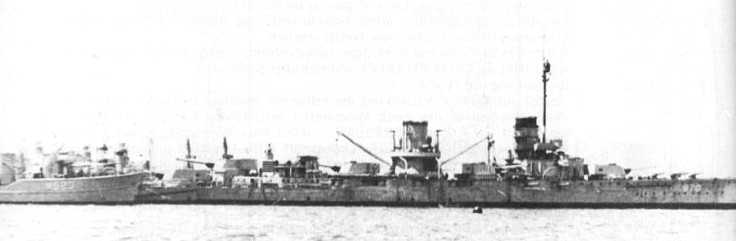
1941年の撮影とされる『ヤウズ』
NATOナンバーが記されているし、艦尾側に写っている掃海艇は、1950年代末にカナダから譲渡されたクラスのようなので、1960年代の撮影だろう。
上部構造物にほとんど手が加えられておらず、近代化改装がごく限定されたものだったことが窺える。後マストが見えないけれども、これは対空砲の射界を遮るからという理由で切り取られてしまったものだ。
|
ゲーベンが開きし門 第四部・第五章 The Goeben opens the gate : part 4 : chap.5 |
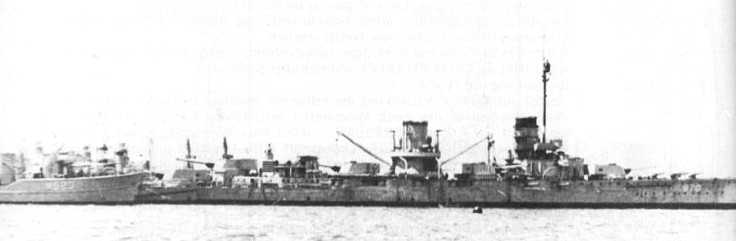
第5章・『ヤウズ・サルタン・セリム』
■"Two lone ships"より
すでにどこにも戦争の騒音は残っていない。この世界が平和を取り戻してから何年にもなるのだ。しかし、戦いの間に起きたさまざまな出来事は、なかなかに忘れ難いものである。
1914年から18年にかけての出来事は、すでに現実だったとは思えないほどに遠く霞んでいるものの、静かな時間の中で記憶をたどれば、いろいろな記憶が断片的によみがえってくる。
あるとき私には、所用でコンスタンチノープルへ行く必要ができた。近東へ戻るのだ。
その日、私は金角湾のスタンブール橋のたもとにたたずんでいた。青いボスポラスへ向かって歩き出すと、穏やかな流れが静かに私を迎えてくれる。目の前にコンスタンチノープルの明るい町並みが開け、永遠の都市は再び、私に呪文を投げかけたのである。
戦後の激動の中で、オスマン帝国は倒れ、多くの事物が変化していたけれども、コンスタンチノープルの生活や色彩は、長い歴史に裏打ちされた壮麗さと豊かさを失っておらず、民衆の息遣いはなおそのままに受け継がれている。首都は内陸のアンカラへ移り、人々は戦争の傷からのゆっくりとした回復を進めている。
私が最初に考えたことはもちろん、「『ゲーベン』はどこにいるのか?」だった。対岸のアジア側にはイズミッドの湾が開けており、そこにいるはずだった。しかし、私の目はボスポラスの対岸を懐かしくさまようばかりである。
スクタリがあった。兵舎の建物は力強さを保ったまま、かすかに輝いて見えた。そこにはかつて、1万人の兵士が寝起きしていたのだ。どっしりとした壁の上には、誇らしげな三日月旗がはためいている。
私の目は、よく知っている場所を次々にあてどなくさまよい、無数の記憶の断片を浮き上がらせる。
視線はハイデル・パシャ駅に吸い寄せられた。ここでは、長い沈黙を経ながらも、なお消えやらぬ戦争の物語が、強く心に呼びかけようと待っていた。かつての壮大な駅舎は、今は残骸となり、血まみれの記念碑となって、その日に起きた事件を語りかけ続けている。
1917年9月6日、およそ20万人分の軍需物資が、ここハイデル・パシャ駅からユーフラテスとシリアの前線へ向かって送り出されるところだった。何か問題がおき、特別列車は出発を一日延期されている。それは、あるいは運命だったのかもしれない。
いずれにせよ、定められた出発時刻の直前に、列車と駅は大爆発を起こした。大気は爆発の衝撃に打ち震え、炎の塊が空高く舞い上がった。積み込まれていた弾薬が爆発したのだ。
まったく予期されなかった原因不明の爆発が、スパイによる破壊工作と疑われたために、コンスタンチノープルは完全に麻痺してしまった。爆発によって半分ほどが崩落した建物は、まだ修理されずにそのままの姿で残っている。
右手にイズミッドの湾が覗ける。しかし、『ゲーベン』は見えなかった。このとき、ボスポラスの対岸から眺めていた私は、あの忘れ難い軍艦が、心の前を横切っていくのを感じていた。
軍艦は厳しい戦いを生き抜き、無防備となったトルコにあって、貪欲な勝利者がその栄誉の記念碑にしようという目論見からも生き残った。
1918年10月の終わりに、善き『ゲーベン』はセヴァストポリを離れ、コンスタンチノープルへと戻った。そして11月2日、正式にトルコの手に渡されたのである。乗組員はすべてがトルコ人によって代わられ、ドイツ人は汽船「コルコバード」によってニコライエフへ連れて行かれた。そして家路に着いたのである。
『ゲーベン』は戦争の傷跡を残したまま、イズミッド湾の浅瀬につながれた。その船体には、ダーダネルスの作戦で機雷に開けられた大穴がそのままだったから、もし不意に沈没しても大事にならないよう、この場所が選ばれたのである。海底は浅く、すぐに沈座してしまうだろう。
こうした事態は起きなかったけれども、トルコ政府は『ヤウズ・サルタン・セリム』に強い注意を払っていた。勇敢に戦って傷ついた軍艦は、勝った側の政府に嫌われている存在だ。そして『ゲーベン』が静かなイズミッド湾に横たわっている間にも、戦勝国とその処遇を巡って様々な交渉が行われている。
トルコは、外交に目覚しい手腕を発揮し、国家と国民の強い意思を根源として交渉に勝利すると、最終的にローザンヌ会議によって保有を認められ、『ヤウズ・サルタン・セリム』はスカパ・フローの仲間に加わらずにすんだのである。そして、誉れ高き軍艦はイズミッドに繋がれたままになった。
長い戦争の爪あとは、その鋼鉄製の船体に深い傷となって残っている。最初の二つの機雷による破口は、接ぎを当てただけに近く、さらに加えてダーダネルス沖での三つの大穴がある。
エンジンやボイラーが能力を取り戻すためには、完全なオーバーホールが必要であり、トルコはいくつかの造船会社との長い交渉を行っている。工事は最終的にフランスの会社に委託された。
まず何よりも、浮きドックが必要である。ようやくその準備が整えられたとき、『ヤウズ・サルタン・セリム』は、ほとんど海底に触れんばかりになっていた。
いくつもの大きな困難が克服され、完全な修理が実現するまでには、何年もの時間が必要だった。そしてついに、装甲巡洋艦は再び軍役につく準備を整えたのである。
ある日、『ヤウズ・サルタン・セリム』は、突然にコンスタンチノープル沖に現れた。このニュースは驚くべき速さで町を駆け抜けていく。マルマラ海を望めるあらゆる場所で、熱狂的な群集は青い海を眺め、そこに浮かぶ力の象徴である軍艦を見付けて、嬉しそうに語り合うのだった。
マルマラ海での公試は、満足される結果をもたらした。『ヤウズ・サルタン・セリム』には、再就役する準備が整っている。その輝かしい日は、1930年3月28日と定められ、トルコの晴れやかな祝日となった。
我らが『ゲーベン』の戦後の運命は、こうした道をたどったのだ。今はトルコの旗を翻し、トルコ人によって操られて、誇らしげに海上を進んでいる。
そうした過去の出来事が私の脳裏を駆け抜けていく一方、私の目はまだ巡洋戦艦を探して、イズミッドの湾をさまよっている。そのとき、マルマラ海にひとかたまりの煙雲が現れた。私はその煙をよく知っていた。あれは『ヤウズ・サルタン・セリム』、いや『ゲーベン』そのものの煙に違いない!
青い空を背景にすらりとしたマストが見えてくるまで、長い時間はかからなかった。やがて美しく整備された船体が水平線に現れ、海面から聳え立ったのである。
まさに『ゲーベン』だった!
その姿に魅了され、小気味よい動きでボスポラスを目指してくる軍艦に、私の視線は釘付けになっていた。そして『ゲーベン』は、プリンス島の近くに錨を下ろしたのである。ありとあらゆる思い出が、ほとんど痛いほどの勢いでよみがえってきた。私は、人生の何年をも共に過ごした、固い絆で結ばれた誇らしい軍艦を見詰めている。
太陽は深く西へ沈み、薄暗い影が忍び寄ってくる。胸には疼くような心臓の鼓動が響いている。それでも、運命の嵐をくぐり抜けたドイツ帝国軍艦の最後の生き残りを、世界を揺り動かした灰色の偉大な存在を、瞳の中心に据えたままで、私は立ちすくんでいた。

★補遺
ゲオルグ・コップ氏の「孤独な二隻」は、英語版が1931年の出版とされているが、原ドイツ語版がいつ出版されたかがわからない。
最後の章が明らかに1930年以降に書かれていることと、途中の部分ではそれ以前に公開されていたはずの、ドイツ公刊戦史 (1928年に和訳が出ている) との矛盾が目につくことが疑問を呈する。あるいは原出版のドイツ語初版には最終章がなくて、後に書き加えられたのかもしれない。また、原著作が書籍の体裁をとっていなかった可能性も考えられ、もしかしたら雑誌の連載記事のようなものだったとも考えうる。
第一次世界大戦の終結後、敗戦国であったトルコが、どうして主力艦である『ヤウズ・サルタン・セリム』の保有に成功したのかは、ある種の謎である。その国家防衛に必要であるというならば、イギリスに余っていた防御的性格の強い旧式戦艦をあてがうほうが、よほど現実的だろう。実際問題としても、いつ沈むかわからないような壊れかけた軍艦より、無傷の戦艦のほうが扱いやすいはずだ。
これにはいくつかの理由が推測できる。
・船体にできた損傷が大きく、とうてい作戦に耐えられる状態ではなかったこと。トルコには必要な施設がなく、修理は困難である。危険で修理のための移動すらままならない。
・トルコ政権の交代があり、政情が混乱して交渉が進まなかったこと。
・勝った側で『ヤウズ・サルタン・セリム』の保有に最も反対しそうなロシアが、瓦解してそれどころではなかったこと。
・心情的に、イギリスの戦艦をあてがわれたのでは、トルコ国民が納得しないだろうこと。
逆に、『ヤウズ・サルタン・セリム』をトルコから取り上げるべき理由も列記してみよう。完全に修理され、能力が回復すればという前提だが、
・その速力性能は、巡洋艦にとって依然として脅威であり、周辺国の軽巡洋艦は強大な仮想敵を持つことになる。(多くは元ドイツ艦だったりするが)
・方位盤射撃指揮装置、重油専焼ボイラーは、改装によって装備が可能であり、なお能力の向上が見込まれる。
・黒海側のソ連艦隊が壊滅している。
・エーゲ海側のギリシャに対抗できる軍艦がない。
例えば低速の準ド級戦艦である『ロード・ネルソン』級であれば、こうしたことは大きな問題にならないし、2隻あればカタログ上の砲能力は『ヤウズ・サルタン・セリム』を大きく上回るのであって、防衛を理由にするなら保有しても他国の脅威になりにくい。
イギリスとすれば、大戦末期には予備役にしていた旧式戦艦だから実損はなく、予備部品などの販売先にもなり得る。この時点では軍縮条約は存在しないから、売却または譲渡にも大きな障害はないはずだ。
しかし、修理もされず、曖昧な存在のまま1922年まで放置されたため、主要海軍国はワシントン軍縮条約の結果として保有を許された以外の艦を処分してしまっており、通常ならかなり長い期間放置状態にあったはずの旧式な除籍艦まで、すでに解体または海没処分されている。
これにより、1922年から23年のローザンヌ会議時点では代替に充てる艦がなく、存在する処分留保艦は艦齢10年未満の優秀艦で、『ヤウズ・サルタン・セリム』よりも有力と言えるものばかりだった。フランスには旧式戦艦が多く残っていたけれども、それは当時の彼らには主力であり、とうてい譲渡できるわけもない。
こうして会議では、新生トルコ政府の主張が大きく受け入れられ、『ヤウズ・サルタン・セリム』は、さらに半世紀の余命を得たのである。
大戦後の『ヤウズ・サルタン・セリム』は、本文中にもあるように、ほぼ放置の状態で数年間を過ごしている。1918年のセヴァストポリ進駐の折のドック入りでも、船体の掻き落としと塗装をされたくらいで、ロシア造船所側の能力が失われていたため、破口の修理はなされなかった。
本格的な修理と近代化改装が計画され、ヨーロッパのいくつかの造船所が名乗りを上げたが、結局フランス、サン・ナゼールのペノエ造船所が請け負うことになった。実際の工事はイズミッドで行われたとされており、4年に及ぶ工事で船体は完全に修復され、若干の近代化が行われている。
実際に行われた近代化は、ボイラーに重油混焼機能が持たされたくらいで、射撃方位盤も戦時中に砲塔指向装置が設けられた程度である。
このため、二次大戦時期には大きな戦力が期待できず、またトルコが参戦しなかったために実戦に使われることもなく、ただただ浮いていただけだった。艦名は1930年に『ヤウズ・セリム』となり、1936年に『ヤウズ』とさらに短くなっている。
戦後の一時期にはNATO艦番号を付されているが、1948年には係留されたままとなり、1954年に除籍されている。本格的な方位盤も、レーダー連動の射撃指揮装置も装備されなかった。使用された航海用レーダーは、ポータブルなものだったとされる。
その後放置されていたものの、1973年に売却され、1976年までに解体された。一時は当時の西ドイツ政府へ譲渡しての保存の動きもあったのだが、経費などに見通しがつかず、貴重な巡洋戦艦の現物は失われてしまっている。

 前へ
前へ
|
第1章へ戻る

|
 士官室へ戻る
士官室へ戻る
|