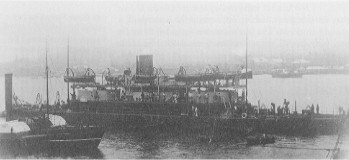
1868年当時の『サーベラス』
|
地獄の番犬ケルベロス(2) The Life of HMVS Cerberus (2) |
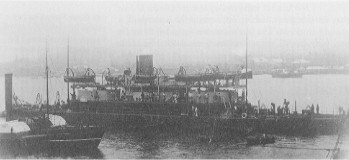
|
●ノーマン艦長の亡くなったのが何年の12月なのか、資料には記載がありません。当時はオーストラリアまで海底電線が敷かれていなかったと思われるので、1869年だとパンターの派遣が間に合わないように思われます。 この場合は新たに派遣されたのではなく、同行していて代理を任ぜられたのかもしれません。香港やシンガポールまでは電信が通じていたはずですから、東南アジアからオーストラリアへの、郵船の往復による命令のやりとりなら辻褄は合います。 1868年の12月とすると、一年以上時間があったことになりますから、経験不足の若い士官を敢えて派遣する理由が見つかりません。ここは、使い走りに連れてこられていた若いパンターが、上司の死によって突然全権を託され、右往左往しながら任務を進めていくと考えたほうが楽しそうなので、そっちだったことにしましょう。 |
|
●この航海では、出発の日時がはっきり判りません。『キャプテン』の逸話が出てくるので、9月は過ぎているはずですから、航海はおよそ半年くらいと思われます。これは当時の所要日数としては長いものではなく、通常の船舶でも遅いものはこのくらいの時間を要しています。 ちなみに、アメリカ東海岸からペルーへ送られたモニターは15カ月、日本まで行った『甲鉄』は8カ月というような数字が残っています。ただし、中国からイギリスへ向かうティー・クリッパーは、喜望岬回りの全航程を100日前後で走り抜けていますから、標準というようなものは存在しません。長距離を駆け抜けられる能力があるか、飛び石式に移動しなければならないか、さらにそれがどれだけ天候と相談しながらでなければならないかで、所要日数はまったく異なるのです。 |
 (1)へ戻る
(1)へ戻る
 (3)へ
(3)へ
|
 ワードルームへ戻る
ワードルームへ戻る
|