ゲーベンが開きし門
第一部・序
The Goeben opens the gate : part 1 : preface
|
このページは、当HP付属の掲示板「三脚檣掲示板・ファイティングトップ」に、2006年7月から2007年10月まで連載された「ゲーベンが開きし門」をコンテンツ化したもので、第一次世界大戦中にドイツからトルコへ譲渡され、「歴史を変えた」とまで言われる大事件の当事者となった巡洋戦艦『ゲーベン』の物語です。
主たる部分は、実際に『ゲーベン』に乗務していたゲオルグ・コップ氏がものした「孤独な二隻」の翻訳であり、当時のドイツ海軍側から見た状況、イギリスを中心とした連合軍側から見た状況を併記する形で、実際の状況とそれぞれの錯誤を書き記したものです。
コップ氏の戦記には、かなり当事者の思い込みや伝聞による誤りが多く、それをいちいち注釈で訂正していると、非常に読みづらくなると考えました。また、実際に起きた出来事がいまさら検証できるわけではありませんから、それが誤りであるという確認もできません。そのため、同じ状況への記述が最大3回繰り返されることになるのを承知の上で、あえてこのような書き方にしたものです。
これは、一般の戦記をお読みになる上でも、そこにどのような誤りが、当事者の思い込みとして発生しうるかという見本にもなるかと思います。また、敵味方双方からの視点を書き並べることによって、それぞれの行動原理を理解する助けにもなるでしょう。一般に流布されているこのときの状況が、現実とどれだけ乖離しているかの指標になるとも思います。
一般の商業誌や書籍では、こうした冗長な併記はやりにくいものですから、いくらでも紙幅が取れるネットコンテンツに特有のものとして、お楽しみいただければ幸いです。
お急ぎの方はこちらからどうぞ
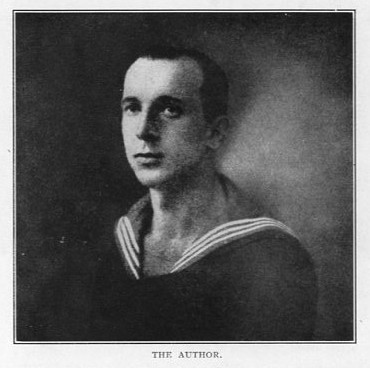
「孤独な二隻」の著者、ゲオルグ・コップ Georg Kopp
このように白縁がつき、英文のキャプションが入っている写真は、「孤独な2隻」に掲載されている挿絵である。
原ドイツ語版にあったものかは不明で、他から流用されたような写真も見られる。
『ゲーベン』の空中写真として、『ザイドリッツ』のそれが載せられていたりもする。
■序
欧州人にとっての「世界」が、ヨーロッパとその周辺に限られていた頃の感覚は、ずっと後の時代まで人々の心に痕跡を残しており、多くの人々は、障壁に囲まれた内世界と、「海」や荒野を隔てた外世界とを、異質なものと受け止めていた。北極の凍った海、果てしのない大西洋、凍てつく不毛の土地や異教徒の住む荒地が、ヨーロッパを取り囲んでいたのだ。
その中でも地中海は、内世界の南方を区切りながらも、別な一面として、アフリカ、アジアという外世界への交通路だった。外でも内でもない、大地の間の海という名のように、その対岸は外の土地でありながら、自分たちと密接に関係してもいる、中間的な場所だったのである。
アジアの存在がおぼろげに知られているだけで、アフリカの内陸は空白、アメリカやオーストラリアがまったく存在すら知られていなかったころでも、地中海は既知の領域であり、恐るべき略奪者の侵入路であると同時に、富の源泉として、またその富を運ぶ通商路として、重要な水路であった。船舶技術の進歩と共に海の向こうの略奪者は影を潜め、利益を産み出す豊饒な海としての地位を上昇させている。1869年のスエズ運河の開通は、その重要性に一層の重みを加えた。
この海の支配は、欧州世界経済に決定的な重さを持つゆえ、海上を支配した英国はここに、ジブラルタル、マルタ、アレクサンドリアという拠点を構えて、最強の艦隊を配置していた。19世紀後半には、その規模こそ本国艦隊には及ばないものの、最新鋭の主力艦が率先して配備されたから、戦力としては旧式艦で水ぶくれしたような本国艦隊をしのぐようになったのである。軍艦そのものにも、地中海での行動を意識した設計がなされている。地中海は英国の動脈であり、行き交う船々は血の一滴にもたとえられた。
この頃、英国にとっての仮想敵は、ロシアが筆頭であり、潜在的には統合されたドイツが意識されるけれども、彼らには海への出口が少なく、地理的に偏っていることから、地中海艦隊にとっての重要性は大きくない。フランス、イタリアが懐柔され、世紀末へ向かってスペインやオスマン・トルコの没落が明確になると、相対的に地中海の危険性が低下してくる。
20世紀に入って、バルト海のロシア艦隊が消滅したために海軍力のバランスが崩れ、急速に台頭してきたドイツがライバルとなるにつれ、北海での脅威が大きくクローズアップされたので、英国艦隊の建造方針や配置は、北海での活動が第一義となっていく。
こうした中、技術革新とともに世界の軍艦の設計思想そのものも大きな変革を遂げ、1906年に英国で『ドレッドノート』が建造されたことから、ドレッドノート級戦艦 (ド級戦艦) と呼ばれる軍艦が、海軍を支配する構造が一般的になる。それまで「守り」の兵器であった戦艦に巡洋艦並みの航洋力が備わったため、「攻め」の兵器であった装甲巡洋艦は、その存在に危機的な状況を迎えることになった。
各国海軍は、非常に高価な兵器であるド級戦艦の整備に忙殺され、これに対抗して攻めの道具たる地位を保持できる装甲巡洋艦の開発は、まったくと言っていいほど進まなかった。どのような能力があれば、ド級戦艦の鋭い爪から逃れつつ、戦力として意味のある存在になり得るのか、手掛かりはほとんどなかったのである。
ド級戦艦の元祖である英国海軍は、これに強烈な回答を用意していた。『インヴィンシブル』級の、12インチ砲多数を装備した装甲巡洋艦の登場である。主兵装は12インチ45口径砲8門で、他には対水雷艇用の4インチ砲と、魚雷発射管を持っているに過ぎない。速力は25ノットと、ド級戦艦より4ノット優速であり、その強大な攻撃力をかわすには、まずまず十分な能力差であった。
この「特型」装甲巡洋艦の出現によって、最も脅威を感じたのは既存の装甲巡洋艦と、逃げようにも追いつかれてしまう小型巡洋艦だった。巡洋艦はもとより戦闘力では戦艦に及ぶべくもないから、その生命線を速力に求めるしかないのだが、軽量な彼らでさえ25ノットから逃れるのは容易なことではなかった。より重く大きい装甲巡洋艦は、これに対してまったく有効な反応ができていない。8インチから10インチ程度の主砲で、せいぜい23ノットくらいの速力では、この俊敏な牙からは逃れられないし、太刀打ちもできないのだ。
その能力は、すでに袋小路の先で飽和していた状況だったから、容易に出口が見つからないのである。
しかし、このように既存の兵器を一夜にしてガラクタにしてしまうような新兵器の開発は、自国にとっても危険な諸刃の剣になりかねず、実際に英国海軍は、この兵器開発によって海軍のバランスを根こそぎ傾けてしまい、これを正常な状態に戻すにはかなりの年月を必要としている。いや、ある意味、そのバランスは戦艦最後の時代まで回復しなかったとも見えるのだ。
装甲巡洋艦の防御力に新開発のタービン・エンジンを積んで25ノットを発揮させ、12インチという戦艦と同等の主砲を装備した「特型」装甲巡洋艦は、あらたに戦闘巡洋艦 battle-cruiser (日本語では巡洋戦艦と訳された) という新種別に分類され、一時は海軍全体を支配するかとも思われた。
しかし冷静に考察してみれば、その性格は基本的なバランスを欠いたもので、彼らの出現によって一気に旧式となった装甲巡洋艦には非常な脅威であったものの、その厳然たる事実は当然に既存種の新規建造を止めてしまうから、獲物となるべき存在は急速に消滅してしまうのだ。そして、もし他国が同じ能力の戦闘巡洋艦を建造した場合、当然に生起するだろうこれとの戦闘は、非常に危険なものになる。どちらもが、鎧を着けずに裸で刀を振り回しているような状態なのだから。
また、新型戦艦並みの価格と乗組員数、これを上回る維持費は、海軍予算に大きな負担となり、当然に数も揃えられないから、存在はこの上もなく貴重なものになる。それでいて脆弱なのでは、この軍艦は思うように使えない床の間の置物になってしまいかねない。また、これによって高価な少数の有力艦は産み出せても、その分、確実に巡洋艦の数は減り、運用に掛かる費用や困難さが跳ね上がったこともあって、配備の自由度は大幅に減少する。
つまり海軍全体としては、戦力の質は向上しても絶対数が減り、「海軍のいないところ」が増えてしまうのである。これは、その存在を抑止力として最良の効果と見るべき軍艦にとって、致命的な欠陥になりうる。各国海軍は、とりあえず予算もないことから、この問題に対する回答を留保し、『インヴィンシブル』に即座に反応した海軍は数えるほどだった。
海軍の新たなバランスはどうあるべきか、答を誤れば国運を揺るがしかねない問題である故に、慎重になった国が多かったのである。限られた予算を投機的な新兵器につぎ込むわけにはいかないからだ。道がどちらへ繋がっているのか、一方で高価なド級艦を整備しつつ、慎重な研究とライバルに先んずる決断が求められた。
こうして、『ドレッドノート』の出現から8年が経過した頃、世界の海軍はそれぞれの更新度合いにあり、新兵器を有効に用いる艦隊システムの研究は、まだ途についたばかりという状況だった。中心に少数の新兵器を配置した艦隊は、満足に体裁すら整えられず、齟齬と矛盾の塊といった風情である。
第一次世界大戦の初期、この問題はあちこちで現実を突き付けられ、いろいろな形で矛盾を具体化した。そのひとつが、ここで語られる『ゲーベン』の物語である。上記のような事情が現実のものでありながら、旧来の戦力が完全には置き換わっておらず、実戦の検証を受けていないために、様々なアンバランスが人々の頭の中と、現実とにそれぞれ別個に存在し、双方のギャップがどんなものかさえ明らかではない、そんな時代の逸話なのだ。
戦争の足音が聞こえ始めていた頃、海上での対立がイギリスとドイツにほぼ限定されていた北海での構図は、互いの主力が睨み合うという形で、ある意味解りやすい図式である。一方、地中海では関連する国家が多く、海軍の更新度合いもそれぞれで、そこには非常に複雑な図式が見られる。同盟関係も複雑であり、情勢の急速な変化は現場を振り回すばかりだった。
そんな地中海にさらなる混沌をもたらすべく、ドイツは新型の巡洋戦艦『ゲーベン』をここへ放っていた。当時の地中海におけるその存在位置は特異であり、速力、攻撃力の両面で、これを単独で上回れる存在はなく、特にその速力は大きな脅威だった。しかしドイツ側にしても、この艦を保護できる場所は持っておらず、簡単に援軍を送れないという地理的事情があって、修理どころか補給、休養すらままならない手に余る存在だったのだ。
帆船時代ならいざ知らず、艦の行動に燃料の制限があり、整備し続けなければ使えなくなる精密機器が欠かせない装備品であって、離れた所と瞬時に連絡のできる無線通信のある時代に、どれほど強力であっても根無し草の存在できる状況は極端に限られる。両軍にとって、『ゲーベン』をどう扱うかは、非常に難しい問題であったのだ。
戦争が始まろうとしていた時期、ドイツをはじめとする同盟国側と、イギリスを筆頭にする連合国側では、互いの意図の把握という面で非常な齟齬があり、政府、軍や情報伝達組織の制度不良、機器的な未熟さに基づく不確実さが重ね塗られて、奇妙な状況があちこちに現出している。
互いに得られる相手方の情報は断片的なものであり、遅れを伴っているため、対応は大きく遅れたり、まったくの見当違いだったりした。ここではこの観点から、その渦中にあった人物のものした戦記を中心に、英独それぞれのサイドから見た状況を書き並べていく。
中心になる視点は、以前に「海防史料研究所」の掲示板で行われた「孤独な2隻」の連載で、底本に用いたゲオルグ・コップの "Two lone ships" を、やはり基本としている。このときにはかなりの抄訳だったけれども、今回はほぼ全訳である。「ほぼ」というのは、私には完全な翻訳ができるほどの語学力がないためであり、誤訳の可能性は常にあることを念頭に置いておいてほしい。
併記される英独両国側からの視点は、なんらかの書物の翻訳というものではなく、あちこちから寄せ集めた内容である。288ページに及ぶ一冊の書物の訳にこれらを加えたため、全体ではかなり長くなるので、とりあえずは最初のクライマックスまでを第一部として公開しようと思う。
"Two lone ships"の著者は大戦中、実際に『ゲーベン』に乗組み、地中海、黒海で戦いながらも無事に生き抜き、終戦時に本国への帰還を果たした人物である。彼はロシア語を話せるという貴重な特技から、開戦後に通信室へ移籍され、多くの秘密を知る立場にもあった。
ただし、これは黒海へ入ってロシアとの対峙が明確になってから行われたことであるから、それ以前の内容については多分に伝聞であり、不自然な部分もある。また、本人の記憶違い、思い込みなどが、当事者の戦記から排除しきれないのは、この種の書物にありがちなことであり、ここでも他の例に漏れない。
また、私の読んでいるのは英訳本であり、独語の原典は手に入れていない。それゆえ、英訳の段階での誤りがあると、変だとは思ってもどうしようもない部分がある。それでは、だいぶ長くなりそうではあるけれども、よろしくおつきあいいただきたい。
―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―
スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。
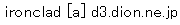
 1
1
 2
2
 3
3
 4
4
 5
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
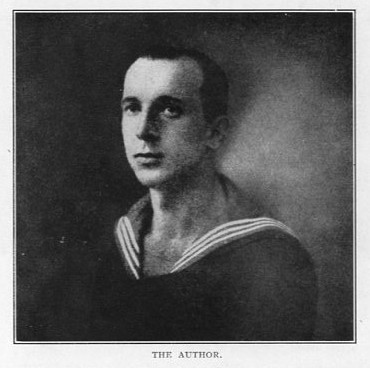
 ゲーベンが開きし門・第1部・第1章へ
ゲーベンが開きし門・第1部・第1章へ